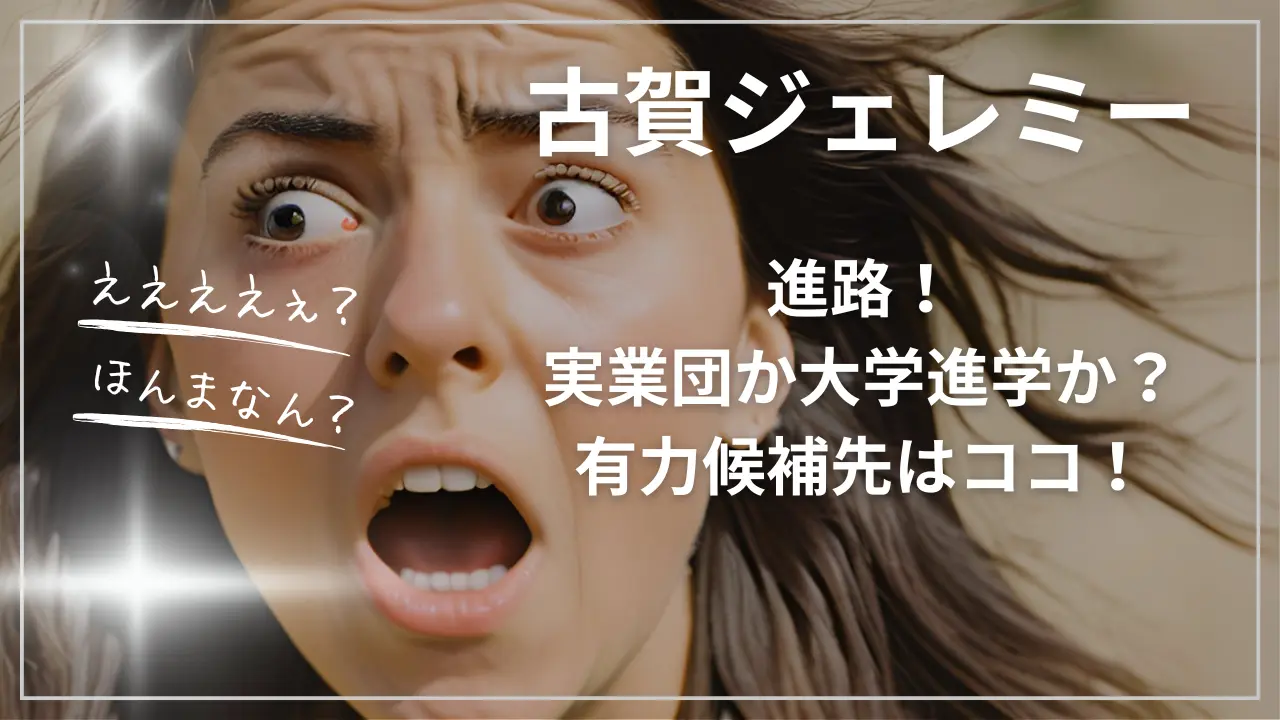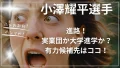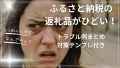現在の有力ルートは「大学進学」です。本人の発言として「大学でインカレ(日本学生対校選手権)4連覇を目指したい」という趣旨のコメントが各種記事で紹介されています。
具体的な大学名は公式には未公表ですが、「強豪大学へ進学する予定」とする報道・まとめ記事が複数あります。一方で、実業団へ直行という情報は、2025年9月30日現在は確認できません。
競技面では、男子110mハードルの高校記録保持者で、2025年インターハイでは13秒18(追い風+2.2m)の驚異的タイムで連覇。U20の世界水準に迫る走りを見せました(追い風参考)。
国際連盟(World Athletics)の競技者ページにも登録があり、主戦種目は110mハードル/60mハードルなど。
要するに、「まずは大学で実績を積み、将来は実業団や世界の舞台へ」という道筋が、今のところ一番現実的で、本人の言葉や報道のトーンとも合致しています。
なぜ「大学進学」が第一候補なの?
ここは、大人目線でも“納得の理由”が並びます。できるだけシンプルに分解してみます。
1) 成長の階段を上りやすい
大学には、専門コーチ、トレーナー、メディカル、栄養サポートが整い、学業と競技の両立も仕組み化されています。高校から世界レベルへとジャンプするには、身体づくり・技術づくり・ケガ予防の三拍子が必要。大学チームはここが強い。
2) 同世代トップと切磋琢磨できる
大学には高校トップ組が集まります。110mHなら日本代表クラスの先輩や同世代ライバルが普通にいます。毎週の練習や記録会が高い“当たり前の基準”を作ってくれます。これは伸び盛りのアスリートにとって大きい。
3) 国際大会へのステップが描きやすい
大学在学中に日本選手権/アジア大会/ユニバーシアードなど上位の公式レースへ挑み、ランキングや派遣標準記録を狙う――王道のルートです。古賀選手はすでに日本選手権でも戦える力を見せており(高校生で入賞の報道あり)、大学でのジャンプアップが期待されます。
4) 本人の目標と一致
記事化された本人のコメントとして、「インカレで4連覇を目指したい」が紹介されています。これは大学競技を舞台にする前提の目標です。
とはいえ「実業団直行」はないの?
絶対に無いとは言い切れませんが、今のところ根拠ある情報は見当たりません。
高校からすぐ実業団入りする選手も稀にいますが、ハードル種目は技術完成度・体力成熟度・故障耐性などの観点で、大学での育成期間を置くケースが多め。
最新の公的・一次情報では「大学名の確定」や「実業団内定」の発表は見つかりません。慎重に言えば、“大学進学の意向が複数報道で伝えられている段階”です。
「有力候補先はココ!」――どの大学が合いそう?
ここはデリケートです。大学名の公式発表は未確認のため、断定はできません。
報道・まとめ記事では「強豪大学」という表現に留まっており、具体名は確証なしで名前が挙がることがあります(例:早稲田・順天堂など)。ただし、これは推測混じりで、公式情報とは言えません。
そこで本記事では、「110mHの育成に実績がある」という一般論の観点で、もし進学ならこういうタイプの大学が“合いやすい”という要件を挙げておきます(大学名の断定はしません)。
- 要件A:ハードル専門コーチの厚み
スプリント・ハードルの技術コーチ/スタート専門/走力強化/可動域・柔軟性など役割分担が明確なプログラム。 - 要件B:メディカル&リカバリー体制
フィジオ(理学療法)・トレーナー常駐、フォーム解析・スプリント測定機器がある環境。 - 要件C:実戦機会の多さ
学連公式戦、強豪校との定期戦・記録会、海外遠征・合宿など経験値が積みやすい。 - 要件D:アカデミックの柔軟性
出場大会・合宿と授業の調整、単位取得のサポート、語学・スポーツ科学など将来に生きる学び。
これらを満たす大学は日本に複数あり、本人と監督・家族が“ベストマッチ”を選ぶ段階だと思われます。公式発表までは、むやみに大学名を断定しないのがフェアです。
タイムライン:いつ“決まる”の?
- 秋〜冬:高校シーズンの締め、各種表彰・強化指定など
- 冬〜春:個別の進学手続・入試・合格発表
- 春〜初夏:大学チームに合流、学連登録、記録会で大学デビュー
- 夏:インカレ・日本選手権など主要大会へ
もちろん、学校・競技状況によって前後します。大学名は、合格が確定し、本人や学校側からの発表が出たタイミングで明らかになるのが通例です。
競技力の“今”を整理
端的に言えば「高校では抜けて強い」「世界のU20でも通用する伸び」「連盟からも将来を見込まれている」。だからこそ、大学での数年が世界の舞台に踏み出す最短ルートになります。
大学に進んだら、何が“伸びしろ”になる?
- スタートと1~3台目
110mHは0~30mの質で勝負が決まることも多い。リアクション・1歩目・重心位置の詰めで、前半の無駄な上下動を消していく。 - ハードル間の“加速維持”
「跳ぶ」より“進む”リズム。大学では接地時間の短縮・設置角度・骨盤の前傾維持など、ミリ単位のフォーム改善を続けやすい。 - 耐久力と故障予防
ハードルは腸腰筋・ハム・臀筋・体幹を酷使。可動域と筋出力の“両輪”を育てながら、年間50本以上のレースを安定してこなす身体へ。 - 風・天候・レーン条件の適応
向かい風の13秒台前半、微追いの12秒台接近――どの条件でも“崩れない”レース運びを磨く。 - 海外遠征の経験
海外のスターター・機材・会場の雰囲気に慣れることは、国際大会で実力を出し切る前提条件。大学はここを後押しできます。
じゃあ、実業団ルートの“良さ”は?
フェアに、実業団の長所も整理しておきます。
ただし、高校卒から直行する選手は短距離ハードルでは少数派。大学での基礎強化→実業団で本格成熟というステップが、故障リスクを減らし、ピークを引き上げるという考え方が一般的です。
「インカレ4連覇」の重さ
“4連覇”は言うのは簡単、実現は超むずかしい。
なぜなら――
- 毎年、ライバルが強くなる。高校トップが次々に入ってくる。
- ケガゼロで4年は神業に近い。風・天候・学業・就活・代表遠征…不確定要素が多い。
- 日本選手権や国際大会との両立は、心身のピーク管理が鍵。
だからこそ、“4連覇”を目標に掲げること自体が覚悟の証明。目標が高いほど、毎日の練習の質が変わります。この“目線の高さ”を感じるコメントが報道で紹介されているのは、強みです。
よくある質問(FAQ)
Q. 具体的な進学先の大学名は?
A. 公式発表は確認できません。強豪大学という報道はありますが、大学名の断定は不可です。正式発表を待つのが確実です。
Q. 実業団直行の可能性は?
A. 現時点で信頼できる一次情報は見当たりません。ハードル種目の育成サイクルからも、大学→実業団が王道です。
Q. そもそも“どれくらい強い”の?
A. 2025年IHの13秒18(+2.2)は追い風参考ながら高校レベルを超えたスピード。すでに日本選手権で上位入賞の報道もあり、U20世界水準に肉薄しています。
Q. 最新情報はどこで追えばいい?
A. まずは月陸Onlineなどの専門メディア、日本陸連(JAAF)の強化情報・記者会見、World Athleticsの競技者ページをベースに。SNSは速報性が高い一方、一次情報の裏取りが重要です。
まとめ
正直に言うと、「高校3年でこの完成度?」と驚く走りです。ただ、短距離ハードルは0.01秒を削る旅。大学の4年間で、スターターの音→1歩目→1台目→ハードル間と、ひたすら“当たり前”を高める作業が続きます。
地味に見えるかもしれません。でも、あの13秒18(参考)の背後には、山ほどの“地味”が積み上がっています。世界へ行く人ほど、地味を好きになっていく。だからこそ、大学→世界という王道を丁寧に歩む選択は、とても理にかなっています。
進学先の公式発表が出たら、改めてカリキュラム・コーチ体制・チーム方針を分析し、「この環境で彼がどう強くなるのか」を深掘りしましょう。
その日まで、私たちは“記録の更新”と“笑顔のゴール”を楽しみに待つだけです。
参考・出典(主要5点)
- World Athletics(競技者ページ):Jeremy KOGA(主戦種目の登録など)。World Athletics
- 月陸Online:2025年IHでの13秒18wによる連覇など、複数記事。月陸Online
- 東京都陸協(東京陸協)ニュース:インターハイ展望で「東京高3・古賀ジェレミー」表記。toriku.or.jp
- 月陸Online タグページ:室内大会の戦績、強化制度関連記事へのハブ。月陸Online
本記事は2025年9月30日(日本時間)時点の公表情報・専門メディア記事・国際連盟データベースをもとに構成しています。進学先など個人の進路は本人・学校・受け入れ先の発表が最優先です。