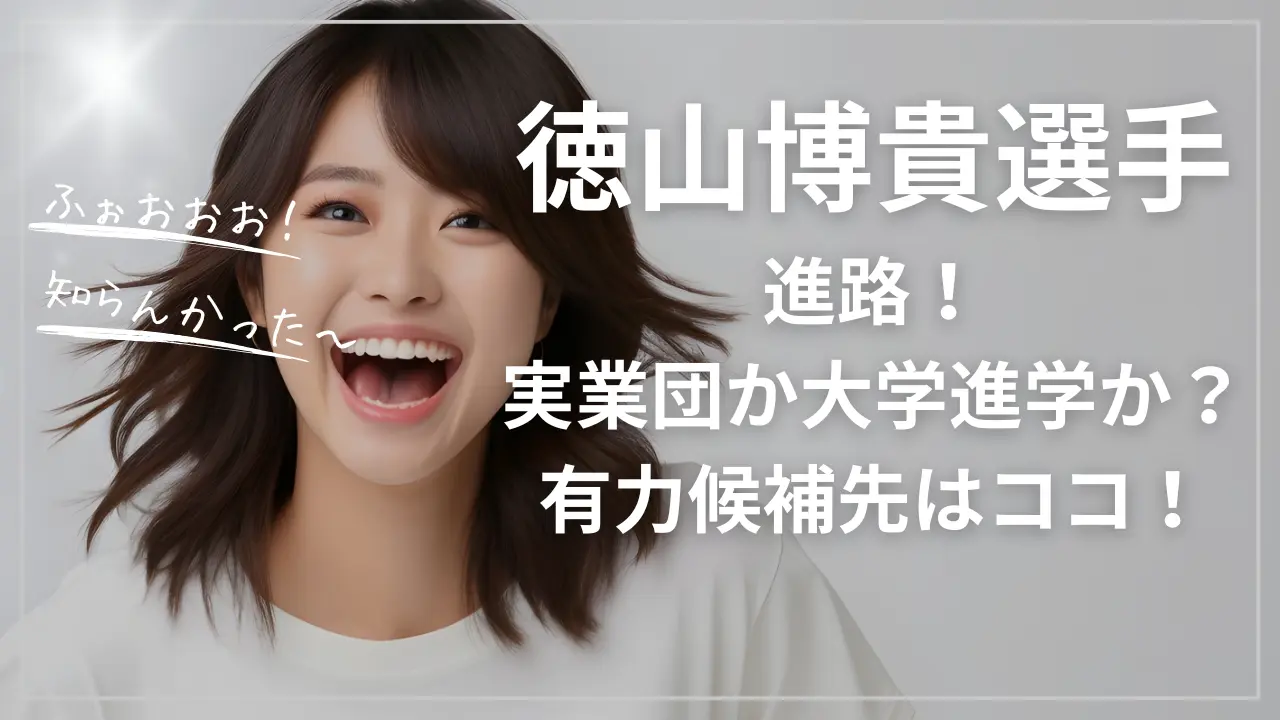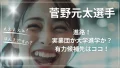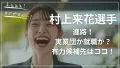2025年の広島インターハイ(全国高校総体)男子3000m障害で、市西宮高校(兵庫)・徳山博貴(3年)が自己新8分53秒04で優勝しました。兵庫勢としては1988年ぶりのタイトル。レースは終盤のラスト勝負を制する、見事な逆転劇でした。
18歳となる徳山選手は、世界陸連(World Athletics)にも3000mSC(障害)を主種目として登録されている新星です。
この記事では、大学進学と実業団(企業チーム)という2つの道について、最新の事実と“日本の長距離・障害種目の育成の流れ”を踏まえて、どちらが本人の成長と目標に合いやすいかを解説します。
徳山博貴選手の現在地(2025年10月時点)
2025年10月3日現在、公式に「進路決定」を公表した一次情報は確認できていません(学校・本人コメント・所属発表など)。本記事の「有力候補」は“育成実績や競技傾向から見た適性の高い選択肢”として提示します。
どっちがいい?「大学進学」と「実業団」の判断ポイント
ここでは、3000m障害という専門性と、日本の育成の現実に絞って考えます。
大学進学のメリット
- 障害種目の専門コーチと環境が充実
日本では3000mSCで世界レベルを狙う場合、大学でフォーム作り・スピード・スタミナ・障害技術を整える流れが王道。
例)順天堂大学は、リオ五輪代表の塩尻和也(現・富士通)が在籍し、駅伝と3000m障害の両立で成果を出してきた実績がある。 - 駅伝を通じた競争環境
箱根駅伝や全日本大学駅伝など、「チームの看板区間+個人種目」の二刀流で鍛えられる。世界で戦うには総合的な走力が必要で、大学駅伝は最適な“実戦の場”。 - 心身の成長に時間を使える
障害は「速さ+技術+耐久力」が噛み合って初めて伸びる。18〜22歳の4年間で体づくり・怪我耐性・レース戦術の幅を広げられる。
実業団(企業チーム)直行のメリット・注意点
- メリット:
- 注意点:
結論(一般論):3000m障害で世界・日本選手権を目指すなら、まずは大学で技術と総合力を磨くのが王道。高校→実業団の直行は、本人の希望・受け入れチームの育成方針・長期目標が一致したときの“レアケース”と考えるのが現実的です。
徳山選手の「走りの特徴」と伸びしろ
インターハイ決勝は、1000m通過2分59秒→2000m通過6分01秒のハイペース展開。徳山選手は一度離されてもラスト1周で再び詰め、残り30mのスパートで抜け出す勝負強さを見せました。
単なるスタミナ型ではなく、終盤で脚が残るスピード耐性と障害処理の安定感があるタイプ。
さらに、駅伝・トラック双方に出場しながら自己新を更新している点も成長の証。高校段階で8分台後半は全国でもトップレベル。
「8分40秒台〜30秒台」が見えるポテンシャルがあり、大学の強化で一気に国際水準へ近づく可能性があります。大会レースへの継続出走歴は、駅伝歴ドットコムでも確認できます。
有力候補:タイプ別にみる「大学」&「実業団」
ここからは“適性に合う可能性が高い選択肢”を、実績と育成スタイルの相性からタイプ別に示します。“内定・決定”ではありません。
大学進学(第一候補ゾーン)
- 順天堂大学
- 順天堂以外で“障害強化+駅伝両立”を重んじる中長距離名門(例)
実業団(直行の可能性を検討するなら)
- 富士通/Honda/GMOインターネットグループ
三浦龍司(高3でU20日本記録→順天堂→世界入賞)もまずは大学を選び、その後SUBARUで競技継続という“王道”を辿っています。「大学で磨き、実業団で花開く」のが現在の日本の主流です。
もし大学進学なら——4年間の“勝ち筋”プラン
- 1年目:障害技術の安定化(ハードル間のリズム、着地後の再加速)/1500m・5000mの“純スピード”向上
- 2年目:8分40秒台への到達を狙う(日本インカレ決勝で勝負)
- 3年目:国際大会(U20/学生選手権・アジア)への出場ラインを目指す
- 4年目:8分30秒台へ接近、日本選手権で表彰台→実業団内定&代表争いへ
目安:日本トップクラスは8分20〜30秒台。塩尻和也は8:27.25。国内で勝ち負けしつつ、世界大会の参加標準を見据えたタイムづくりが鍵。
もし実業団直行なら——配属先の“見るべき条件”
例:東日本の主要チームの対抗構図(富士通・Honda・GMO など)は、毎年ニュースや連盟発信で確認できます。入団後の駅伝区間起用方針も、選手の成長に大きく影響します。
市西宮高校という土台——“伸びる人”の習慣
市西宮は進学校としての学習文化と、陸上部の規律と自治が特徴。
朝練・清掃ジョグなど“生活の積み重ね”を大切にするチームカラーは、大学や実業団に進んでもケガをしにくい生活設計や継続できる練習習慣につながります。
Q&A:よくある疑問
Q1. 高校から実業団に行っても大丈夫?
→ 可能ですが、長距離・障害では少数派。多くは大学を経てから実業団入り。18歳は伸び盛りの時期。育成に強い大学で基礎を固めるほうが、ケガを避けつつ天井値を上げやすいのが現実です。
Q2. 徳山選手は駅伝も強い?
→ 兵庫・近畿の駅伝や各種大会に出場しつつ、トラックで自己新&全国制覇。駅伝の適性も期待できます。
Q3. 8分53秒ってどれくらいすごい?
→ 高校生として全国優勝レベル。大学での鍛え方次第で8分40〜30秒台を狙える実力の“入口”にいます。
本命シナリオ(当サイトの見立て)
いずれの道でも、徳山選手のレース巧者ぶり(残り1周のギアチェンジ)と障害技術の安定化が磨かれれば、日本選手権で表彰台争い→代表レベルが現実味を帯びます。
まとめ——“可能性のボトルキャップ”を開けるのはどの環境か
最後に:高校王者になった今が“出発点”。どの道を選んでも、自分の強み(終盤のキレ・障害の安定感)を伸ばせる環境かどうか——それが、徳山博貴という才能のボトルキャップを開ける合図になります。静かな積み重ねを続ける姿勢は、大学でも、実業団でも、必ず武器になるはずです。