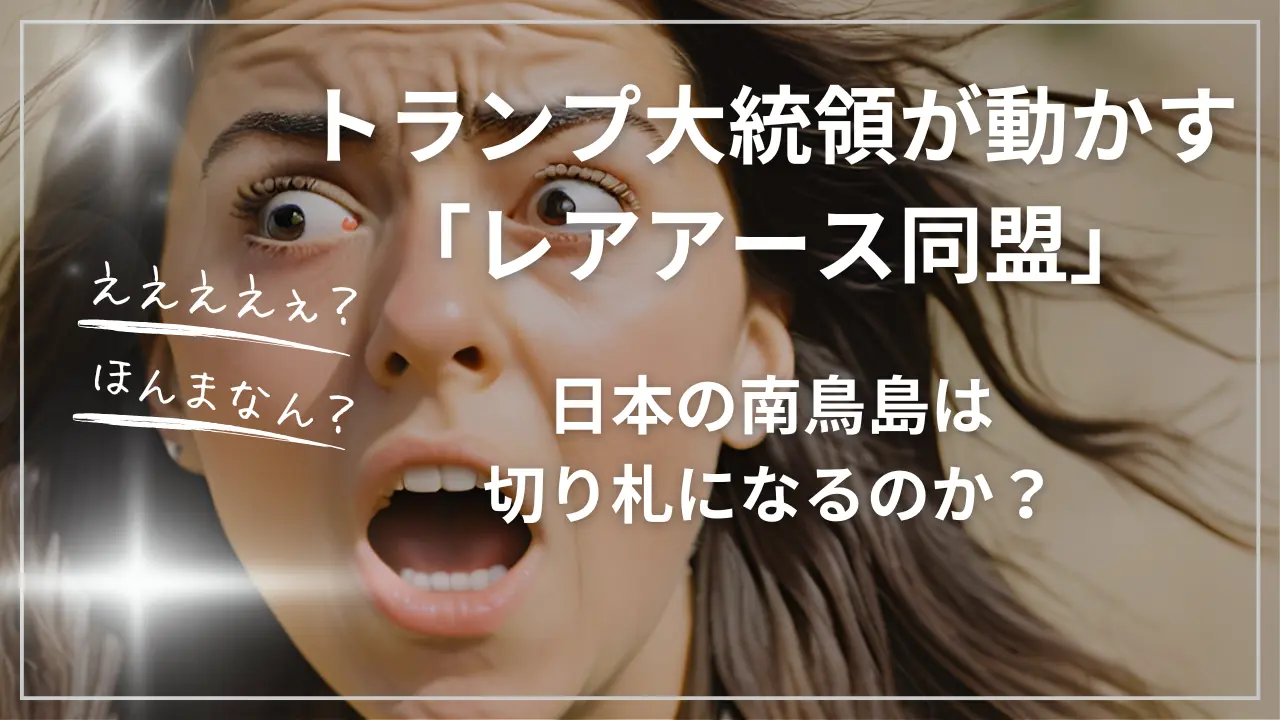- 米国はオーストラリアや日本と手を組み、「中国に依存しないレアアース供給網」を本気で作ろうとしています。トランプ政権は豪州との大型投資を後押しし、日米でも技術・オフテイク(長期引取り)で動きが出ています。
- 日本の「南鳥島(みなみとりしま)」近海の深海には、重希土類を多く含む“レアアース泥”が広く分布していることが研究で示されており、2026年に試験採掘が始まる計画が動いています。中長期的に“切り札”になり得ます。
- ただし、深海5,000m級の商業化は技術・コスト・環境のハードルが高い。すぐに大量生産できるわけではなく、「豪州など陸上資源の即効薬」+「南鳥島の長期カード」を組み合わせる現実路線が必要です。
なぜ今「レアアース同盟」なの?
レアアース(希土類)は、EVモーター、風力発電、スマホ、半導体装置、軍事レーダーなどに欠かせない“縁の下の力持ち”です。世界の精製・磁石製造は長らく中国が圧倒的で、輸出規制や価格変動が起きると、サプライチェーンが一気に不安定になります。
この弱点を補うため、米国は同盟国と「中国に依存しないサプライチェーン」を作る方向に舵を切っています。 10月20日、トランプ大統領はAUKUS(米英豪の安保枠組み)を再確認すると同時に、豪州との重要鉱物・レアアースへの共同投資に言及しました。狙いは“対中依存の低下”です。
さらに直近では、米豪間で約130億豪ドル規模(報道)の枠組みが取り沙汰され、豪州のレアアース鉱山やガリウムなど周辺素材の増強が進みます。これは短中期の供給力を底上げする即効薬になり得ます。
日本もこの流れに乗っています。2025年6月、日本は対米関税協議の場でレアアース協力を提案。産業政策として、技術供与や長期の引取り(オフテイク)といった実務的な連携が前進しています。
日本の“切り札”:南鳥島レアアース泥とは?
南鳥島は東京の南東約1,800kmにある日本最東端の島。周辺の深海には、レアアースやイットリウム(REY)を高濃度で含む“レアアース泥”が広く分布していることが、大学・研究機関の調査で示されています。
2018年の東大発表や2018年の査読論文(Scientific Reports)では、世界の陸上埋蔵量を上回る規模のポテンシャルや、重希土類(HREE)の比率が高いというメリットが紹介されています。重希土類は高性能磁石のキーパーツで、供給が特に不安定になりやすい元素群です。
最近の研究でも、この“泥”の成り立ちや層序が詳しく更新されており、学術的な裏付けは年々厚くなっています。
「いつ取れるの?」時間軸がカギ
すぐに大量生産、という話ではありません。日本政府や関係機関の発表・報道ベースでは、
- 2026年:試験採掘(トライアル)を開始
- 2027年:パイロット抽出(小規模実証)へ
というロードマップが示されています。これは“工業化の第一歩”ですが、商業生産の本格化には、回収・揚泥・選鉱・分離のコスト・信頼性・環境配慮をすべて満たす必要があります。
深さは約5,000〜5,500m級。世界最先端のオフショア技術が必要で、パイプの強度、ポンプ、詰まり対策、連続運転など、地味だけれど難しい工学課題が山ほどあります。
それでも“切り札”と呼べる理由
- 重希土が豊富:南鳥島の泥は重希土:軽希土がおよそ50:50という報告があり、中国の陸上鉱床(25:75)に比べて希少な重希土が相対的に多いのが強み。磁石やモーターの高性能化に直結します。
- 資源量のポテンシャル:世界需要を長期間まかなえる可能性が学術・報道で繰り返し示唆されてきました。もちろん実際に“掘って運んで精製”できて初めて供給になりますが、長期カードとしての存在感は非常に大きい。
- 日本のEEZ内:地政学リスクが相対的に低く、国家戦略として育てやすい。同盟国との技術・資本連携で、中国リスクを分散しやすくなります。
トランプ版「レアアース同盟」と南鳥島の関係
トランプ大統領は、豪州との資源連携を実務レベルで前に進め、日米間でも技術・引取りの合意が積み上がっています。これは短中期の“陸上”供給を厚くする策です。
一方で日本は、南鳥島という“超長期の切り札”を持っています。米豪で「今すぐ増やせる」供給を支えながら、南鳥島で2030年代の商業化を目指す——そんな二段構えが現実的なシナリオです。
政権が「同盟での資金・装置・人材の流れ」を作れば、日本企業が深海技術を磨き、コストを下げる時間を稼げます。
環境とルール作り:避けて通れないテーマ
深海はまだ知られていない生態系が多く、採掘が海底に与える影響(濁り=プルーム、微生物群、炭素循環など)に国際的な関心が高まっています。
商業化の前に、環境影響の基礎データ収集、モニタリング技術、国際ルール(ISA等)との整合が必要です。南鳥島の試験は、科学的データを積み上げ、影響を最小化する工程設計を示せるかが勝負所です。
日本の産業・家計にどう効く?
- 産業の安定:自動車(特にEV・HEV)、産業ロボット、風力発電などのコア部品(高性能磁石)の供給が安定し、価格の乱高下リスクが下がる期待。
- 価格への波及:短期的に家電や車の価格が下がるとは限りませんが、中長期ではコスト上振れのリスクを抑える効果が見込めます。
- 雇用・投資:国内で分離・精製・磁石製造の再強化が進めば、地方の研究開発拠点・工場に投資・雇用が生まれます。実際、日米の技術・オフテイク連携のニュースが続いています。
「南鳥島は本当に“切り札”?」現実的な見方
切り札=すべてを一気に解決ではありません。現実的には——
- 短期(〜数年):豪州など陸上鉱山+精製の増強が主役。米豪・日米の枠組みで進む。
- 中期(2030年前後):南鳥島のパイロット→商業化の道筋が見えてくるか。技術・コスト・環境の“三つ巴”の最適化が鍵。
- 長期(2030年代):うまくいけば、南鳥島が重希土の“安定供給源”として世界を下支え。日米豪の“レアアース同盟”に深海からの第2エンジンを提供。
つまり、豪州=今を守る盾/南鳥島=未来を切り開く剣、この役割分担がもっとも筋が通ります。
よくある疑問にさくっと回答
Q1:南鳥島はどれくらい“持つ”の?
A:学術・報道では「世界需要を数百年レベルで賄える可能性」が示唆されています。ただし“資源量がある=供給できる”ではありません。技術・コスト・環境・法制度をクリアして「回せる量」にできて初めて意味があります。
Q2:商業化は本当にできる?
A:2026年の試験採掘→パイロットは重要な一歩。ここで安定運転とコストの壁をどれだけ崩せるかがカギ。国際的な環境ルールとも調和させる必要があります。
Q3:トランプ政権の動きは長続きする?
A:安全保障・産業政策として超党派性が強いテーマです。AUKUSの再確認や豪州との鉱物投資は、政権が変わっても方向性が大きく逆回転しにくい分野。少なくとも今は「前に進む」サインが相次いでいます。
日本が今やるべき実務アクション(現実的5点)
- 分離・精製・磁石までの国内一貫体制の再構築(人材・設備・電力を含む)。日米の技術・オフテイク連携を梃子に量産ラインを太くする。
- 豪州案件への参加・長期引取りで、短中期の安定供給を確保。
- 南鳥島の試験採掘・パイロットの加速:装置の冗長設計、詰まり対策、連続運転、選鉱・分離の現場最適化を急ぐ。
- 環境影響の実測データ×公開:国内外の理解を得るため、測定・監視・低減策を科学的に示す。
- 需要側(自動車・電機)との“生産計画の見える化”:価格だけでなく供給の安定価値を共有し、長期契約と投資回収の見通しを合わせる。
まとめ:南鳥島は“未来の切り札”、今は“同盟の実弾”を積む時期
- トランプ政権のもと、米豪+日米のレアアース協力は勢いを増しています。これは短中期の実弾供給(鉱山・精製・磁石)を太らせる政策です。
- 南鳥島は日本の長期カード。2026年の試験採掘→パイロットという階段を確実に上がり、2030年代の商業化を視野に入れる。
- 結論:日本は「豪州など陸上=今の安定」と「南鳥島=未来の自立」の二正面作戦で、“中国一極”のリスクを減らすことが最善手です。
出典メモ(研究・解説)
- 南鳥島のレアアース泥(Scientific Reports 2018、東大発表)—資源量と重希土の優位性。 Nature
- 2025年の研究アップデート(AGU誌ほか)—堆積年代や層の理解が前進。 AGU Publications
- 2026年試験採掘の見通し(EU-Japan Centre、Japan Forward)—タイムラインの整理。 EU-Japan
- 日米の技術・オフテイク連携の動き—実務面での前進。 Metal News