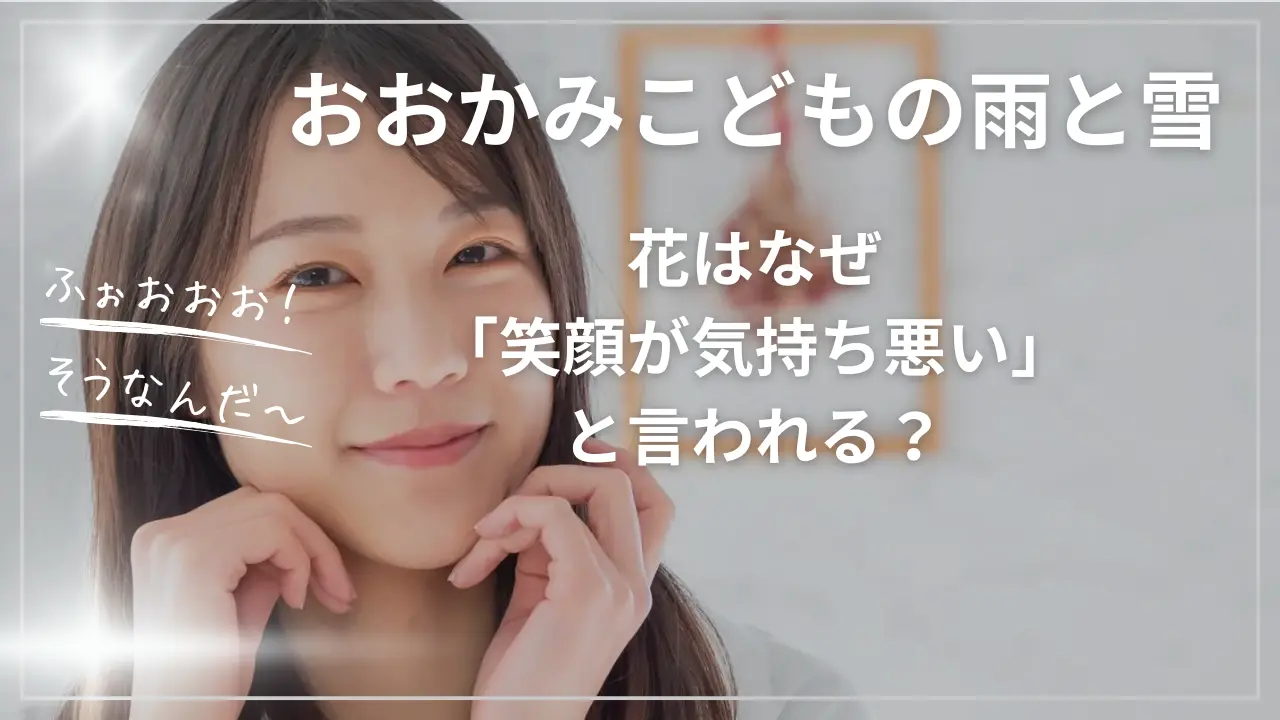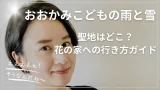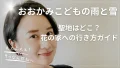細田守監督の『おおかみこどもの雨と雪』は、テレビ放送のたびに
「号泣した」「子どもを持ってから見ると刺さる」
という絶賛の声があがる一方で、
「花の笑顔がどうしても気持ち悪い」
「理想のお母さんを押しつけられているみたいでムリ」
という“モヤモヤ”の声も、毎回のようにSNSやレビュー欄に出てきます。
同じ映画なのに、どうしてここまで意見が割れるのでしょうか?
この記事では、「花の笑顔が気持ち悪い」と言われる理由と、
そこから見えてくる作品のメッセージを解説していきます。
まずおさらい|花ってどんなキャラクター?
物語の主人公・花は、国立大学に通う女子大生。
ある日、大学で出会った「おおかみおとこ」と恋に落ち、
やがて2人の子ども「雪」と「雨」を授かります。
しかし、幸せな時間は長く続かず、夫は突然の事故で亡くなってしまう。
しかも、子どもたちは「おおかみこども」。
人にもオオカミにもなる、不思議な存在です。
花は
- ひとりで二人の子どもを育てる
- 正体がバレないように人目を避ける
- 田舎に移り住んで自給自足に近い生活を始める
という、かなりハードな人生を選びます。
そんな過酷な状況の中でも、花はほとんどいつも笑顔。
ここが、多くの人が「好き」と感じるポイントでもあり、
同時に「気持ち悪い」と感じてしまう引っかかりにもなっています。
「笑顔が気持ち悪い」と言われる主な3つの理由
まずは、ネットやレビューでよく挙がる
「花の笑顔が気持ち悪い」とされる主な理由を、
大きく3つに分けて整理してみましょう。
① 理不尽な不幸でも常に笑っているから
花は作中で、かなり理不尽な不幸に次々と襲われます。
- 大学生なのに妊娠・出産
- 夫の急死
- お金も頼れる人もほとんどいない
- 子どもは「おおかみこども」で、育児は想像以上に大変
- 田舎ではよそ者扱いされ、うまくいかない農業にも苦労
普通なら心が折れてもおかしくない状況です。
ところが、そういう時にも花はほとんど笑顔を崩さない。
ある映画レビューでは、
「理不尽な不幸に襲われ続けているのに、
いつも笑っている花が“非人間的な自己犠牲の塊”に見えて気持ち悪い」
という感想も書かれています。
「つらいなら、つらそうにしてもいいじゃないか」
「弱音も吐かず、ただ頑張って笑うだけなんて、人間らしくない」
そう感じる人が少なくないわけです。
② 「理想の母親像」を押しつけられているように感じるから
もうひとつ大きいのが、“理想の母親”としての花の描かれ方です。
- 子どものために学業もキャリアも捨てる
- 自分の恋愛や再婚よりも、子どもの成長を最優先
- 眠る暇もないくらい働きながら、文句も言わずに笑っている
この姿が、
「母親はこうあるべき」「母ならここまでやるのが当然」
という“理想像”として提示されているように感じてしまう、という指摘があります。
実際に子育て中の母親からは、
- 「こんな人、本当にいたらすごいけど、現実離れしすぎていてついていけない」
- 「このレベルが理想だと思われたら、世の中のお母さんがつらくなるだけ」
といった声も上がっています。
つまり、
花の笑顔=“完璧なお母さん”の象徴
のように見えるがゆえに、
「こんな母親像を“素晴らしい”と押しつけられているみたいで気持ち悪い」
と感じる人がいる、というわけです。
③ 子どもへの向き合い方が「毒親っぽい」と感じる人もいるから
もう少し踏み込んだ批判として、
「花って、案外“毒親”っぽくない?」
という意見もあります。
たとえば、
- 子どもに自分の価値観を強く押しつけている
- とくに雨に対しては、亡くなった“おおかみおとこ”の面影を追いすぎている
- 雨には甘く、雪には厳しく見える場面がある
こうした点から、
「息子にはべったり、娘には厳しくあたる感じがイヤ」
「子どもの選択より“こうあってほしい”という親の願望が強すぎる」
と感じる人もいるのです。
この「重たい愛情」も、花の笑顔に
“ねばっとした圧”を感じさせてしまう原因のひとつと言えます。
花の笑顔には「呪い」がかかっている?
ここまで聞くと、
「やっぱり花って、完璧ぶったちょっと怖いお母さんなんじゃ…?」
と思うかもしれません。
でも、作品をよく見てみると、花の笑顔は決して
「生まれつきのポジティブさ」だけでできているわけではありません。
父親から受けた「つらい時こそ笑え」という呪い
作中で、花は自分の父親についてこんなエピソードを語ります。
- 父は「つらい時こそ笑っていなさい」と教えた
- 花はそれを真に受けて、「つらい時には笑う子」になった
ある映画コラムでは、この教えを
「花にかかった呪い」だと表現しています。
この視点で見直すと、
- 約束に遅れてきた恋人を前に、無理やり笑顔を作るシーン
- 育児ノイローゼになってもおかしくない状況で、それでも笑っている姿
は、
「強くて前向きな女性だから笑っている」のではなく、
「つらさを隠さないといけないと思い込んでいる」
とも読めます。
あるブロガーは、
花は、つらい現実を本当に“乗り越える”強い人というより、
“弱さを見せたらいけない”と信じて必死で笑っている人
と分析しています。
つまり、花の笑顔は「強さ」ではなく「弱さの裏返し」
だという解釈もできるのです。
「笑顔が怖い」のは、花の“闇”が透けて見えるから
待ち合わせ場所で恋人がなかなか来ないシーンを思い出してみましょう。
不安そうにうずくまっていた花は、彼がようやく現れた瞬間、
「ごめん、怒った?」と聞かれて、わざとらしいほどの大きな笑顔を見せます。
この笑顔に対して、
「なんかもう怖い」
「あそこが一番ゾッとした」
という感想もあります。
でもそれは、
- 「怒っていいのに、怒ることを自分に許していない」
- 「相手に嫌われないために、無理やり“いい子の笑顔”をしている」
という、花の心の闇が透けて見えるからこその“怖さ”でもあります。
そう考えると、
花の笑顔は「完璧な聖母の微笑み」ではなく、
「本当は弱いのに、弱さを見せられない若い女性の仮面」
と見ることもできるのです。
「花=理想の母親」か? それとも「間違いも多い一人の人間」か?
花の評価が割れる大きなポイントは、
彼女をどういう前提で見るかというところにあります。
「グレートマザー=偉大な母」として見るとしんどくなる
ある評論では、花のことを
「グレートマザー(偉大な母)」と呼んでいます。
- 奨学金で国立大学に通う優等生
- シングルマザーとして田舎で自活
- どんなに苦しくても笑顔を絶やさない
こう並べると、確かに“すごい人”に見えます。
しかし同じ論考の中で、
「こんな母親いるかよ、というツッコミも妥当だし、
“母親はこうあるべきだ”と押しつけられているようでムカつく」
という視聴者の反発も「よくわかる」と述べられています。
つまり、
- 「花=理想の母親像」を見せつけられている
↓ - 自分や身の回りの母親と比べて苦しくなる
↓ - 結果として「花、気持ち悪い」「嫌い」という感情になる
という流れが発生しやすいのです。
「間違いだらけの若い母」として見ると印象が変わる
一方で、
「花は色々“間違っている”子だから、モヤっとする。
でも、それでいいんだと小説版を読んで気づいた」
という感想もあります。
この視点では、
- 学生で妊娠・出産する
- ほとんど準備もなく子どもを産む
- 行政や医療機関にもっと頼れたはずなのに、頼らない
- 田舎での生活も、ほぼ勢いで決めてしまう
といった“無計画さ”や“未熟さ”も、
一人の若い女性としてのリアルな「間違い」として受け止めます。
すると、花の笑顔も
「立派なお母さんの笑顔」ではなく、
「何度も失敗しながら、それでも笑うしかなかった若い女の子の笑顔」
として見えてくるのです。
この見方に立つと、
- 花は完璧な母ではない
- だからこそ、雪や雨も彼女から“自立”していく必要があった
という、親子の成長物語として読み取ることができます。
花への「違和感」も含めて、この作品の“リアル”なのかもしれない
ここまで見てきたように、花が「気持ち悪い」と言われる背景には、
- 理不尽な不幸に対しても笑い続ける“異常さ”
- 母親像を美化しすぎているように見える演出
- 子どもへの愛情が重すぎて“毒親”っぽく見える面
といった要素があります。
しかし同時に、
- 父親の教えによる「つらい時こそ笑え」という呪い
- 弱さを隠すために笑顔の仮面をかぶる花の心情
- 間違いの多い若い母としての等身大の姿
といった“裏側”を読み取ることもできます。
観客が感じるモヤモヤ=「こういう母親像はイヤだ」という叫び
花に対して、
「こんなお母さん像、押しつけないでほしい」
「母親だって弱音を吐いていいし、笑えない日があってもいい」
という怒りや違和感を覚えるのは、
ある意味、とても健全な反応です。
それは、
- 「母親はいつも笑顔で、強くて、自己犠牲的であるべき」
- 「子どもを最優先して、自分の幸せは後回し」
という、社会に根強くある価値観そのものへの
NO(ノー)のサインでもあるからです。
それでも花の物語が胸に刺さるのはなぜか
一方で、多くの人がこの作品を「大好き」と言い、
号泣してしまうのも事実です。
それは、
- 花がどんなに不器用でも、必死に子どもたちを愛そうとしている
- 雨と雪が、それぞれ違う道を選び、自分の足で歩き出す
- 花自身も、最後には「子どもを手放す」という、
親として一番つらいけれど大切な選択をしている
という、親子の“手放し”と“旅立ち”の物語として
強く心に響くからでしょう。
これから『おおかみこどもの雨と雪』を見る人へのガイド
最後に、「これからもう一度見てみようかな」という人に向けて、
ちょっとした“見方のヒント”を置いておきます。
見方① 花を「完璧なお母さん」として見ない
最初から
「この人は理想の母親なんだ」
と思いながら見ると、どうしても息苦しくなります。
代わりに、
- 20歳そこそこの、親もいない若い女の子が
- わけのわからない状況の中、がむしゃらに生きている
「すごく不器用で、でも必死な一人の人間」として見てみてください。
すると、笑顔の裏にある不安や弱さが、
少し見えやすくなります。
見方② 「花が笑うシーン=つらさを隠しているサイン」として見る
花がどんなタイミングで笑うかに注目してみるのもおすすめです。
- 本当は怒っていい場面で笑う
- 泣きたいのに笑う
- 子どもに心配をかけないために笑う
こうした場面は、
「花が一番つらい瞬間」でもあります。
「うわ、また笑ってるよ」とイラッとしたら、
そのたびに
「あ、今この人、相当しんどいんだな」
と置き換えて見てみると、
花への見え方が少し柔らかくなるはずです。
見方③ 雨と雪の“視点”に立ってみる
物語は、基本的に雪の回想という形で語られています。
- 雪にとって、花はどんな母に見えたのか
- 雨にとって、花はどんな存在だったのか
を想像しながら見ると、
「いい母・悪い母」という単純なジャッジではなく、
「子どもにとって親は、ありがたい存在でもあり、重たい存在でもある」
という、よりリアルな親子関係が見えてきます。
まとめ|「気持ち悪い」と感じていい。そこからが、この映画の本番
『おおかみこどもの雨と雪』が賛否両論になるのは、
- 花があまりに“がんばりすぎる母”として描かれていること
- その笑顔が、誰かにとっての「理想の母」像に見えてしまうこと
- そして、それが現実の母親たちを追い詰めるイメージと重なること
が大きな理由です。
でも一方で、
- 花の笑顔は「つらいときほど笑え」という呪いの結果でもあり
- 未熟で無計画で、間違いだらけの若い女性なりの“あがき”でもあり
- 子どもたちは、そんな母から自立して、自分の道を選んでいく
という、
「完璧じゃない親」と「それでも育っていく子ども」の物語として読むこともできます。
だからこそ、
「花の笑顔がどうしても好きになれない」
「見ていてモヤモヤする」
という感情も、実はこの作品が投げかけている問いに
きちんと向き合っている証拠なのかもしれません。
「どうして自分は花を気持ち悪いと感じたんだろう?」
その理由を自分なりに言葉にしていくこと――
そこからが、この映画の本当の“観賞体験”の始まりだと言えるでしょう。