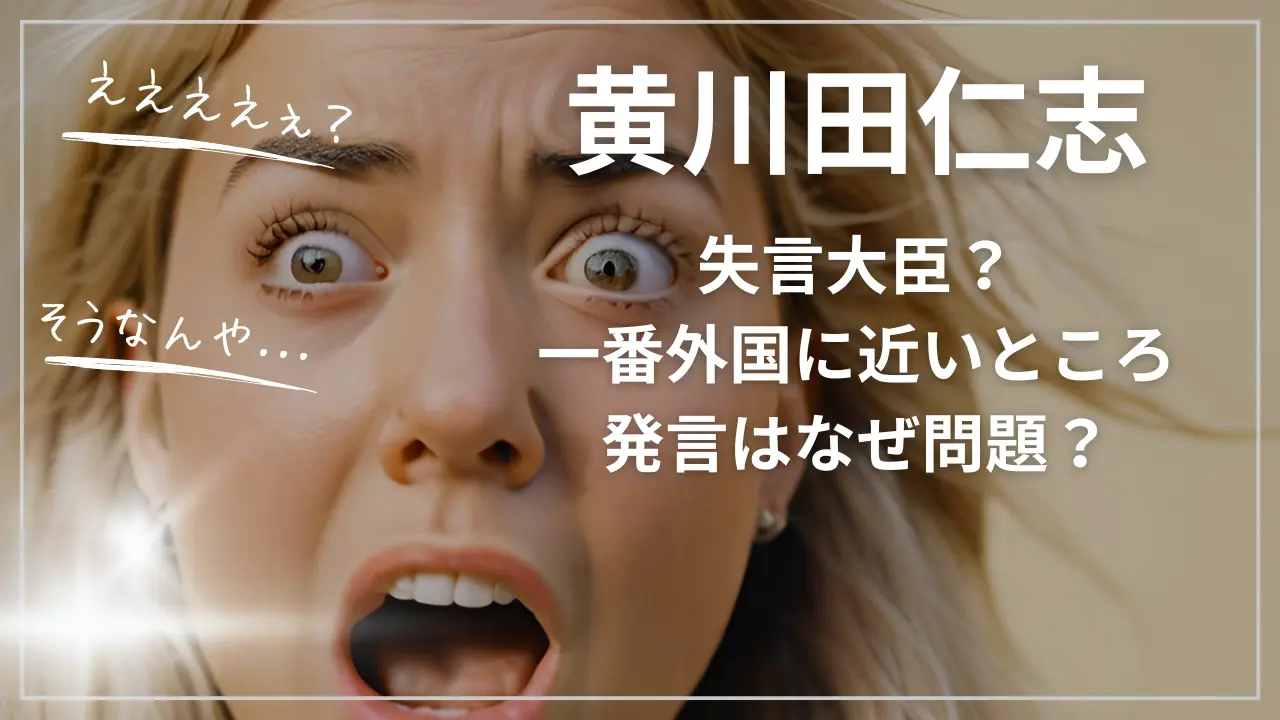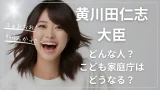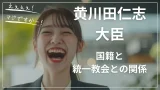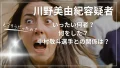2025年11月、「黄川田仁志(きかわだ ひとし)沖縄北方担当大臣」のある一言が、大きな波紋を広げています。
「(納沙布岬は)一番やっぱり外国に近いところですから。それを目で感じるのが大切だと思います」
北海道・根室市の納沙布岬(のさっぷみさき)から北方領土を眺めながら、こう話した映像がニュースで流れました。
一見すると、「日本と外国が近い場所だよね」という、よくありそうな感想にも聞こえますよね。
しかし、
この一言は、
- 北方領土は「日本の領土」として返還を求めている最前線の場所
- 元島民や地元の人たちにとっては、いまも“故郷”そのもの
という、とても重い場所で出た言葉でした。
そのため、
- 「外国扱いしたのでは?」
- 「政府の立場とズレるのでは?」
- 「元島民の気持ちを傷つけるのでは?」
と批判が集まり、「失言大臣?」という厳しい声も出ているのです。
この記事では、
「なぜ、この一言がここまで問題になっているのか?」
を解説していきます。
黄川田仁志ってどんな人?
まず、発言した本人がどんな立場の人なのかを、簡単に整理しておきましょう。
- 自民党の衆議院議員
- 埼玉3区選出で当選5回
- 高市早苗首相を支える側近の一人とされる
- 高市内閣で「沖縄・北方担当大臣」「こども政策・少子化・若者などの担当大臣」を兼務するポストに就任
つまり黄川田氏は、
「沖縄」と「北方領土」という、
日本の中でも特に“センシティブな地域”を担当する大臣
という、とても重要な役割を任されている人です。
だからこそ、一つひとつの言葉の重みが、より大きく問われるポジションだと言えます。
問題の「一番外国に近いところ」発言とは
いつ・どこで・どんな場面で出た言葉?
問題になっている発言は、以下のような状況で出ました。
- 日付:2025年11月8日
- 場所:北海道・根室市 納沙布岬
- 状況:納沙布岬から、すぐ目の前に見える北方領土・歯舞群島を視察
- 質問:記者から「感想」を聞かれて答えた言葉
そのとき黄川田大臣は、こう答えました(要約)。
「ここは一番外国に近いところだから、実際に目で感じるのが大事だ」
この言葉がニュースで繰り返し流れ、
- 「北方領土を“外国”扱いしたのでは?」
- 「政府は『日本固有の領土』と言ってきたのに…」
と、問題視されるようになりました。
発言のあと、すぐに広がった違和感
発言をその場で聞いていた北海道の鈴木直道知事は、
「聞いた瞬間に『これはどういう意味だ?』と思った」
と振り返っています。
その後、知事は黄川田大臣に対し、
- 北海道として看過できない(見過ごせない)
- 元島民が傷つくような発言は慎んでほしい
と伝え、現場で謝罪を求めたことも明らかになりました。
さらに、
- 木原官房長官が「政府の立場に誤解を招きかねない」と注意
- 高市首相も「電話で注意した」と国会で答弁
するなど、政府の中でも問題視される事態となっています。
なぜこの一言が問題視されたのか?
ここからが本題です。
なぜ、「一番外国に近いところ」という一見シンプルな言葉が、ここまで批判されているのでしょうか。
ポイントは、大きく4つあります。
① 北方領土は「日本固有の領土」という政府の立場
日本政府は、北方領土(択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島)について、
「歴史的にも国際法上も、日本固有の領土である」
という立場を、ずっと公式に表明してきました。
- ロシアが実効支配しているけれど、
- 日本としては「不法占拠されている」という認識
という、非常にデリケートな問題です。
そのため、日本政府の要人が北方領土に触れるときは、
- 「わが国固有の領土」
- 「返還に向けて粘り強く交渉」
など、言葉の一つひとつを慎重に選んで発信してきました。
そんな中で、
「一番外国に近いところ」
という言い回しは、
まるで北方領土そのものを“外国”として認めたように聞こえてしまう――
ここが最初の大きな問題点です。
② 「外国に近い」という表現がもつ重み
もちろん、地理的に見ると、
- 北海道の東の端から
- すぐ目の前に“ロシアが実効支配している島”が見える
という意味で、「外国に近い場所だ」という表現自体は、日常会話としては成立します。
しかし、問題は誰がどの立場で言ったかです。
- 一般の観光客が「外国めっちゃ近いね〜」と言うのと
- 「北方担当大臣」という立場の人が言うのとでは
意味の重さがまったく違います。
北方領土を担当する大臣が、
「ここは外国に一番近い場所」
と言ってしまうと、
- 「日本政府も、あの島々を事実上“外国扱い”しているのでは?」
- 「日本側の主張があいまいになってしまうのでは?」
と受け取られかねません。
木原官房長官が、
「北方領土はわが国固有の領土であり、ご指摘の発言は政府の立場に誤解を招きかねない」
とコメントしたのは、まさにこの点を問題視したからです。
③ 元島民や地元の人の気持ちへの配慮
もう一つ、とても大きなポイントがあります。
それは、
北方領土を故郷として育った“元島民”の人たちの存在
です。
- 戦前・戦中は、あの島々に日本人が普通に暮らしていた
- 戦後、ソ連軍の進攻で、島を追われる形で本土に移された
- 高齢になった今も、「故郷へ帰りたい」という思いを抱き続けている
そんな方々が、根室市などに多く暮らしています。
そうした人たちにとって、
「一番外国に近いところ」
という言い方は、
- 「自分たちの故郷を“外国”と言われたようでショックだ」
- 「日本の大臣にまで、そういう言い方をされるのか」
と、心を痛める表現になりかねません。
北海道の鈴木知事は、この点を考えて、
- 「元島民が傷つく発言は慎んでいただきたい」
- 「北海道として看過できない」
と、黄川田大臣に伝えたとされています。
領土問題は、単なる地図の話ではなく“人の生活と感情の問題”でもある――
そのことを改めて浮き彫りにした発言だったと言えます。
④ ロシアとの関係・外交的な意味合い
さらに、国際政治という視点でも、この発言は無視できません。
- ロシアは「北方領土は自国の正当な領土」と主張
- 日本は「日本固有の領土を不法占拠されている」と主張
という、主張が真っ向からぶつかっている状態です。
こうした中で、日本側の大臣が
「外国に一番近いところ」
と言ってしまうと、
- ロシア側から「日本の大臣も“外国”と言っている」と利用される
- 日本側がこれまで積み上げてきた主張が、弱く見えてしまう
という外交上のリスクも指摘されています。
もちろん、黄川田大臣本人に“ロシアの肩を持つつもり”があったとは考えにくいです。
しかし、外交の世界では、
「言葉そのものが、相手にどう解釈されるか」
が非常に重要であり、“うっかり一言”が相手国に利用されることもあるのです。
政府・北海道知事・大臣本人の対応
では、この発言を受けて、関係者はどのように動いたのでしょうか。
官房長官・首相からの注意
- 木原官房長官
- 「北方領土はわが国固有の領土」
- 「発言は政府の立場に誤解を招きかねない」として注意
- 高市早苗首相
- 国会で「誤解を招きかねない発言だったと感じた」と答弁
- 黄川田大臣に電話で注意したことを明らかにした
内閣のトップと官房長官が揃って注意するというのは、
かなり重い対応と言えます。
北海道知事「看過できない」&謝罪要求
北海道の鈴木知事は、記者会見で、
- 「その場で大臣に真意を確認した」
- 「北海道として看過できないと伝えた」
- 「元島民の気持ちを考えれば、謝罪が必要だと考えた」
などと語りました。
報道によると、現場でも黄川田大臣に謝罪を求めたとされています。
大臣本人の釈明と謝罪
黄川田大臣本人は、その後の取材や国会答弁などで、
- 「根室は海外へのゲートウェイという市長の説明を受け、その話の延長線上で答えた」
- 「発言が誤解を与えたとするなら、今後は注意しながら責任ある言葉を発したい」
と釈明・謝罪を行いました。
つまり本人としては、
「“地理的に外国に近い”という意味で言ったつもりで、北方領土を外国だと認めたわけではない」
というスタンスを示しているわけです。
「失言大臣?」と言われる背景
今回の「一番外国に近いところ」発言には、もう一つ背景があります。
それは、
黄川田氏が、就任前からすでに“言葉の問題”で批判を受けていた
という点です。
過去の「顔が濃い方」発言とは?
2025年9月、高市早苗氏の自民党総裁選 出馬会見で、司会を務めていた黄川田氏は、
挙手した記者を指名する際に、
「一番奥の机の顔が濃い方」
「逆に顔が白い、濃くない方」
などと発言しました。
このとき高市氏はすぐに、
「何てこと言うんですか。すみません」
と、その場で謝罪。
黄川田氏も後日、
「不適切な表現だった」として謝罪
しましたが、「ルッキズム(見た目差別)」ではないかと批判が広がりました。
こうした経緯があったため、
- 「また黄川田氏がやらかした」
- 「こどもや多様性を担当する大臣としてどうなのか」
という形で、“失言大臣”というレッテルを貼るような声も出やすくなっているのです。
こうした失言から私たちが学べること
ここまで見てくると、
「政治家って、言葉の一字一句まで大変だな……」
と感じるかもしれません。
でも、この問題は単に「一人の政治家のミス」で終わらせてしまうには、もったいないテーマでもあります。
ここから、私たち一般の立場でも学べるポイントを2つ挙げてみます。
① 言葉の「癖」が炎上を生む
今回も、過去の「顔が濃い」発言も、
どちらも
- “その場を軽くしよう”
- “ちょっと面白く言おう”
という本人の「話し方のクセ」から出た言葉に見えます。
しかし、そのクセは、
- ルッキズム(見た目で人をいじる)
- 領土問題を軽く見ているように聞こえる
と受け取られ、炎上の原因になっています。
これは、SNS時代の私たちにも当てはまりますよね。
- 「ちょっとウケるかな」と思って書いた一言
- 「その場のノリで言っただけ」の一言
が、コンテキストから切り取られて拡散されるのは、政治家に限った話ではありません。
「自分のクセが、誰かを傷つけたり、誤解を生んだりしていないか?」
と、ときどき立ち止まって見直すことは、誰にとっても大事な習慣だと言えそうです。
② 政治家の言葉は、なぜここまで重いのか
もう一つは、
「権力や責任を持つ人の言葉は、同じ一言でも“重さ”が違う」
ということです。
- 一般人の「外国に近いね」はただの感想
- 北方担当大臣の「外国に近いところ」は、外交・領土問題と直結
同じ日本語でも、立場によって意味が変わってしまうのです。
これは、会社や組織の中でも同じです。
- 上司の何気ない一言が、部下には“正式な方針”に聞こえる
- 経営者のちょっとした冗談が、社員を深く傷つける
といったこともあります。
今回の件は、
「立場が上がるほど、言葉の責任は重くなる」
という、シンプルだけれど忘れがちな事実を、改めて見せてくれた出来事だと言えるでしょう。
まとめ
今回の「一番外国に近いところ」発言は、
- 北方領土を「日本固有の領土」としてきた政府方針とのズレ
- 元島民や地元の人の気持ちへの配慮不足
- ロシアに“利用される”恐れのある外交上のリスク
といった点から、「これはまずい」と受け止められたと言えます。
黄川田大臣は「誤解を与えたなら今後注意したい」と釈明し、
首相や官房長官からも注意を受けましたが、
「元島民の心の傷は簡単には癒えない」という声もあります。
一方で、
- 人は誰でも言い間違いをする
- その後どう向き合い、学び、変わるかが大事
という見方もできます。
私たちにできるのは、
- 感情的に「失言だ!」と叩くだけでなく
- 何が問題だったのかを冷静に理解し
- 自分自身の言葉の使い方も、少し振り返ってみる
ことかもしれません。