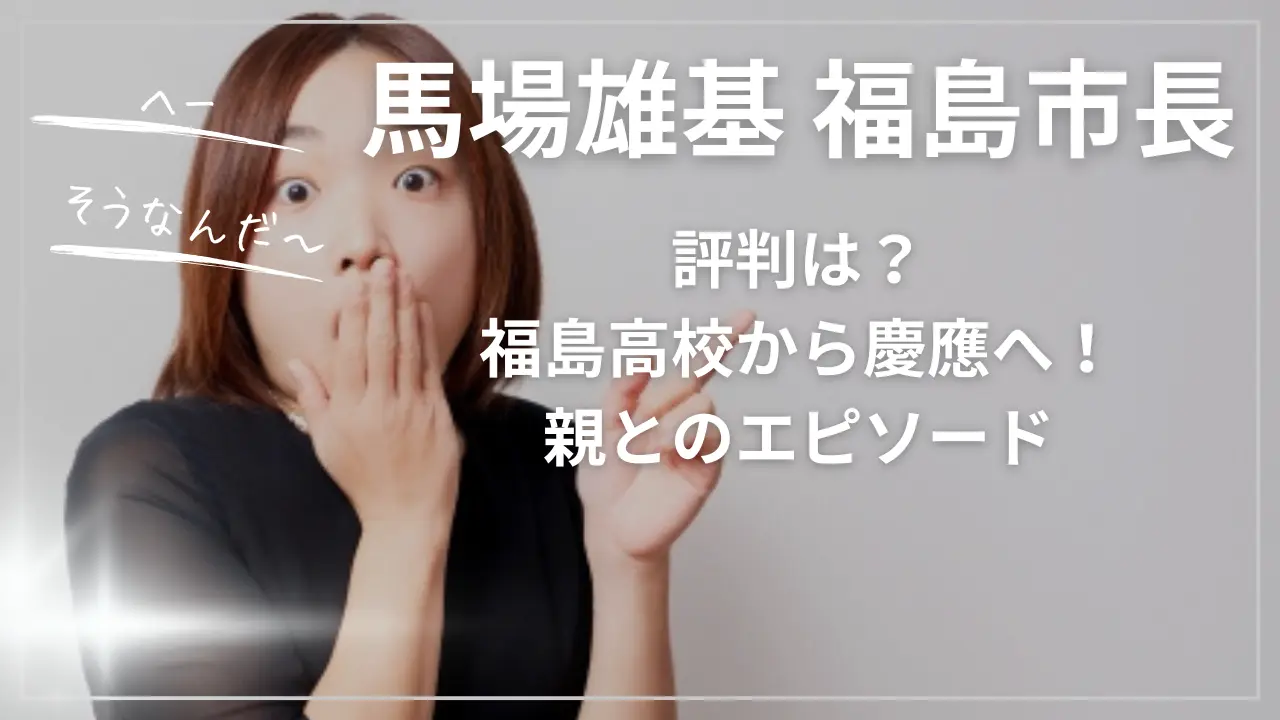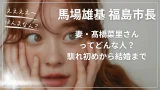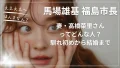馬場雄基さんの名前を、ニュースやSNSで見かけることが増えてきましたよね。
「若い市長」「元・最年少国会議員」というイメージはあっても、
- どんな評判の政治家なのか
- 福島高校から慶應に進んだ学生時代はどんな様子だったのか
- 「親とのエピソード」から見える、人としての原点はどこにあるのか
までは、なかなか知られていません。
この記事ではていねいに整理していきます。
馬場雄基さんはどんな人?基本プロフィールと最近の動き
まずはざっくりプロフィールから見てみましょう。
- 1992年10月15日生まれ(33歳)
- 福島県郡山市生まれ、4歳から福島市で育つ
- 福島大学附属小・中 → 福島県立福島高校 → 慶應義塾大学法学部政治学科
- 三井住友信託銀行の銀行員を経て、松下政経塾に入塾
- 福島市の交流施設「アオウゼ」事業統括コーディネーターなど、地域の仕事に携わる
- 2021年の衆院選で初当選。平成生まれとして初の国会議員で、当時唯一の20代衆議院議員になる
そして、2025年11月16日に行われた福島市長選挙で初当選。33歳での当選は「福島市では合併後最年少の市長」としてニュースになりました。
つまり今の馬場さんは、
「元・最年少国会議員」から「福島市長」へバトンを渡した、世代的にもかなり若いリーダー
という立ち位置にいます。
福島高校から慶應へ:勉強だけじゃない学生時代
福島大学附属小・中から福島高校へ
馬場さんの学歴を並べると、いわゆる「進学校コース」です。
- 福島大学附属小学校(1999〜2005年)
- 福島大学附属中学校(2005〜2008年)
- 福島県立福島高校(2008〜2011年)
福島高校は、福島県内でもトップクラスの進学校として知られています。そこから慶應義塾大学法学部に進んでいるので、学力的にもかなり努力してきたことが分かりますね。
生徒会長として「ルール」を変えた高校時代
高校時代について本人のサイトを見ると、単に「勉強ができる生徒」ではなく、かなり「動くタイプ」の高校生だったことが分かります。
- 水泳部に所属
- 文化祭でウォーターボーイズと一緒にダンス披露
- 高1で生徒会副会長に当選
- 高2・高3で生徒会長。しかも112年の歴史の中で最多得票率を獲得
- 「ABS(Active But Small)」というコンセプトで、生徒会を「よく動く、小回りのきく組織」にしようと提案
さらにおもしろいのが「携帯電話ルール」を変えたエピソードです。
高校生主体で、授業中・休み時間の携帯電話マナーをルール化し、先生や教育委員会との話し合いを重ねた結果、
福島県の高校で初めて「携帯電話の学内持ち込みOK」を実現した
と紹介されています。
「ルールは上から降ってくるもの」ではなく、
- 現場にいる高校生自身が
- 課題を整理して
- 関係者とかけ合い
- 具体的なルールに落とし込んでいく
という経験を、高校時代からしていたわけです。
「政治家っぽいこと」をかなり早い段階からやっていた、と言えるかもしれません。
震災と大学進学 ― 福島を離れる迷い
2011年3月11日。東日本大震災が起きたとき、馬場さんは福島市のコミュニティ施設「アオウゼ」で勉強している最中に被災しました。
- 物理的な被害も大きかった
- それ以上に、原発事故のニュースと「人体に直ちに影響はない」という言葉に不安を感じた
- 周りの人が避難していく中、自分はどうするべきか分からなかった
それでも進学のために、東北道の復旧と同時に東京に出る決断をします。
そのとき、高校の後輩から届いたメッセージは、
「逃げるのですね」
という、かなり重い一言だったそうです。
「福島を離れて東京に行く自分はどう見られるんだろう…」
そんな迷いを抱えたまま、慶應義塾大学へ進学したことが語られています。
慶應時代:インターンを渡り歩きながら「政治」に近づく
2011年、慶應義塾大学法学部政治学科に入学した馬場さん。
震災のショックもあり、最初はなかなかエンジンがかからなかったそうですが、ある日、大学の掲示板で「経済産業省インターン生募集」というチラシを見て、思い切って応募します。
そこから一気に動きが変わっていきます。
- 経済産業省でのインターン(1年生で挑戦)
- 国会議員秘書のインターンで、議員の考え方を学ぶ
- 働き方改革の会社でインターン(株式会社ワーク・ライフ・バランス)
こうした経験を通して、
「とにかく社会を見たい」「視野を広げたい」
という気持ちが強くなっていったと書かれています。
大学のゼミでは行政学を学び、東日本大震災の政策や、郵政民営化なども研究していたとのこと。
「福島高校から慶應へ」という学歴だけ見ると、“エリート感”がありますが、中身はかなり地に足のついた「現場を見に行くタイプ」の学生だったようです。
「親にはかなり心配されたな」― 立候補のときの本音
タイトルにもある「親とのエピソード」は、衆院選に立候補したときのインタビューに出てきます。
2021年の衆議院選挙後、同級生の記者が行ったインタビュー記事の中で、こう語っています。
「20代で立候補したとき、周りは『えっ』という反応が多かった」
「もともと政治家は選択肢の一つだったけど、『早い』と言われた」
「親にはかなり心配されたな。政治の世界に不安があったんだと思う」
ここから分かるのは、
- 親御さんにとっても、政治家への挑戦は「応援一色」ではなく
- 「ほんとにやって大丈夫なの?」という不安も大きかった
ということです。
それでも実際には息子の挑戦を止めることなく、見守ったわけですよね。
「心配はしているけれど、チャレンジを止めはしない」――これは、多くの親子にも共通するリアルな距離感ではないでしょうか。
さらに同じインタビューの中で、選挙中の厳しい声についても正直に話しています。
「『何もやっていない青二才が!』と批判された」
「社会常識や経験のなさを、選挙で自分でも痛感した」
こうした言葉を、本人が隠さず話しているのも印象的です。
親に心配されつつ、それでも「自分で決めた道だから」と腹をくくって進んだ、その背中が見えてきます。
家族とのエピソードから見える「原点」
では、そもそもどんな家庭で育ったのでしょうか。
父は県警本部の事務官、母は保育士
プロフィールによると、
- 父:福島県警察本部の事務官
- 母:保育士
- 姉との2人きょうだい
という家庭で育ったとされています。
「警察」と「保育」という、
安全・ルール・人の命や生活を守る仕事に関わる両親のもとで育った、というのはなかなか象徴的です。
- 父の仕事からは「ルール」「公正さ」「安全を守る責任」
- 母の仕事からは「子どもへのまなざし」「支えるケアの心」
こうした価値観に、自然と触れながら育ってきたと考えられます。
引っ越しと「ベビースイミング」
幼少期のエピソードとして、自身のサイトにこんなことも書かれています。
- 1歳半から母親と一緒に「ベビースイミング」に通い、水泳を始める
- とても負けず嫌いで、何でも一番にならないと気がすまなかった
- 3歳のとき、親の転勤で福島市に引っ越す
「親の転勤で福島市に移り住み、そこでその後の人生の基盤ができていく」という流れを見ると、
福島市長になった今、「原点に戻ってきた」という感じもありますよね。
小学校5年生からは学校の授業でYOSAKOIを踊り、UFOの里YOSAKOI祭りで元気賞を取るなど、地域のイベントにも積極的に参加していたそうです。
「小学生にも分かるように話す」行動指針
彼の公式サイトには、「行動指針」としてこんな一文もあります。
「小学生が理解できるように話さねば信用は得られない」
これは、おそらく保育士のお母さんや、地域の子どもの場に関わる経験の影響もありそうです。
- 専門用語を並べるより
- 子どもにも伝わる言葉で話すことが大事
という考え方は、政治家としてというより「一人の人間としてのクセ」に近いものかもしれません。
銀行員から松下政経塾、そして国会へ
一度は民間企業へ ― 三井住友信託銀行時代
慶應卒業後は、いきなり政治家になるわけではなく、まず三井住友信託銀行に就職しています。
- 神戸支店の個人営業を担当
- そこで出会った「福島から避難してきた男の子」とのエピソードが転機になる
避難して学校になじめなくなっていた福島出身の男の子が、馬場さんと出会って久しぶりに笑ってくれた――
そんな出来事がきっかけで、
「福島はいつか勝手に復興するだろう」とどこかで思っていた自分を恥じた
と振り返っています。
そこから、
- 「福島に戻る」
- 「復興に直接関わる」
と決め、松下政経塾へ進む道を選んでいきます。
松下政経塾・地域活動での経験
松下政経塾では、
- 早朝の掃除や茶道・書道などの研修
- 自衛隊やパナソニック販売店での現場研修
- 国内外の自治体を回り、まちづくりを学ぶ
など、多様なプログラムに参加しています。
その後、
- 福島市のコミュニティ施設「アオウゼ」の事業統括コーディネーター
- ふくしま地域活動団体サポートセンターの連携・人材育成コーディネーター
- SDGsアドバイザーとして子ども食堂ネットワークの支援
など、「地域の場づくり」「住民の活動を支える仕事」をしてきました。
こうした経歴を知ると、
「最初から国会議員になるための“政治家キャリア”を歩いた」というより、
「福島の現場を見て、そこから政治に近づいていった」
という流れが見えてきます。
評判は?実績や「質問力」への評価
では、肝心の「評判」はどうなのでしょうか。
「質問がうまい」「説明が分かりやすい」という声
ネット上のまとめ記事では、
- 「質疑能力には定評がある」
- 「質問が具体的で分かりやすい」
といった評価が紹介されています。
また、本人の「行動指針」にも、
「小学生が理解できるように話さねば信用は得られない」
という一文があるように、難しい話をかみくだいて説明するスタイルを大事にしていることが分かります。
実際、国会での初質問や予算委員会での質疑は、YouTubeなどにも公開されており、「聞きやすい」「言い回しが丁寧」といったコメントも見られます。
若さゆえの批判も、本人は自覚している
一方で、先ほどのインタビューで出てきたように、
- 「青二才」「何もやっていない」
- 「若さだけで売っているんじゃないか」
といった厳しい声も、選挙中には浴びたと本人が語っています。
これに対して彼は、
- 「未熟なのは当然だと割り切った」
- 「だからこそ、現場を回り対話を積み重ねて実力をつけたい」
と話しています。
つまり、
「若さを武器にする」というより
「若さゆえの未熟さは認めた上で、行動で信頼を積み上げたい」
というスタンスだと読めます。
福島市長選で見えた「刷新感」と地元での評価
2025年の福島市長選挙では、3期目を目指す現職の木幡浩市長らを破り、馬場さんが初当選しました。
選挙報道を見ていると、いくつかポイントがあります。
- 33歳という若さでの当選は、福島市では合併後初の30代市長
- JR福島駅東口の再開発計画の一部見直しなど、「まちづくりの土台を考え直そう」と訴えた
- 「刷新感」を打ち出したことが、幅広い層の支持につながったと報じられている
開票状況では、
- 馬場雄基氏:58,453票
- 木幡浩氏:43,818票
- 高橋翔氏:2,745票
と、現職にかなりの差をつけての勝利となりました。
この結果だけを見ると、
- 「現状維持」より「変化」
- ベテランより「新しい世代」
に期待する市民が、一定数以上いたと考えられます。
もちろん、評価はこれからの4年間の市政運営で大きく変わっていくでしょう。
ただ、スタートラインとしては「期待を込めた選択」だったと言ってよさそうです。
まとめ
ここまで、
をざっくりたどってきました。
情報を整理すると、馬場雄基さんの「原点」は、次の3つに集約されていきます。
- 家族と福島で育った経験
- 警察・保育という「人を守る」仕事の両親
- 転勤で福島市に移り住み、地域のイベントや学校生活の中心で動いてきたこと
- 高校〜大学で培った「ルールを変える側」の感覚
- 生徒会長として携帯電話ルールを変えた経験
- 行政や政策を自分の目で見て学ぼうとしたインターンの数々
- 震災と「福島に向き合う」覚悟
- 震災で福島を離れる迷い
- 神戸で出会った福島出身の男の子の笑顔
- 「福島はいつか勝手に復興する」と思っていた自分を恥じ、戻ることを決めたこと
評判については、
- 「質問力がある」「説明が分かりやすい」という好意的な評価
- 一方で「経験不足」「若すぎる」といった厳しい声
- それらを本人自身がきちんと自覚している様子
が見えてきました。
福島市長としての4年間が、どんな評価につながるのかは、これからの行動次第です。
ただ、「親に心配されながらも挑戦を選んだ20代」から、「福島市の舵取りを任された30代」へ――
この流れの裏側には、
家族や故郷との関係の中で、「逃げた」と見られるかもしれない自分と向き合い続けてきた時間
があるように感じられます。
これからの市政で、
- どこまで「市民目線」を貫けるのか
- どれだけ「分かりやすい説明」と「実行力」を見せられるのか
そのあたりを意識してニュースや発信を追いかけていくと、「評判」の中身も立体的に見えてくるでしょう。