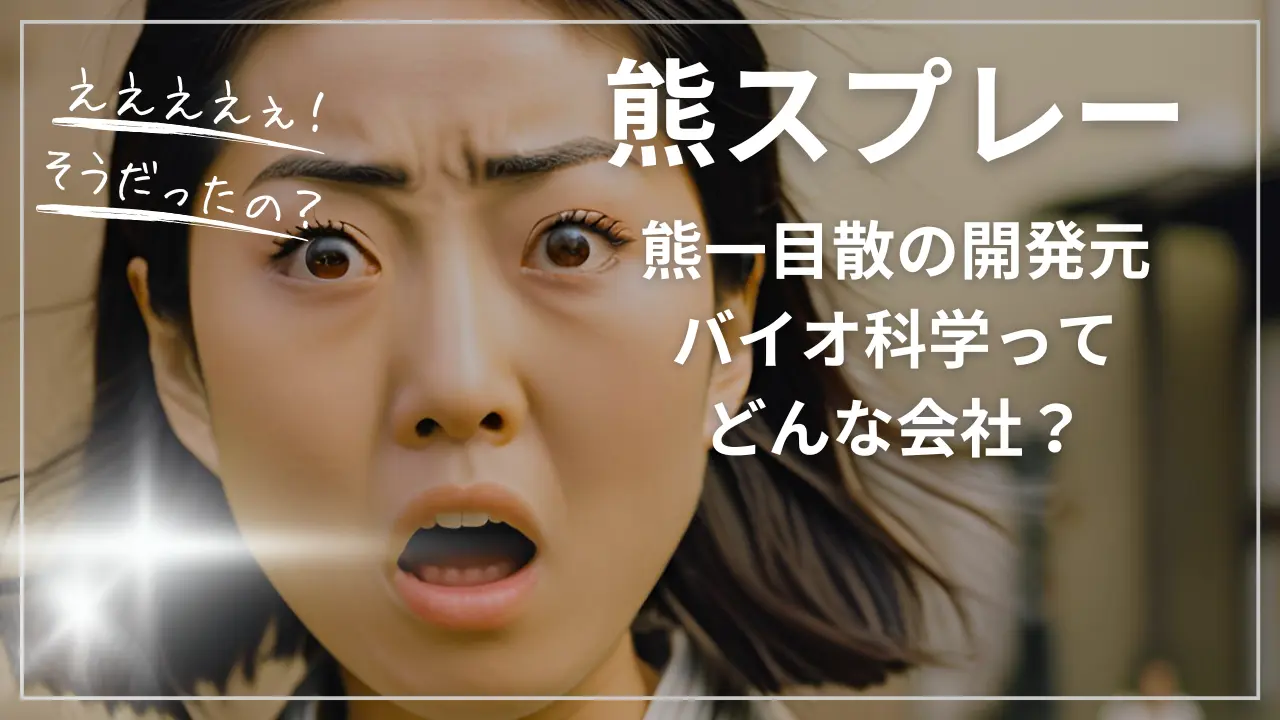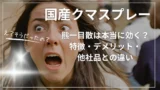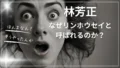「熊一目散」を調べていると、必ず出てくる名前が
開発元・バイオ科学株式会社 ですよね。
- どんな会社が作っている熊スプレーなのか
- 信頼していい会社なのか
- 熊用の製品なんて前から作っていたのか
このあたりが分かると、「熊一目散」を買うかどうか判断しやすくなると思います。
この記事では、熊スプレー「熊一目散」の開発元・バイオ科学がどんな会社なのかを紹介します。
まず結論:バイオ科学は「動物用医薬品」の専門メーカー
バイオ科学株式会社は、徳島県阿南市に本社と工場を置く「動物用医薬品のメーカー」です。
公式の会社概要によると、
- 社名:バイオ科学株式会社
- 設立:1983年7月1日
- 本社所在地:徳島県阿南市那賀川町工地246-1
- 資本金:1億円
- 売上高:55億円(2024年12月期)
- 従業員数:102名(グループ合計約140名、2025年時点)
となっていて、地方に本社を置く中堅クラスのメーカーです。
さらに事業内容を見ると、
- 牛や豚、鶏などの家畜向けの薬やワクチン
- 養殖魚向けのワクチンやサプリメント
- 飼料(エサ)に混ぜる栄養剤・機能性成分
- ビタミンやミネラルなど原料の輸入販売
といった、畜産・水産業の“裏方”を支える製品を長年つくってきた会社だと分かります。
キャッチコピーは公式サイトにもあるように
「生命を科学する。」
というもので、生き物の健康と成長を科学の力で支えることを会社のフィロソフィー(考え方)の中心に置いています。
そもそも「熊一目散」ってどんな熊スプレー?
会社を見る前に、簡単に製品の特徴もおさらいしておきます。
「熊一目散」は、
- 日本初の“純国産”熊撃退スプレー
- 動物医薬品メーカーのバイオ科学が、
酪農学園大学・佐藤喜和教授(熊研究の第一人者)と共同開発した製品 - ヒグマなどに対して忌避効果があるとされる
カプサイシンを2%以上配合 - 最大噴射距離 約10m・連続噴射 約10秒
- 海外製品でよく使われる温室効果ガス「HFCガス」を使わず、
環境負荷の少ないLPガスを採用
というスペックです。
名前だけ見ると「新しいアウトドア用品メーカー?」と思いがちですが、
中身を作っているのは、もともと「動物の薬」を専門にしている会社というのがポイントです。
バイオ科学の本業は「畜産・水産の現場を支えること」
バイオ科学のメインの仕事は、ざっくり言うと
「牛・豚・鶏・魚など“人の食料になる動物”を、健康に育てるための薬や栄養剤をつくること」
です。
具体的には、次のような分野があります。
畜産関連事業
- 牛・豚・鶏などの病気を予防・治療する薬やワクチン
- 牛の胃で分解されにくくして、きちんと栄養が届くようにした
ルーメンバイパス製剤「乳肝(ミルカン)」などの栄養剤 - 乳量アップ・健康維持のためのサプリメントや機能性飼料
→ 簡単に言うと、酪農家や畜産農家の「牛や豚を丈夫に育てたい」「病気を減らしたい」というニーズに応える製品です。
水産関連事業
- 養殖用の魚の病気を防ぐワクチン
- 魚のストレスを減らすサプリメントや機能性飼料
- フェノキシエタノールを主成分とする
世界初の魚類用麻酔剤などの開発実績もあるとされています。
魚を輸送するとき、暴れたりケガをしたりしないように、軽く眠らせるための麻酔剤などですね。
商社・OEM事業
- ビタミン・ミネラル・アミノ酸など原料の輸入販売
- 他社ブランドの栄養剤を受託製造(OEM)
こうした事業を通じて、日本だけでなく海外にも製品を提供しており、
アジア最大級の畜産・水産業の展示会「VIV ASIA」にも出展するなど、
国際展開にも積極的です。
会社のパーパスは「世界の食料生産の課題を解決する」
求人情報などで語られているバイオ科学のパーパス(存在意義)は、
「世界の食料生産の課題を解決する」
というものです。
世界的に人口が増え続ける中で、
- 限られた土地・資源で、どれだけ効率よく安全な食料を生産できるか
- 病気や感染症で、家畜や魚が大量に倒れてしまうリスクをどう減らすか
- 環境負荷を減らしながら、持続的に生産を続けられるか
といった課題があります。
バイオ科学は、
- 病気を減らすワクチンや薬
- 栄養効率を高める飼料やサプリメント
などを通じて、「少ない資源で、健康な動物を育てる」ことをサポートしている会社です。
こうした背景を知ると、のちほど紹介する
「人も熊も守る熊スプレーをつくる」
という発想とも、自然につながってくるはずです。
なぜバイオ科学が熊スプレー「熊一目散」を開発したのか
ここが、読者として一番気になるところだと思います。
背景:全国で増える熊との遭遇
近年、日本各地で
- 住宅地や市街地に熊が出る
- 農作物が荒らされる
- 登山中や里山の散歩中に人が襲われる
といったニュースが相次ぎ、熊撃退スプレーの需要も急増しています。
ただ、これまでは
- 熊スプレーのほとんどがアメリカ製
- 日本で買うと為替や輸送コストの影響で価格が高い
- 国内での安定供給にも不安がある
といった課題がありました。
国産熊スプレーを作ろう、というチャレンジ
バイオ科学は、こうした状況を受けて
「日本の会社が、日本の環境と実情に合わせた熊スプレーを作るべきではないか」
と考え、約3年かけて国産熊スプレー「熊一目散」を開発しました。
開発には、
- 熊研究の第一人者とされる
酪農学園大学・佐藤喜和教授が監修として参加し、 - 実際にヒグマなどを対象にしたフィールドテストや、忌避効果の検証が行われた
と紹介されています。
開発担当者は、
「人を襲った熊は駆除されてしまう。不必要な接触事故を減らすことで、人も熊も守りたい」
という趣旨のコメントも出しており、
単に「熊を撃退する道具」ではなく、「人と熊の距離を適切に保つための道具」という位置づけで作られています。
「熊一目散」に生かされているバイオ科学の強み
では、動物用医薬品メーカーとしての経験は、熊スプレーにどう生かされているのでしょうか。
ポイントを整理すると、次のようになります。
① 動物を相手にした製品の「安全性・品質管理」のノウハウ
バイオ科学は長年、
- 家畜用ワクチン
- 動物用医薬品
- 飼料添加物
などを製造してきました。これらは人の食品になる動物に直接使うものなので、
- 成分の安全性
- 製造ラインの衛生管理
- 有効成分の濃度管理
- ロットごとの品質検査
といった、かなり厳しい品質管理が求められます。
この「安全で安定した製品を作り続ける仕組み」が、そのまま熊スプレーの製造にも生かされていると考えられます。
② 大学との共同研究に慣れている
バイオ科学は、国内外の企業や大学と共同で研究開発を行う体制を持っています。
今回も、酪農学園大学との連携で
- 熊に対する忌避効果の検証
- 実際のフィールド(北海道など)でのテスト
が行われていることから、研究と現場をつなぐ開発スタイルが見て取れます。
③ 国内自社工場での製造=安定供給と価格面のメリット
熊一目散は、徳島の本社・工場で国産製造されています。
海外製の熊スプレーは、
- 為替の影響で価格が大きく変動
- 輸入が滞ると、必要な時に手に入りにくい
といった問題がありますが、国産品であれば
- 価格が比較的安定しやすい
- 需要が増えたときに、増産などで対応しやすい
というメリットがあります。
実際、新聞報道でも
「米国製品と同等の性能で、価格はおよそ半額程度に抑えた」
と紹介され、各地の消防署や電力会社などから問い合わせが相次いでいるとされています。
④ 環境への配慮(HFCガス不使用)
熊一目散は、噴射に使うガスにもこだわりがあります。
- 多くの海外製熊スプレー:温暖化物質である「HFCガス」を使用
- 熊一目散:環境負荷の少ない「LPガス」を採用
と明記されており、気候変動にも気を配った設計になっています。
⑤ 現場目線の「使いやすさ」設計
バイオ科学は、普段から
- 養殖業者
- 畜産農家
- 飼料メーカー
といった「現場の声」に向き合って製品を作っている会社です。
熊一目散でも、
- 日本人が日常的に触れ慣れたボタン式ノズル
- 誤噴射を防ぐ安全キャップ
- 片手で素早く取り出せる専用ホルダー
- 本番と同じ感覚で練習できる「練習用スプレー」も別売り
など、「いざという時にきちんと使えるように」という“現場のリアル”が反映された仕様になっています。
メディアからの注目度と社会的な信頼
「熊一目散」は発売直後から、
- 地方紙や全国紙のウェブ記事
- テレビ番組の特集コーナー
- 各種アウトドアショップやワークウェアメーカーのニュースリリース
などで、「国産の新しい熊撃退スプレー」として広く紹介されました。
バイオ科学自身も、自社サイトで
- 全国各地での熊出没増加の現状
- 「熊一目散」がテレビやアワードで取り上げられた実績
- 練習用スプレーの開発
といった情報を公開しており、単発の商品ではなく、継続的な取り組みとして位置づけていることがわかります。
どんな人が会社を率いているのか
バイオ科学の代表取締役は奥谷 飛さんです。
求人情報などでは、
- 動物用医薬品分野での安定成長
- 社員の定着率が高いこと
- 海外展開への積極的な姿勢
などが会社の特徴として挙げられており、
長期的な視点で事業を育てている印象があります。
熊一目散のリリースでも、
「人も熊も守るために、不必要な接触事故を減らしたい」
というメッセージが前面に出ており、“食料生産を支える会社”としての視点と、“野生動物との共存”という視点がつながっているように感じられます。
「熊一目散」を検討している人への注意点・上手な付き合い方
ここまで読むと、
「バイオ科学って、ちゃんとした会社なんだな」
という印象を持った方も多いと思います。
ただし、どれだけ信頼できる会社の熊スプレーでも、「持っていれば絶対安全」ではないという点は、強調しておきたいところです。
熊スプレーは「最後の最後の保険」
- 熊鈴やラジオ、複数人での行動
- 出没情報のチェック
- 夕方〜夜明けの行動を避ける
といった 「そもそも熊と鉢合わせしない工夫」 が最優先です。
熊スプレーは、
「それでも遭遇してしまったときに、自分の命を守るための“最後の保険”」
と考えるのが現実的です。
使い方の練習と保管も大事
- 必ず公式マニュアル・注意書きをよく読む
- 可能であれば、練習用スプレーで噴射の感覚を掴んでおく
- 高温になる車内放置などは避け、説明書どおりの温度で保管
- 使用期限(製造から約5年)も確認し、古くなったものは買い替え
など、「持つだけで満足しない」ことが、いざという時の生死を分けます。
まとめ:バイオ科学は「動物のいのちを扱ってきた会社」
最後に、ポイントを整理します。
「どこの誰が作っているか分からない謎のスプレー」ではなく、
「動物のいのちを扱ってきた会社が、熊との“適切な距離”を守るために作った道具」
と理解すると、熊一目散の位置づけが少しクリアになるのではないでしょうか。