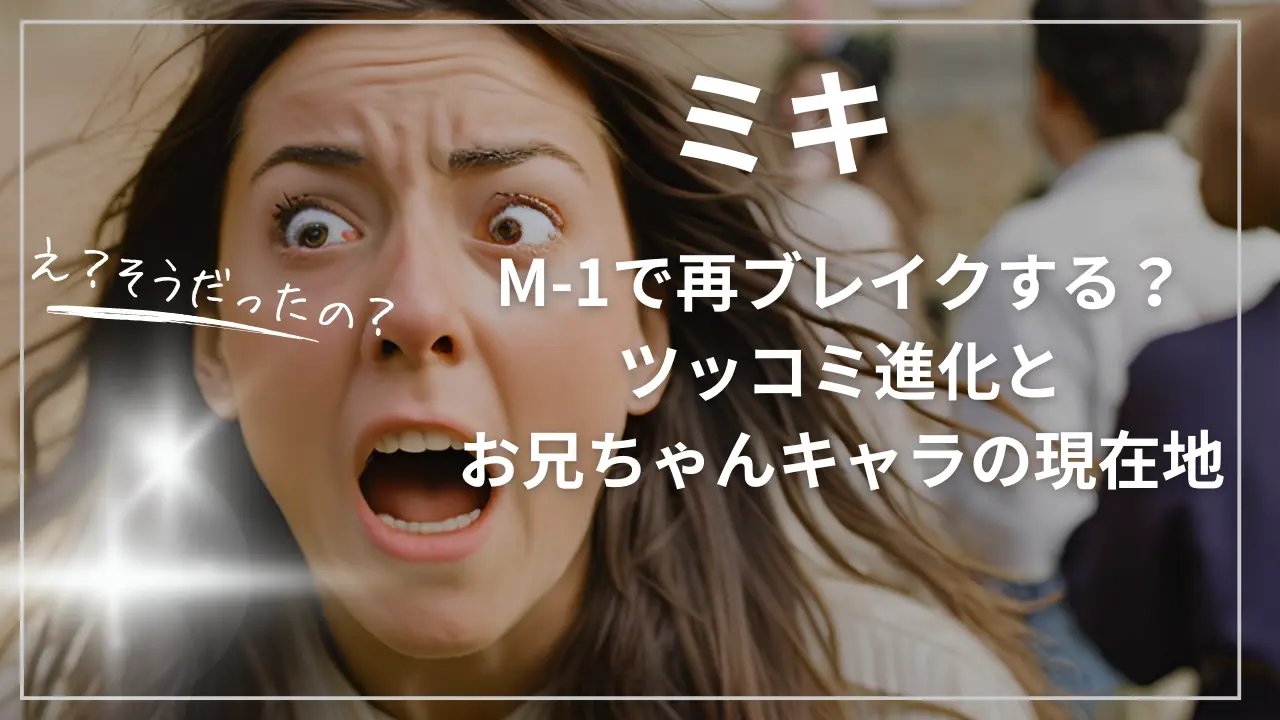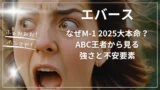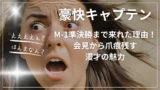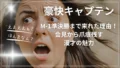2025年のM-1グランプリでは、ミキが準々決勝を突破し、準決勝進出30組の中に名前を連ねました。
2017年・2018年の決勝進出、そこからの伸び悩み時期を知っているファンからすると、
「え、またミキ来てるやん」
「この感じ、ちょっと再ブレイクっぽくない?」
と感じている人も多いはずです。
しかも2025年は、全国ツアー「ミキ漫2025」で47都道府県を回り切る計画を立てており、劇場・ホールでの生の漫才にも全力。
テレビ・ラジオで見ない週がないくらい忙しい中で、
それでも漫才にこだわり続け、M-1の準決勝まで上がってきている。
この状況を、この記事では「静かな再ブレイク期」と呼びながら、
- そもそもミキってどんなコンビだったのか
- 昴生のツッコミはどう進化したのか
- 「お兄ちゃんキャラ」は今、どんなポジションにいるのか
- 2025年のM-1で、どこまで行けそうなのか
を整理していきます。
まずおさらい:ミキってどんなコンビ?
兄・昴生と弟・亜生の兄弟漫才コンビ
- 所属:吉本興業
- 結成:2012年4月、京都で結成
- メンバー:
- 兄・昴生(こうせい)…ツッコミ担当
- 弟・亜生(あせい)…ボケ担当
ハイスピードでしゃべり倒す「しゃべくり漫才」が持ち味で、
2016年にはNHK上方漫才コンテストで優勝。
その後も各種賞レースで結果を残し、テレビのレギュラー番組やCMにも多数出演する“売れっ子コンビ”へと成長しました。
M-1でのこれまでの成績
M-1グランプリでの主な成績はこんな感じです。
- 2015年:準々決勝進出
- 2016年:準決勝進出
- 2017年:決勝進出・3位(最終決戦進出)
- 2018年:決勝進出・4位(敗者復活から決勝へ)
- 2019年:準決勝敗退
- 2020年:準々決勝敗退
- 2021年:準々決勝敗退
- 2022年:準決勝進出(敗者復活戦3位)
- 2023年:準々決勝敗退
- 2024年:準々決勝敗退
- 2025年:準決勝進出(※現在進行形)
2017年に初めて決勝に出て、いきなり3位。
この年の決勝は「とろサーモン優勝、和牛2位、ミキ3位」という並びで、
ミキの名前が一気に全国区になりました。
一方で、その後は決勝の壁に何度も跳ね返され続けているのが現実です。
一度目のブレイクから「長いトンネル」まで
「若手スター」から「中堅手前の勝負期」へ
2017~2018年ごろのミキは、
- M-1決勝の常連候補
- 情報番組のレギュラー
- 兄弟コンビならではのバラエティ対応
…と、いわゆる「若手スター」のポジションにいました。
ところが、M-1の結果だけで見るとその後は
決勝までは行くけど優勝はできない
→ そもそも決勝に届かなくなる
という流れになっていきます。
2020年代前半は、他の若手コンビがどんどん台頭してくる時期でもありました。
令和ロマンやエバース、カベポスター、豪快キャプテンなど、新しい世代のコンビがM-1で名前を売っていきます。
その中でミキは、
- テレビ・ラジオの仕事は途切れない
- でもM-1ではもう一歩届かない
という、少し難しい立ち位置にいました。
「主軸はあくまで漫才」という軸
そんな中でも、ミキはインタビューで
「マルチに仕事はしているけれど、主軸はあくまで漫才」
とはっきり語っています。
M-1敗退をきっかけに、
- 自分たちが“芸能人”になりすぎていないか
- 芸より露出が先走っていないか
を振り返り、もう一度「漫才を真ん中に置く」ことを確認したと話しています。
そして2025年、「ミキ漫2025」全国ツアーで47都道府県を回る計画を立てるほど、
劇場・ホールでの漫才に力を入れているのは、その覚悟の表れだと言えます。
ツッコミはどう進化した? 昴生の「3つの変化」
この記事のタイトルにもあるように、
2025年のミキを語るうえで外せないキーワードが「ツッコミの進化」です。
ここでは、兄・昴生のツッコミがどう変わってきたのかを、
わかりやすく3つのポイントに分けて整理します。
① 「怒鳴るツッコミ」から「温度を調整するツッコミ」へ
昔のミキと言えば、
- 大声でまくしたてる
- 高速で何発もツッコむ
- 「なんでやねん!」の連打
というイメージが強かったと思います。
もちろん今でも熱量は高いのですが、最近の昴生は
- あえて“ちょっと静かに”ツッコむ
- 小声でボソッと言って笑いを起こす
- ひと呼吸おいてからツッコむ
など、声の大きさ・間の取り方を細かく調整するスタイルが増えてきました。
2024年の座談会では、先輩ツッコミ芸人たちから
「今年一番進化していたのは昴生」と評される場面もあり、
ツッコミのクオリティが同業者から見ても評価されていることがわかります。
②「ただ怒る兄」から「説明する兄」へ
昔の昴生は、「怒っているお兄ちゃん」というキャラが前面に出ていました。
- 「しっかりせえ!」
- 「何してんねん!」
- 「お前のその感じや!」
など、感情そのままの言葉でツッコむことが多かった印象です。
最近はそこに一文、説明が足されるようになっています。
「〇〇やと思ってたのに△△してるやん」
「普通はこうするやろ?なんでそれをあえて外すねん」
といった、「なぜおかしいのか」をちゃんと言葉にしてくれるツッコミが増えました。
これは、視聴者にとってもかなりありがたい変化で、
- 漫才をあまり見ない人でも笑いやすい
- ラジオやテレビのトークでもオチがわかりやすい
という効果を生んでいます。
③ ツッコミの裏に「兄弟愛」が見えるようになった
昴生のツッコミが“うるさいだけ”に感じられない理由のひとつが、
その裏に弟への愛情や責任感が透けて見えるところです。
2018年に放送されたドッキリ番組では、
「弟の亜生が芸人を辞めたい」と告白する仕掛けに対して、昴生が
「お前と漫才やるから意味あんねん。他のやつとやっても意味ない」
「お前の限界、俺が上げたるやん!」
と本気で訴えかける姿が話題になりました。
このエピソードからもわかるように、
- 「うるさい兄ちゃん」ではなく
- 「相方として責任を取る兄ちゃん」
としてのキャラが、年を重ねるごとに前に出てきています。
その“兄の覚悟”が、2025年のツッコミの説得力にもつながっていると言えるでしょう。
変わらない武器:亜生のボケと「弟キャラ」
一方の弟・亜生は、いい意味でずっと「弟のまま」です。
家族インタビューでは、
- ミキ家では「お兄ちゃんが絶対」というルールがあった
- 亜生は本当に「弟、弟」して育った
という話も出てきます。
このバックボーンがあるからこそ、
- ちょっと甘えた感じのボケ
- 小学生みたいな言い訳
- 「兄ちゃんやってよ〜」と頼りにいく姿
が、作り物ではなく“素”に近いものとして伝わってきます。
ミキの漫才がただの掛け合いではなく「兄弟漫才」に見えるのは、
- 亜生が本当に弟らしくボケる
- 昴生が本当に兄としてツッコむ
というリアルな関係性が、そのままネタの中に持ち込まれているからです。
2025年のネタを見ていても、
- 令和の価値観や若者っぽい感覚を持つ亜生
- 昭和~平成っぽい「兄目線」でツッコむ昴生
という世代ギャップ的な構図がより強くなっていて、
ここが今のM-1の観客層とも相性がよくなってきていると感じます。
「お兄ちゃんキャラ」の現在地とテレビでの立ち位置
昔:いじられがちな“シミ扱いの兄”
デビューから数年は、
- 「弟の方がモテる」「人気がある」
- 「兄はシミ扱い」といじられる
といったエピソードもよく語られていました。
観客から見ても、
- 兄:うるさくてイライラしがちな人
- 弟:ふわっとした人気者
という図がわかりやすく、
番組側もその“人気格差いじり”をよく使っていました。
今:まとめ役・MC側に寄ってきた昴生
ところがここ数年のテレビを見ていると、
昴生は
- MCに近い立ち位置
- 番組の進行を助ける側
- ゲストをイジりつつも最後はちゃんとフォローする
という「まとめ役」ポジションを任されることが増えています。
その一方で亜生は、
- 動物好き・釣り好き
- ちょっと天然で、やさしい人柄
といった“癒やし系の弟キャラ”を伸ばしており、
2人のキャラクターが良いバランスで分かれてきました。
「兄が仕切れるようになった」ことは、漫才にとっても大きなプラスです。
- ネタの世界観を作る
- ボケをちゃんと紹介する
- オチに向かって話を運ぶ
といった役割を、昴生が前よりも丁寧にこなせるようになったことで、
ネタ全体の“ストーリー感”が増し、M-1の4分ネタとしての完成度も上がってきています。
ミキが「M-1再ブレイク候補」と言える3つの理由
ここまでの話を踏まえて、
なぜ2025年のミキを「M-1で再ブレイクしそうなコンビ」と見る人が多いのか。
ポイントを3つに絞って整理します。
理由①:実績と経験を持ったまま、再び準決勝まで戻ってきた
- 決勝経験あり(3位・4位)
- その後、何度も敗退を経験
- それでもエントリーし続けている
というコンビが、2025年にまた準決勝まで上がってきたという事実はかなり重いです。
新人コンビなら「勢い」で説明できますが、
中堅に差し掛かったコンビがここまで登ってくるのは、
- ネタの再構築がうまくいっている
- 今の観客・審査員に合う形にチューニングできている
というサインでもあります。
理由②:ツッコミの進化が“同業者”からも評価されている
前述の座談会で、
カンニング竹山、ハライチ澤部、アンガールズ田中らが
「今年一番進化していたのは昴生」
と口をそろえて語っていたのは象徴的です。
同じツッコミ職人たちから見ても、
- ボケの活かし方
- 自分の感情の見せ方
- ネタ・番組内での立ち回り
が明らかにレベルアップしている、ということ。
M-1は「ツッコミの大会」と言ってもいいくらい、
ツッコミの力量が結果に直結するコンテストです。
そのポイントで評価が上がっているのは、再ブレイクを語るうえで大きな材料になります。
理由③:漫才を主軸にした活動量が圧倒的
- 劇場・ホールでの全国ツアー「ミキ漫2025」
- ラジオ番組でのトーク力の鍛錬
- テレビでも漫才を意識した立ち回り
など、「主軸は漫才」と口で言うだけでなく、
実際のスケジュールの組み方も漫才中心になっています。
漫才の本数が多いということは、
- ネタの精度が上がる
- 会場ごとのウケ方を調整できる
- M-1の4分に最適化しやすい
という意味で、賞レース的にも大きな武器です。
2025年M-1で、ミキにどこまで期待していいのか
現時点(準決勝進出が決まった段階)で、
ミキが2025年のM-1でどこまで行けそうかを、個人的な見立てベースでまとめると…
- 決勝進出の可能性は十分ある
- 経験値+ツッコミの進化+漫才本数
- 準決勝メンツの中でも「名前と実績」はトップクラス
- 優勝候補かと言われると、まだ“ダークホース寄り”
- 新世代のエッジの立ったコンビたち(令和ロマン、エバース、豪快キャプテンなど)と比べると、サプライズ感ではやや劣る部分もある
- ただし「兄弟漫才」「兄のツッコミ進化」という物語性が、決勝の空気とハマると一気に優勝圏内に入る可能性もある
- “ミキの年”というより、“ミキ再ブレイク元年”になるかも もし決勝に進出できなかったとしても、
- 2025年のネタでつかんだ手応え
- ツッコミ進化への評価
- 全国ツアーでのファンの反応
「2025年前後から、ミキまたおもろくなってきたよね」という空気がじわじわ広がっていくはずです。
まとめ
最後に、この記事のポイントをサクッと整理します。
2025年のM-1は、
ミキにとって「優勝を狙う大会」であると同時に、
「進化した兄弟漫才を、全国にもう一度見てもらうための実験場」
でもあります。
結果がどう転んでも、
- ツッコミが進化したお兄ちゃん・昴生
- 変わらない弟キャラ・亜生
- そして、漫才を主軸に据え直したミキ
という3点セットが、
これから数年間の“静かな再ブレイク”を作っていくのは間違いないでしょう。
M-1本番では、ぜひ
「昔のミキ」と「今のミキ」
どこが変わって、どこが変わっていないのか
を意識しながらネタを味わってみてください。