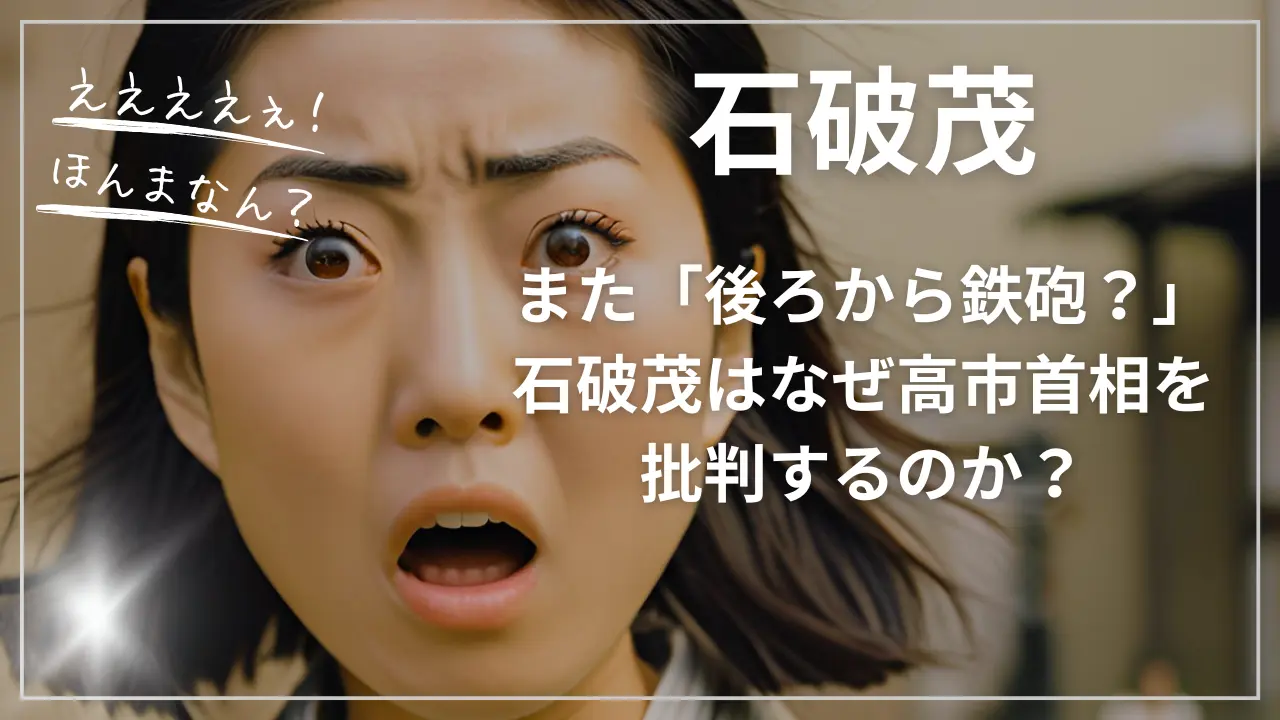高市早苗さんが首相になってから、まだ日が浅いのに、早くもネットではこんな声が飛び交っています。
「石破、また後ろから鉄砲撃ってるじゃん」
「前首相なんだから、もうちょっと静かにしててよ…」
実際、石破茂・前首相は、中国新聞のインタビューなどで、高市内閣の「連立の組み方」や「コメ政策の転換」にかなり辛口のコメントをしています。
この記事では、
- そもそも「後ろから鉄砲」って何のこと?
- 今回、石破さんは高市首相の何に怒っているのか?
- それは“ただの足を引っ張っているだけ”なのか、“必要な苦言”なのか?
を整理していきます。
今、何が起きている?ざっくり時系列まとめ
まずは最近の流れを、ニュースをもとにサクッと整理しておきます。
高市内閣が誕生
2025年10月21日、高市早苗さんが第104代内閣総理大臣に就任しました。戦後初の「女性首相」として、かなり大きな話題になりました。
高市内閣の特徴としてよく言われるのが、
- 自民党と日本維新の会による新しい連立政権
- 「責任ある積極財政」を掲げた、かなり攻めた経済・財政運営
という2点です。
実際、経済財政諮問会議や成長戦略会議に「リフレ派(積極財政&金融緩和を支持する経済学者)」を次々と起用し、
「アベノミクス再び?」と金融市場でも注目されています。
その一方で「公明党との連立解消」や「コメ政策転換」
一方で、高市政権は長年続いた公明党との連立を離れ、日本維新の会との連立に舵を切りました。
さらに農業、とくにコメ政策についても、高市内閣で方向転換が始まっています。
石破内閣時代に作った政策が、早くも見直されつつあるわけです。
そこに、前首相・石破茂が苦言
そして10月30日、石破茂・前首相が中国新聞デジタルのインタビューでこのような発言をしました。
- 維新との連立は「すごく違和感がある」
- 自民党がさらに保守に傾くことを「懸念している」
- コメ政策の方向転換については「不愉快な話だ」
これが報じられると、SNSでは、
「また後ろから鉄砲かよ」
「前首相が10日でこれ言う?」
という批判が一気に広がりました。
そもそも「後ろから鉄砲」って何?
「後ろから鉄砲を撃つ」
この言葉は、石破さんにつきまとってきた“レッテル”のようなものです。
意味としてはざっくり言うと、
「同じ政党にいながら、
表で味方っぽい顔をして、
裏では批判ばかりしている人」
というニュアンスです。
安倍政権時代から言われ続けてきた言葉
石破さんは、安倍政権の時代から、安保法制や森友・加計問題などで、かなりハッキリと批判的な発言をしてきました。
そのたびに、
「同じ自民党なのに、なんで野党みたいなこと言うんだ」
「後ろから鉄砲を撃つような真似はやめろ」
と、党内外から批判されてきた歴史があります。
石破本人はどう考えているのか
しかし石破さん自身は、この「後ろから鉄砲」批判に対して、こう反論しています。
- 同じ政党だからこそ、
おかしいと思うことは遠慮なく言うべきだ - 誤りは誤りだと指摘することが
政権を守ることにもつながる - だから、党内で異論を唱えるのは
むしろ義務だと考えている
つまり石破さんにとっては、
「後ろから撃っているつもりはない。
正面から、ちゃんと問題点を言っているだけだ」
という自己イメージなんですね。
今回、石破茂は高市首相の“何”を批判しているのか?
では、今回の高市政権に対して、石破さんは具体的に何を問題視しているのでしょうか。
ポイントは大きく3つあります。
① 日本維新の会との連立への「違和感」
石破さんはインタビューの中で、日本維新の会との連立に対して、こんな趣旨のことを語っています。
- 維新は「新自由主義的」である
- その維新と連立することで、
自民党がさらに「保守」側に傾くことを心配している
ここで言う「新自由主義的」とは、
「自己責任を強く求める、小さな政府志向」
「市場原理を重視し、弱い立場への公的な支援が弱くなりがち」
というイメージです。
石破さんは、
「自民党があまりにそちら側に寄りすぎると、
中間層や弱い立場の人を置き去りにするのではないか」
という危機感を持っている、と考えられます。
② コメ政策の“方向転換”への怒り
2つ目は、コメ政策です。
石破内閣は、農家の安定と食料安全保障を両立させるため、コメの生産や価格を支える政策を進めてきました。
ところが高市政権では、財政負担の見直しなどもあり、コメ政策の方向転換が始まっています。
これに対して石破さんは、
- 自分たちが一生懸命つくった政策が
あっさり変えられたことへの不満 - コメを単なる「コスト」として扱うような発想への怒り
から、「不愉快な話だ」とまで言ったとされています。
③ 政権運営の“右寄り化”への不安
3つ目は、政権全体の「右寄り化」です。
高市首相は所信表明演説などで、強い安全保障政策や、積極的な財政出動を打ち出しています。
もちろん、これ自体は「強い日本をつくる」という意味で、支持する人も多いでしょう。
しかし石破さんは、
維新との連立+積極財政+強い安保路線
→ 自民党がかなり右側に寄り過ぎてしまうのでは?
と懸念しているように見えます。
なぜ「また後ろから鉄砲」と言われるのか?
とはいえ、ここで出てくるのが、
例の「また後ろから鉄砲かよ」という声です。
なぜ、ここまで叩かれるのでしょうか。
タイミングが“早すぎた”
まず一つはタイミングです。
- 高市内閣が発足して、まだ10日足らず
- 高市首相が、ようやく組閣と国会対応で走り始めたタイミング
その時点で「違和感がある」「不愉快だ」と前首相が言えば、
「いやいや、せめてもう少し様子見してから言えよ」
「自分で推した後継じゃないの?」
と感じる人が多いのも、自然です。
「前首相」の立場だからこそのハードルの高さ
しかも今の石破さんは、
- ついこの前まで総理大臣だった
- まだ与党・自民党の重鎮の一人
という立場です。
その人がメディアで新政権をバッサリ批判すれば、
「だったら自分の政権の時に、
もっときちんとやってから辞めろよ」
と、ツッコミたくなる人もいるでしょう。
過去のイメージが“色眼鏡”になっている
そして何より大きいのは、
過去の「後ろから鉄砲」のイメージです。
安倍政権時代から、メディアでもネットでも、
- 「また文句言ってる」
- 「党内野党だ」
- 「ずっと批判してばかり」
という語られ方をされてきました。
一度ついてしまったイメージは、簡単には消えません。
だから今回も、
「高市首相になっても、
結局やってることは同じじゃん」
と、過去と同じパターンに見えてしまうわけです。
石破茂は“なぜ”あえて批判するのか?
ここまで読むと、
「いや、それでも今は黙って応援しとけばいいじゃん」
と感じる人も多いと思います。
では、それでも石破さんが発言する理由は何なのか?
考えられるポイントを3つに分けてみます。
① 「与党の中でも、ブレーキ役が必要だ」という信念
石破さんは、先ほどのインタビューでも、過去の文章でも一貫して、
「同じ党だからこそ、
間違いは間違いと言うべきだ」
というスタンスを取っています。
つまり、
- 野党から批判するだけでは、政策は変わらない
- 与党の中から「それは違う」と言える人がいないと、
暴走してしまう
という危機感を持っている、とも読めます。
彼にとっては、高市政権の「保守色の強さ」や「連立の組み方」は、
それくらい危ない匂いがするテーマなのかもしれません。
② 自分の「レガシー」を守りたい
もう一つの側面として、
前首相としてのプライド(レガシー)もあるでしょう。
- コメ政策など、自分の政権で苦労して作ったものが、
あっさりひっくり返される - さらに、それが「前より良くなった」と評価されると、
自分の政権は“失敗だった”と見なされかねない
人間として、これはなかなかつらい状況です。
だからこそ、
「ちょっと待て、それは違うだろ」
と言いたくなる気持ちは、理解できる部分もあります。
③ 「高市一強」にならないようにしたい
そして3つ目は、
高市政権の一強化を防ぎたいという思惑です。
- 高市首相は、就任直後からかなり高い支持率
- 女性首相という“新しさ”
- 積極財政や強い安保路線という“分かりやすさ”
これらが組み合わさると、「高市一強」体制になりやすい土壌が整います。
そこに、
党内からも何も文句が出ない
→ ますますブレーキが効かなくなる
という流れを、石破さんは警戒している可能性があります。
「後ろから鉄砲」か「必要な苦言」か――私たちはどう見ればいい?
では、私たち有権者は、この構図をどう見ればいいのでしょうか。
プラス面:与党内の“異論”には価値がある
まず、プラスの面から見てみます。
- どんなに優秀な政権でも、
すべての判断が正しいわけではない - だからこそ、同じ与党の中からのチェックは、
民主主義にとって重要な役割
これは、原則として間違っていない考え方です。
とくに高市政権のように、
「積極財政+強い安保+維新と連立」という、
かなりドラスティックな路線を取る内閣については、
「本当にそれで大丈夫?」
「どこかで歯止めはかかるの?」
と疑問を持つ声が、党内にあること自体は自然です。
そういう意味で、石破さんの存在は、
「与党の中のブレーキ」
「もう一つの保守」
としての意味も持ち得ます。
マイナス面:タイミングと“言い方”の問題
一方で、やはり問題として見られやすいのは、
- タイミングがあまりに早すぎる
- 表現が「違和感がある」「不愉快だ」など、
感情的に聞こえやすい
という点です。
同じ内容でも、
- 内々の党内会合で、
データを示しながら冷静に説明する - 公には、「こういう点が心配なので、丁寧に検討してほしい」
くらいのトーンに抑える
という形であれば、
ここまで「後ろから鉄砲」とは言われなかったかもしれません。
結局は「見たいものが見える」
政治家への評価は、結局のところ、
こちら側が、その人に何を期待しているか
によって、大きく変わります。
- 元々石破さんが好きな人
→ 「よく言ってくれた。これくらい言える人がいないと困る」 - 元々石破さんに不信感がある人
→ 「ほら出た。また後ろから撃ってるよ」
今回の一件も、
多くの人が自分の“元々持っていたイメージ”を
そのまま重ねて見ている、という面は否めません。
今後、私たちがチェックすべきポイント
最後に、「なんとなくモヤモヤする」で終わらせないために、
今後どこを見ていけばいいのかを整理しておきます。
① 高市政権の政策は、ちゃんと説明されているか
- 維新との連立で、どんなメリット・デメリットがあるのか
- コメ政策の変更で、農家と消費者に何が起きるのか
- 積極財政の結果として、将来の負担はどうなるのか
これらについて、高市政権がどれだけ丁寧に説明するかは、
大事なチェックポイントです。
② 石破茂の批判は、「ただの文句」で終わっていないか
一方で、石破さん側にも、私たちはこう問うべきでしょう。
- 具体的に、どの政策のどこが問題なのか
- それに対して、代わりにどんな案を出すのか
- 党内の場で、どの程度きちんと議論しているのか
もし単に、
「違和感がある」「不愉快だ」と言って終わり
なのであれば、それはやはり“文句”に見えてしまいます。
しかし、
「こういうデータがあるから、このやり方は危ない。
だから、こう修正すべきだ」
と具体的に提案できているなら、
それは「後ろから鉄砲」ではなく、
健全な党内批判と言えるはずです。
③ メディア・SNSの「盛りすぎ」にも注意
そしてもう一つ。
- 見出しのために、発言の一部だけが切り取られる
- SNSで、元発言を読まずに引用と感情だけが増幅される
こうした現象が起きるのは、今や日常茶飯事です。
だからこそ、私たちとしては、
「見出し」と「まとめ記事」だけで判断しない
→ できるだけ元のインタビューや会見の全文に近いものを読む
という姿勢も、大事になってきます。
まとめ
改めて、この記事のポイントをまとめます。
「後ろから鉄砲」という言葉は、分かりやすくて便利ですが、
時に“思考停止の合言葉”にもなります。
- 本当に“後ろから”なのか
- 本当に“鉄砲”レベルの攻撃なのか
- それとも、必要な苦言なのか
一つひとつの発言を、
できるだけラベル抜きで見ていくことが、
これからの政治を考えるうえで大事なのかもしれません。