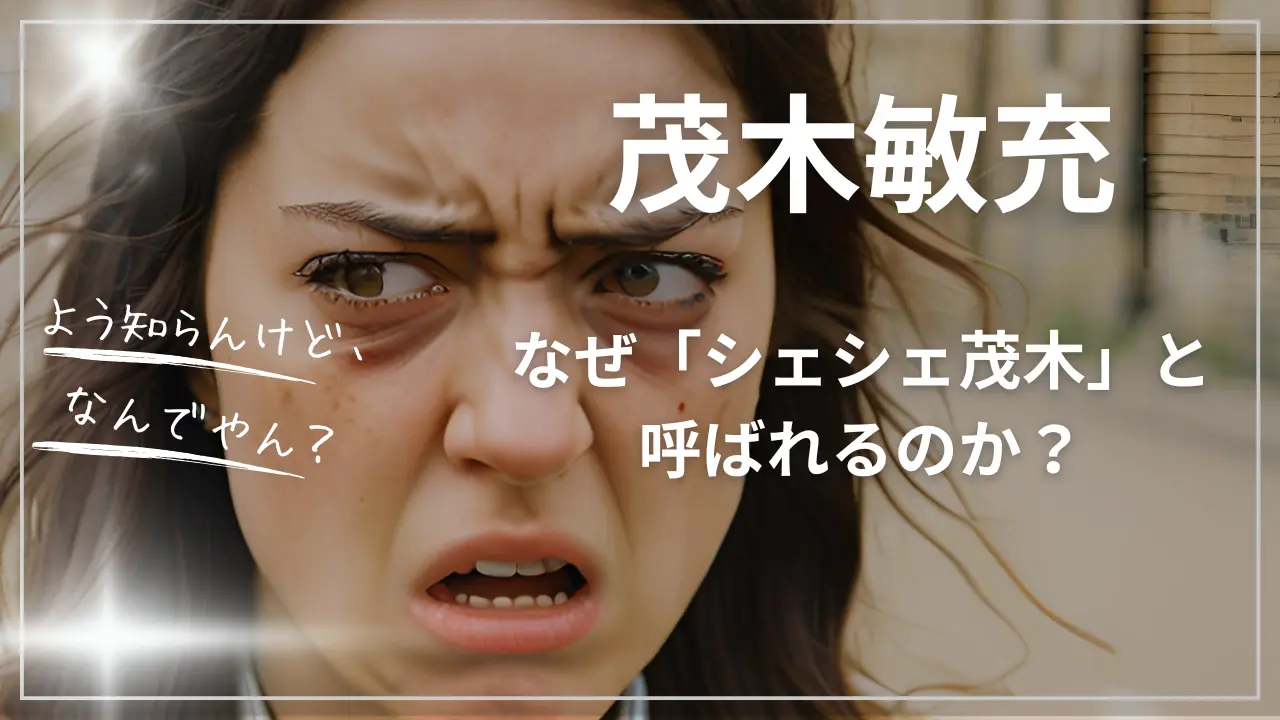SNSで見かけることが多い呼び名――「シェシェ茂木(シェイシェイ茂木)」が、なぜ生まれ、どう広がったのかを整理していきます。
結論を先に:呼び名のきっかけは「謝謝(シェイシェイ)」
この呼び名は、2020年11月24日、当時外務大臣だった茂木敏充さんが、中国の王毅外相と会談した前後のやり取りがきっかけです。
記者からの質問に答える場面で、茂木さんが中国語で「謝謝(シェイシェイ=ありがとうございます)」と口にしたことが映像・文字起こしに残り、これをきっかけに一部のネット上で「中国に気をつかいすぎだ」という文脈であだ名化した――というのが大まかな流れです。
実際、外務省の公式会見録にも、冒頭で中国メディアの記者に応じる形で「謝謝」とあるので、事実として「謝謝」と言ったのは確認できます。
何が起きていた?当日の流れをざっくり
- 日時:2020年11月24日(火)
- 相手:中国の王毅(おう・き)国務委員兼外交部長(外相)
- 用件:日中外相会談と共同記者発表
- 背景:コロナ禍で途絶えていた日中の高官往来を再開する節目。
この日の共同発表で、王毅外相は尖閣諸島(中国名:釣魚島)をめぐる主張を述べ、日本側と食い違う発言を行いました。これに対し、その場ですぐ強い言い返しがなかったという見方が自民党内の一部からも出て、批判記事・解説が相次ぎました。
一方で、茂木さんが「謝謝」と言った文脈は、外務省の会見録を見ると、中国メディアの記者からの質問に対して、礼儀として冒頭に「謝謝」と返したという形です。これは外交会見では珍しくありません(日本語の会見でも「ご質問ありがとうございます」にあたるひと言です)。
なぜ「シェシェ茂木」という呼び名になったのか
1) 視覚・聴覚の“強い印象”
動画や文字起こしで「謝謝」という外国語フレーズがはっきり残ると、人の記憶に残りやすいものです。しかもテーマは尖閣というナイーブな主権問題。そのため、「その場で中国に配慮したのでは?」と感じた人が、短いラベル(ニックネーム)で揶揄しやすくなりました。
2) 「その場で反論しなかった」という政治的評価
当時の解説・論評には「その場で明確に言い返すべきだった」という意見が目立ちました。ここで“対中姿勢が軟弱”というレッテルと、「謝謝」という言葉がセットで拡散し、呼び名が定着していきます。
3) テレビ・ネット言説での再生産
テレビの討論番組やネット記事でもこの件が繰り返し語られ、感情のこもった表現が重なってラベルがさらに強化されました。
ここを誤解しない:事実と評価は別モノ
- 事実:当日、茂木さんは「謝謝」と言いました(会見録に明記)。
- 評価A(批判的):「主権問題を前に“謝謝”は印象が悪い。反論が弱い」
- 評価B(擁護的):「会見進行や通訳の都合もある。礼儀の“謝謝”自体は慣例的で、発言全体は日本の立場を主張している」※この擁護的見解は、後日の説明や通訳事情への言及を踏まえたものです。
ポイントは、「“謝謝”という一語」がSNSで切り出されると、動画の“瞬間風速”が評価のすべてになりやすいということ。外交の現場は発言順や同時通訳の有無で見え方が大きく変わります。実務的な主張は別の場面(会談本文や後段の説明)で出ることも多いのです。
タイムラインで整理
- 2020/11/20:王毅外相の訪日が事前発表。
- 2020/11/24:東京で日中外相会談・共同記者発表。尖閣をめぐり中日で対立する発言。茂木さんの「謝謝」もこの文脈で記録。
- 2020/11/26〜:自民党内の部会などで「対応が弱い」との批判が報じられる。
- 2020年末〜2021年:テレビ・ネット言説で繰り返し取り上げられ、「シェシェ(シェイシェイ)茂木」という呼び名が広がる。
ニックネームが生まれる“3つの条件”
- 短くて響きが面白い
「シェシェ」は音が軽く、からかい表現として拡散しやすい。 - 映像・言葉の“切り抜き”に強い
1語で象徴化できるため、SNSの見出しやサムネに向いている。 - 政治的対立の“記号”になった
対中強硬派vs対話重視派、といった国内の対立軸に乗って、呼び名が立場の記号として消費される。
(この3条件は今回に限らず、政治のニックネーム一般に見られる現象です。)
よくある疑問に答えます(Q&A)
Q1. 本当に「中国に頭を下げた」証拠なの?
A. いいえ、「謝謝」=「外交姿勢」ではありません。 会見録の該当箇所は、中国メディアの質問に対する礼儀の一言としての「謝謝」で、内容自体は日本側の論点(コロナ対応・二国間懸案など)に移っています。
Q2. その場で反論しないのは“弱腰”では?
A. 評価は分かれます。批判的な論考は確かに存在し、世論の一部はそれを支持しました。一方で、外交の場は発言順や通訳の仕様があり、強いメッセージは会談本文や後段の説明で打ち返すことも多い――という実務側の説明もあります。
Q3. じゃあ、なぜ呼び名が定着したの?
A. 「1語で印象が伝わる」「主権問題という強いテーマ」「国内政治の対立構図」という拡散条件がそろったからです。テレビやネットで繰り返し語られ、ラベルとして便利だったことも大きいでしょう。
もう一歩だけ深掘り:外交の“見た目”と“中身”
外交は、「その瞬間の映像」と「交渉の中身」がズレて見えることがよくあります。たとえば、
- 映像では柔らかい笑顔 → バックヤードでは厳しい条件提示
- 記者会見での礼儀的なひと言 → 公式文書での明確な立場表明
今回も、礼儀の“謝謝”が先に目に入り、対外メッセージの全体像が十分に共有されないまま、SNS上でレッテルが独り歩きした面があります。報道面でも、「その場での応酬」だけでなく、その前後の会談内容・外務省の説明までセットで見ることが、冷静な判断には大切です。
まとめ:呼び名に振り回されず、一次情報で確認を
- 「シェシェ茂木」という呼び名は、2020年11月の会見での“謝謝”が発火点。
- 批判は「主権問題の場面での“見え方”が悪い」ことに集中。
- 一方で、礼儀表現や通訳事情など、現場のコンテクストを考慮すべきとの見方もある(この点は百科事典的整理にも現れている)。
最後に、事実確認のための一次情報を置いておきます。興味があれば目を通してみてください。
- 外務省「茂木外務大臣会見記録」(2020/11/24)— 質疑応答の冒頭に「謝謝」の表記あり。外務省
- 王毅外相訪日についての外務省発表(2020/11/20)— 訪日の経緯や日程。外務省
- 在中国日本大使館サイトの会談要旨(中国語、2020/11/25)— 会談の公式整理。在中国日本国大使馆
- 批判報道の例:Arab News Japan(時事電、2020/11/27)— 自民党内の反応を紹介。Arab News
- 論考の例:JBpress(2020/12/3)— 対応を厳しく批判する記事。JBpress(日本ビジネスプレス)
- テレビ言説の例:東スポWEB(2021/11/6)— 番組での強い批判発言の紹介。東スポWEB