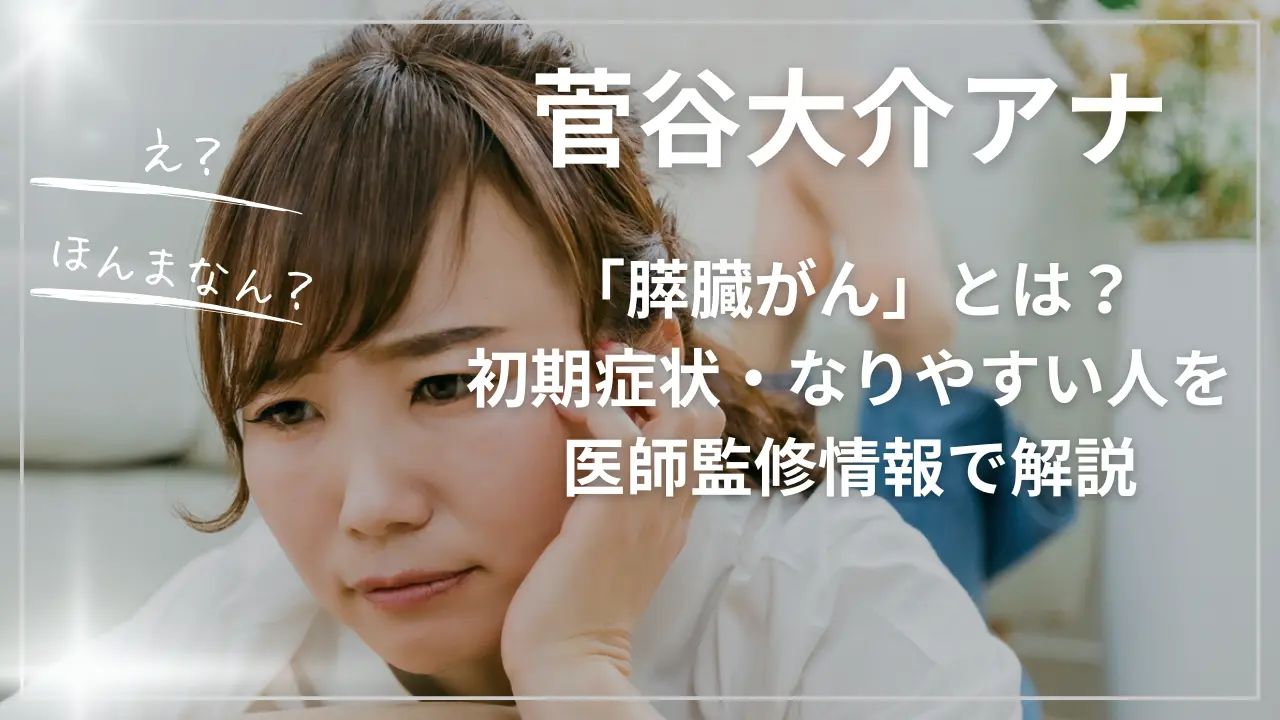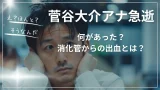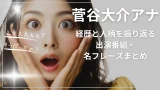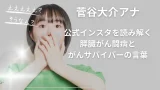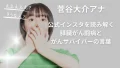菅谷大介アナの訃報にふれ、「膵臓がんってどんな病気なの?」「自分や家族は大丈夫なんだろうか」と不安になった方も多いと思います。
この記事では、できるだけ専門用語をかみくだいて、でも医師監修の公的サイトなどの情報にそって、膵臓がんのことを整理していきます。
※この記事は一般的な情報のまとめです。
具体的な症状や検査については、かならず医師や医療機関に相談してください。
菅谷大介アナの訃報と「膵臓がん」への関心
日本テレビの菅谷大介アナウンサーは、2022年に膵臓がんを公表し、その後も仕事を続けながら闘病していたことが報じられてきました。2025年11月8日、消化管からの出血のため53歳という若さで亡くなったとされています。
ニュースを見て、
- 「膵臓がんってそんなに怖い病気なの?」
- 「気づいたらもう手遅れって本当?」
- 「なりやすい人の特徴ってあるの?」
と感じた方も多いのではないでしょうか。
実は、膵臓がんは「早期発見がとてもむずかしいがん」として知られています。
まずは、膵臓(すいぞう)という臓器がどこにあって、どんな仕事をしているのかから見ていきましょう。
膵臓(すいぞう)ってどこにあって、どんな役割?
膵臓の場所
膵臓は、お腹のかなり奥、みぞおちの裏側あたりにあります。胃のうしろ側で、背中側に近い位置です。
そのため、
- 触ってもわからない
- 超音波(エコー)でも見えづらいことがある
といった理由で、病気が見つかりにくい臓器でもあります。
膵臓の仕事
膵臓の主な仕事は2つです。
- 消化液(膵液)を出す
- 食べものの中の脂肪やたんぱく質を分解する「消化酵素」がたくさん入っています。
- これがないと、食べてもきちんと栄養を吸収できません。
- 血糖値を調整するホルモンを出す
- 「インスリン」を出して、血糖値を下げる役割があります。
- ここに問題が起きると「糖尿病」の一因になります。
このように、膵臓は消化と血糖値コントロールという、どちらも生きていくためにとても大事な役割を持っています。
「膵臓がん」とはどんな病気?
膵臓がんの多くは「膵管がん」
膵臓がんは、膵臓の中でも「膵管(すいかん)」という膵液の通り道にできるがんがほとんどで、腺がんというタイプが多いと言われています。
がんができると、
- 膵臓そのものが壊れていく
- 膵液が流れにくくなる
- まわりの臓器(胆管や十二指腸など)にも影響する
といったことが起こります。
なぜ「見つかりにくい」のか
国立がん研究センターの「がん情報サービス」によると、膵臓はがんが小さいうちは症状が出にくく、早期発見が簡単ではない臓器とされています。
理由としては、
- 体の深い場所にあって、自覚症状が出にくい
- 胃や腸など他の臓器の症状と区別しにくい
- 特有の「これ!」という初期症状が乏しい
といった点が挙げられます。
膵臓がんの「初期症状」と言われるサイン
代表的な症状(かなり進行してから出ることが多い)
膵臓がんがある程度大きくなると、次のような症状が出てくることがあります。
- みぞおちや上腹部の痛み
- 背中の痛み(とくに腰より少し上のあたり)
- 食欲がない、すぐにお腹いっぱいになる
- 体重がどんどん減っていく
- お腹がはる感じ(腹部膨満感)
- 黄疸(おうだん)
→ 目の白い部分や皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる など
ただし、これらは膵臓がんに限らず、胃炎や胆石、腰痛などでも起こる症状です。
逆にいうと、「この症状がある=膵臓がん」と決めつけることはできません。
「初期」に出ることがあるサイン
いわゆる初期症状と呼べそうなサインとして、次のようなものが知られています。
- 原因がはっきりしない糖尿病の発症・悪化
→ 今まで糖尿病でなかった人が急に糖尿病を指摘される
→ 長年安定していた血糖値が、急に悪くなってきた など - なんとなく続く上腹部の違和感
- はっきりした原因がないのに体重が減っていく
膵臓がんが原因でインスリンが出にくくなり、糖尿病として気づかれるケースもあります。
ただし、糖尿病の人がみんな膵臓がんになるわけではありませんし、体重減少にもいろいろな理由があります。「いつもと違う」「何かおかしい」が続くときは、一度医療機関で相談してみることが大切です。
「膵臓がんになりやすい人」の特徴(危険因子)
「Medical DOC」など医師監修メディアや、日本膵臓学会のガイドラインでは、膵臓がんの「危険因子(リスクファクター)」として、主に次のようなものが挙げられています。
家族歴・遺伝的な要因
- 近い家族(両親・兄弟姉妹・子ども)に膵臓がんになった人がいる
- 膵臓がんになりやすい「遺伝性の病気」がある家系
膵臓がん患者さんのうち、数%は家族にも膵臓がんの人がいるとされています。
第一度近親者に2人以上膵臓がんの方がいる場合、「家族性膵癌」として、リスクが高いと考えられます。
生活習慣に関する要因
- 喫煙(タバコ)
- 喫煙者は、非喫煙者に比べて膵臓がんのリスクが高まるとされています。
- 大量の飲酒
- 大量飲酒は慢性膵炎を起こし、それが膵臓がんのリスクになります。
- 肥満(BMIが高い)
- 肥満・過体重は、膵臓がんの危険性を高めると報告されています。
他の病気がもともとある場合
- 慢性膵炎
- 長いあいだ膵臓に炎症が続いている状態で、膵臓がんのリスクが4~8倍になるという報告もあります。
- 糖尿病
- 新しく糖尿病を発症したり、急に悪化するケースは、膵臓がんが背景にある可能性が指摘されています。
- 膵嚢胞(すいのうほう)やIPMNといった膵臓のしこり
- 「前がん病変」として、慎重な経過観察が勧められています。
まとめると…
なりやすい「傾向」はあっても、「この条件に当てはまる=必ず膵臓がん」ではありません。
ただし、
- 家族歴がある
- 喫煙・大量飲酒・肥満などの生活習慣が重なっている
- 慢性膵炎や膵嚢胞など、膵臓の病気がある
といった方は、一度消化器内科などで相談し、定期的なチェックを考える価値があるとされています。
膵臓がんはどうやって見つける?検査の流れ
膵臓がんは、いわゆる「人間ドックのオプション検査」などで見つかることもありますが、決定的な「簡単検査」は残念ながらまだありません。
画像検査
主に次のような検査が行われます。
- 腹部超音波検査(エコー)
- お腹にプローブを当てて内部をみる検査。
- ガスや脂肪などの影響で、膵臓は見えにくいこともあります。
- CT検査
- 造影剤を使ったCTで、膵臓や周囲の臓器を詳しく調べます。
- MRI/MRCP
- 胆管や膵管の様子を詳しく見ることができます。
- 内視鏡的超音波検査(EUS)
- 胃や十二指腸から内視鏡を入れて、先端の超音波で膵臓を詳しく観察します。
血液検査(腫瘍マーカー)
膵臓がんでは、CA19-9という腫瘍マーカーが上昇することがよく知られています。
- CA19-9が高い → 膵臓がんの可能性の一つの手がかり
- ただし、膵臓がんだけでなく、ほかのがん・肝臓病・胆石などでも上がることがある(偽陽性)
- 逆に、膵臓がんでもCA19-9が上がらない人もいる
そのため、CA19-9だけで**「確定」できる検査ではなく、画像検査などと組み合わせて総合的に判断**します。
「自分も膵臓がんかも?」と思ったときにどうする?
ニュースやSNSを見て不安になり、
「最近、なんとなくお腹が痛い気がする」
「体重が少し減ってきた…膵臓がんかもしれない」
と考えすぎてしまう方もいるかもしれません。
自己判断せず、まずは「相談」から
- 症状が数週間以上続く
- 「今までと明らかに違う」体調の変化がある
- 糖尿病が急に悪化したと言われた
- 家族に膵臓がんの人がいて不安
こうした場合は、かかりつけ医や内科、消化器内科で相談してみましょう。
「膵臓がんかどうかを見てもらいたい」と正直に伝えてOKです。
必要に応じて、
- 血液検査
- 腹部エコー
- 専門病院への紹介
など、次のステップを提案してもらえます。
「不安だけど、どこまで検査するべき?」
膵臓がんは確かに怖い病気ですが、不安だからといっていきなり高度な検査を全員が受けるべきとは限りません。
- 年齢や家族歴
- 生活習慣(喫煙・飲酒・肥満)
- これまでの病歴(糖尿病・慢性膵炎など)
- 今の症状の強さ・期間
こうしたものを合わせて、医師と相談しながら検査のレベルを決めていくことが大切です。
日常生活でできる「膵臓がん予防」につながる習慣
膵臓がんを完全に防ぐ方法は、今のところありません。それでも、「危険因子を減らす」ことでリスクを下げることはできると考えられています。
禁煙をする
- タバコは多くのがんのリスクを高め、その中に膵臓がんも含まれます。
- 禁煙は、がん予防の中でも効果がはっきりしている対策です。
飲酒量をおさえる
- 毎日多量のお酒を飲んでいる人は、まず「量をへらす」ことから。
- 可能であれば「休肝日」をつくり、週のうち何日かはお酒を飲まない日を意識してみましょう。
体重・血糖値を整える
- 肥満は膵臓がんだけでなく、糖尿病や心筋梗塞など多くの病気のリスクになります。
- 「急に痩せる」のは要注意ですが、「少し太りすぎかな…」という人は、
- 間食を減らす
- 一駅分歩く
- エレベーターを階段に変えてみる
など、無理のない範囲で生活を見直すだけでも違ってきます。
定期的な健康診断を受ける
- 血糖値、肝機能検査、腹部エコーなどは、膵臓がんだけでなく他の病気の早期発見にも役立ちます。
- 「異常なし」と言われても、その結果を蓄積していくこと自体が将来の比較データになります。
大切なのは「怖がりすぎず、現実的な一歩を」
膵臓がんは、
- 見つかりにくい
- 進行が速いことがある
- 手術も大きな負担になる
とても大変な病気です。
ニュースを見て落ち込んだり、不安になったりするのは当然のことだと思います。
でも、私たちにできることもあります。
- タバコをやめる・減らす
- お酒の量を見直す
- 体重や血糖値を管理する
- 家族歴や持病がある人は、早めに専門医に相談しておく
- 「何かおかしい」と感じたときは、早めに病院に行く
こうした小さな一歩の積み重ねが、自分や家族の健康を守ることにつながります。
まとめ
最後に、この記事のポイントを簡単にまとめます。
菅谷大介アナの訃報は、本当に悲しく、やりきれないニュースでした。
その一方で、私たちが「膵臓がん」を知るきっかけにもなりました。
不安な気持ちになったときこそ、
- 正しい情報を知る
- 自分にできる小さな行動を選ぶ
- 必要なら、医師に相談する
この3つを意識して、「怖いから目をそらす」のではなく、「知ることで守る」方向に、一緒に一歩ずつ進んでいけたらと思います。
もし今、あなた自身やご家族のことで心配なことがあるなら、この記事をきっかけに、身近な医療機関に相談してみてくださいね。