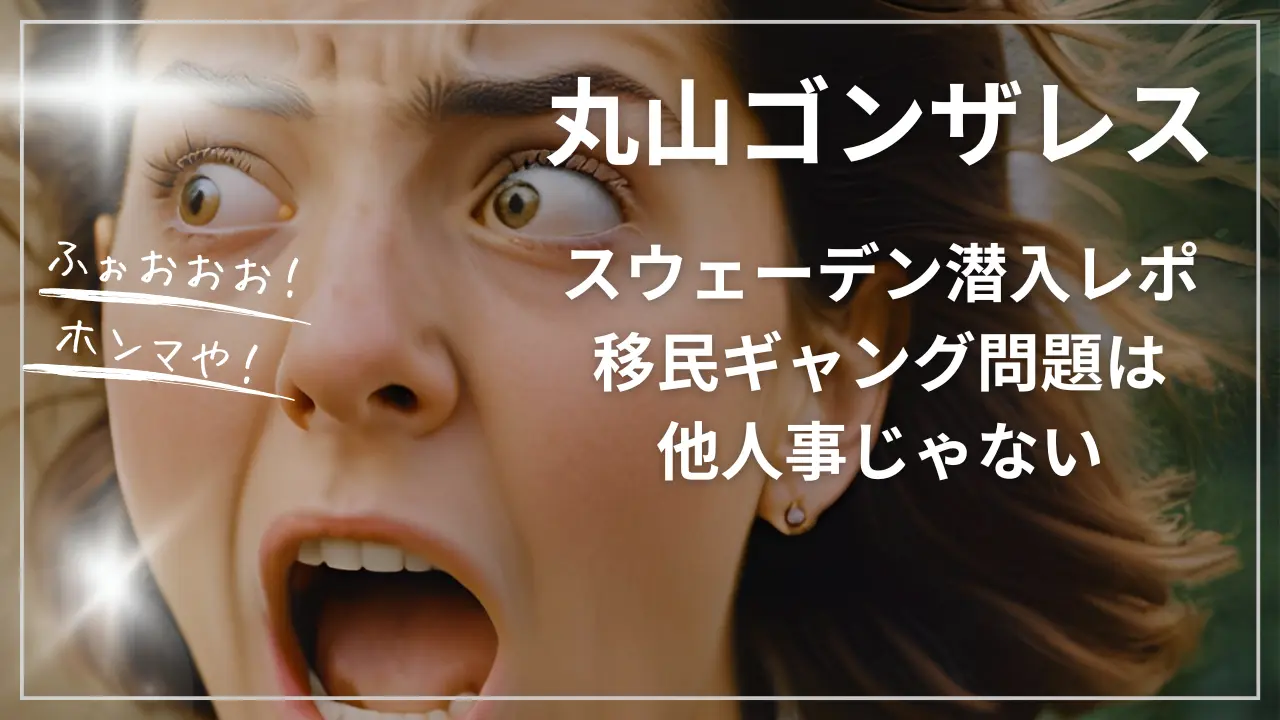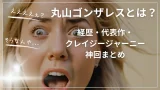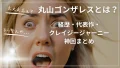丸山ゴンザレスさんが番組などで伝えてきた「スウェーデンの移民ギャング問題」は、遠い北欧の治安ニュースではありません。
じつは、私たち日本に住む人にとっても、「これからの社会で何が起きるか」を考えるヒントになるテーマです。
この記事では、
- 丸山ゴンザレスってどんな人?
- スウェーデンで実際に何が起きているのか(銃撃・爆発・ギャング抗争)
- なぜ移民の若者がギャングに流れてしまうのか
- スウェーデン政府の対策
- 日本で生きる私たちにとって「他人事ではない」理由
を整理していきます。
丸山ゴンザレスとは?「世界の裏側」を歩くジャーナリスト
まずは主人公から。
丸山ゴンザレスさんは、危険地帯や“裏社会”を自分の足で歩いて取材するジャーナリストです。
TBS系の人気番組「クレイジージャーニー」にたびたび出演し、紛争地帯やスラム街、犯罪の現場などをレポートしてきました。
- 普通の観光客は絶対に行かないエリアに入る
- 現地のギャングや元犯罪者にも直接話を聞く
- 危険すぎる場所は、きちんとリスクを説明する
こうしたスタイルで、「ニュースだけでは見えてこないリアル」を伝えるのがゴンザレスさんの特徴です。
そんな彼が注目した国のひとつが、北欧の福祉国家として知られていたスウェーデンです。
かつては「平和で豊かな北欧」だったスウェーデン
スウェーデンと聞くと、どんなイメージがありますか?
- 税金は高いけど、そのぶん福祉が充実している
- 教育や医療が手厚い
- 治安が良くて、平和な北欧の国
おそらく、多くの日本人がこんな印象を持っていると思います。
実際、少し前までのスウェーデンは、
- ヨーロッパでもトップクラスの福祉国家
- 難民や移民を積極的に受け入れる「寛容な国」
として知られていました。
しかしここ10〜20年ほどの間に、「ギャングによる銃撃・爆発事件がヨーロッパでも突出して多い国」へと変わってしまいます。
スウェーデンを揺さぶる「移民ギャング」の実態
銃撃・爆発事件が“日常ニュース”に
スウェーデンでは、ギャング同士の抗争による銃撃や爆発事件が急増しました。
- EUの中で、人口あたりの銃撃による死亡率が上位になっていること
- ギャングが爆発物を使った攻撃を日常的に行っていること
などが、国際的な報道や調査でも指摘されています。
たとえば、
- 自宅マンションがいきなり爆破される
- 住宅街で銃撃戦が起きる
- 近くの店や家が「間違い」で巻き込まれる
こうしたニュースが、スウェーデン国内で続いてきました。
2024年時点で、約6万2千人が犯罪ネットワークに関わっている、という推計もあります。
もちろん、スウェーデン全体が「危険で歩けない」という意味ではありません。
しかし、「特定の地域では、一般市民も巻き込まれるレベルの抗争が続いている」というのが現状です。
背景には「移民の若者」と「貧困・格差」
スウェーデンのギャングの多くは、移民や移民2世の若者が大きな割合を占める、と報じられています。
ここで大事なのは、
「移民=犯罪者」ではまったくない
という点です。
移民の人たちの多くは、まじめに働き、家族を支え、社会に溶け込もうとしています。
問題になっているのは、その一部の若者たちが、さまざまな理由でギャングに流れやすい状況にある、ということです。
よく言われる要因は、例えばこんなものです。
- 移民が多く住む地域が、貧困地域として固定化されてしまった
- 学校教育での遅れや中退が多く、就職が難しくなる
- 差別や偏見から、「自分はスウェーデン社会の一員ではない」と感じてしまう
- そんな中で、ギャングが「金・仲間・居場所」を与える存在として近づいてくる
つまり、「移民だから犯罪に走る」のではなく、
貧困・差別・教育格差・居場所のなさ
こうした要素が重なった結果、たまたま移民の若者が多く巻き込まれている
という構図です。
丸山ゴンザレスが見た「スウェーデンの現場」
テレビやネットニュースだけでは、こうした状況はなかなか実感しにくいものです。
そこでゴンザレスさんは、実際にスウェーデンの危険とされるエリアに足を運び、地元の人たちや関係者の声を拾いながら、その実態を伝えています。
一見すると「普通の住宅地」
多くのギャング抗争の現場は、映画に出てくるような“いかにも危険そうな路地”ばかりではなく、
- 普通のマンションが並ぶ住宅地
- 子どもも遊んでいる公園の近く
- スーパーや学校のそば
だったりします。
「きれいな北欧の街並み」と、「銃声・爆発」というイメージのギャップこそ、スウェーデンの問題を象徴していると言えるかもしれません。
真面目に暮らす移民たちの不安
現地で話を聞くと、移民としてスウェーデンへやってきた家族の多くは、
- 「子どもには安全な国で育ってほしい」
- 「戦争や迫害から逃れるために来たのに、今度はギャングの暴力におびえている」
といった複雑な気持ちを抱えています。
「一部のギャングのせいで、移民全体が悪く言われるのがつらい」という声も、多くの取材で聞かれます。
スウェーデン政府の動き:子どもを「使い捨て」にするギャングにどう対抗するか
年齢の低い実行犯が増えている
スウェーデンでは、ギャングが「14〜15歳以下の子ども」を実行犯として使うケースが増えていると報じられています。
理由はシンプルで、
- 刑事責任の年齢が高いと、子どもは重い刑罰を受けにくい
- その「法のスキ」を、ギャングが悪用している
からです。
これに対しスウェーデン政府は、
- 刑事責任年齢の引き下げ(現在15歳)を検討
- 少年犯罪への処罰を重くする方向
- 同時に、搾取されている子どもたちを守る仕組みづくり
といった方針を打ち出しています。
犯罪対策と、社会政策の「両方」が必要
一方で、警察や法律を強化するだけでは根本解決にはなりません。
- 貧困地域の改善
- 教育支援
- 差別や排除を減らす取り組み
- 若者が「ギャング以外の居場所」を見つけられる社会づくり
といった、長期的な社会政策も欠かせないとされています。
なぜ「他人事じゃない」のか? 日本とのつながり
ここまで読むと、
「いやいや、日本は銃も爆弾も少ないし、スウェーデンとは違うでしょ」
と思うかもしれません。
たしかに、日本でスウェーデンのような銃撃戦や爆発事件が日常的に起きているわけではありません。
ただし、「スウェーデンがたどった道」と「今の日本」が、じわじわと重なっている部分もあります。
① 貧困・格差・孤立する若者
日本でも、
- 非正規雇用が増え、将来に希望を持ちにくい若者
- 家庭環境が不安定で、居場所を失っている子ども
- 学校や社会で浮き、ネットの世界だけが頼りになっている人
が増えている、と言われています。
スウェーデンのギャング問題は、
「社会の中で取りこぼされた若者が、犯罪組織にすくい上げられるとどうなるか」
を、極端な形で見せているとも言えます。
日本も、若者の孤立を放置すれば、
- 犯罪
- カルト的な団体
- 過激なコミュニティや暴力的なネット集団
などに取り込まれるリスクは十分にあります。
② 外国人労働者・移民との共生
日本でも、コンビニや介護、工場、建設現場など、
外国人労働者なしでは回らない仕事が増えています。
これから少子高齢化が進めば、外国人に頼る場面はもっと増えるでしょう。
そのときに、
- 「外国人=安い労働力」としてだけ扱う
- 日本語教育や生活サポートをほとんどしない
- 差別や偏見を放置する
という状態が続けば、スウェーデンと同じように、
「社会から排除された外国人コミュニティ」と
「そこに入り込む犯罪組織」
というセットが生まれる可能性は、決してゼロではありません。
③ デマや偏見に流される危険
スウェーデンでも、
- ギャングによる事件が増える
- →「移民は危険だ」「追い出せ」という極端な意見が出てくる
- →社会の分断が広がる
という悪循環が問題視されています。
日本でも、SNSなどで偏った情報やデマが広がれば、
- 「外国人が増えると治安が悪くなる」
- 「○○国出身はヤバい」
といった短絡的なイメージが広がりかねません。
本当に必要なのは、「冷静なデータ・現場の声・背景事情」を知ったうえで考えること。
丸山ゴンザレスさんのように、「現場に近づこうとする姿勢」は、
情報があふれる今の時代ほど大事になっていると言えます。
私たちにできること:ニュースを「他人事」で終わらせない3つの視点
では、スウェーデンの話を聞いた日本の私たちは、何を考え、どう動けばいいのでしょうか。
ここでは、今からでも意識できる3つの視点を挙げてみます。
1.「誰かを悪者にして終わり」にしない
スウェーデンの例を見ると、
- 移民の若者がギャングに入るのは、本人の性格だけの問題ではない
- 社会の仕組みや、教育・貧困・差別などが複雑に絡んでいる
ことがわかります。
日本で問題が起きたときも、
- 「○○人だから」
- 「ゆとり世代だから」
- 「若者はこれだから」
のように、ラベル貼りで片づけるのではなく、
「なぜその人は、そこまで追い詰められたのか?」
「社会側に、どんな“ほころび”があったのか?」
と、一歩踏み込んで考えるクセをつけることが大切です。
2.「孤立している人」を放置しない
ギャングや過激な団体が狙うのは、たいてい
- 孤独
- 貧困
- 将来への絶望
を抱えている人たちです。
身近なところで、
- 明らかに元気をなくしている同僚
- 学校や職場になじめず、浮いてしまっている人
- 家庭の事情で大変そうな友人
に対して、
- ちょっと声をかける
- 話を聞く
- 専門家や支援窓口につなぐ
といった小さなアクションが、
“ギャングやおかしなコミュニティに持っていかれないための「防波堤」”になるかもしれません。
3.外国人と「一緒に生きる」準備をする
外国人を「お客さん」や「一時的な労働力」としてだけ見るのではなく、
「これから同じ社会で生きていく仲間」
として考えることが、長い目で見れば治安の安定にもつながります。
- 日常のあいさつを交わす
- 簡単な日本語を教えたり、逆に相手の文化を教えてもらう
- 会社や学校で、外国人だからといって不当な扱いをされていないか気づく
こうした小さな積み重ねが、
「移民コミュニティを丸ごとギャングに奪われる」ような事態を防ぐ土台になります。
まとめ
最後に、この記事のポイントを整理します。
丸山ゴンザレスさんのスウェーデン潜入レポは、
“遠い国の怖い話”ではなく、
「このままいくと、日本でも同じことが起きるかもしれないよ」
という、未来からの警告のようにも見えます。
ニュースやバラエティで彼の取材を目にしたら、
ただ「ヤバい」「怖い」で終わらせず、
- なぜそうなったのか
- 日本の自分の生活と、どこがつながっているのか
を、少しだけ立ち止まって考えてみてください。
それがきっと、「移民ギャング問題は他人事じゃない」というタイトルの、本当の意味になるはずです。