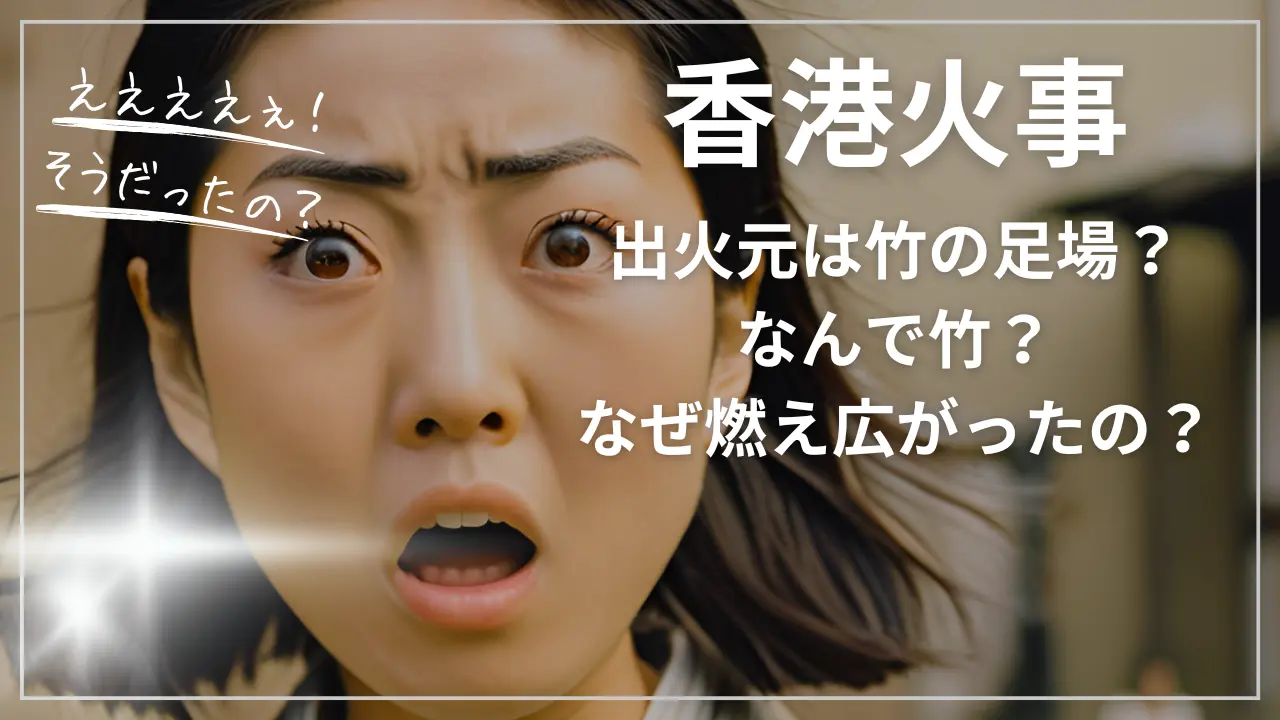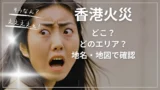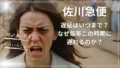ニュースで、香港の高層マンションが
ビルごと炎に包まれている映像を見た方も多いと思います。
- 炎に包まれているのは外側の竹の足場
- ビル全体が緑色のネットにくるまれている
- それが何棟もまとめて燃えている
という、まるで映画のような光景でした。
今回の香港・大埔(タイポ)地区の宏福苑(Wang Fuk Court)火災は、
少なくとも44人が死亡、50人以上がケガ、行方不明者も多数と伝えられており、
ここ数十年で最悪クラスの火災だと言われています。
そんな中で、世界的に注目されているのが
出火元は竹の足場なのか?
そもそも、なんで高層ビルに「竹」を使っているの?
どうしてここまで一気に燃え広がってしまったの?
という点です。
この記事では、大人向けの内容を
を、順番に整理していきます。
※数字や状況は、2025年11月27日時点の海外報道をもとにしています。
今後の調査で変わる可能性があることを前提に読んでください。
今回の火災はどこで何が起きたのか
高層団地「宏福苑」での大規模火災
火災が起きたのは、
- 場所:香港・新界(ニューテリトリーズ)地区の大埔(タイポ)区
- 団地名:宏福苑(Wang Fuk Court)
- 建物:31〜32階建ての高層マンションが8棟並ぶ巨大団地
- 戸数:約1,984戸
- 入居開始:1983年ごろから入居が始まった、築40年以上の大型団地
日本でいうと、
「郊外のニュータウンにある、30階建て級のマンションが
8棟ドーンと並んでいる巨大団地」
というイメージに近いです。
ここで、外壁の大規模修繕工事が行われていました。
そのため、団地の多くの棟の外側が、
- 竹で組んだ足場
- 緑色の防護ネット
で、すっぽり覆われていました。
その状態で火が出てしまい、
竹の足場とネットを伝って炎が一気に広がったとみられています。
死傷者と被害の大きさ
報道によると、
- 死亡:44人以上
- 負傷:50人以上
- 行方不明:200人以上(報道によって数字に差あり)
とされ、香港当局は火災警報レベルの最高「5級」を発令しました。
香港では1996年に九龍の商業ビルで41人が亡くなる火災がありましたが、
それを上回る、数十年ぶり最悪の大火災と評価されています。
「竹の足場」ってそもそも何?
香港では“当たり前”の工事風景
日本ではビルの足場というと、
- 鉄のパイプ足場
- アルミの足場
をイメージしますよね。
ところが香港では、今でも
ビルの外側に、竹を組んだ足場を組む
という伝統的な工法が広く使われています。
高層ビルの外壁が、
- 細い竹が格子状に組まれ
- その上に緑色のネットが張られている
という光景は、香港の“名物”のような存在でした。
なぜ竹を使うのか?4つの理由
では、どうしてわざわざ竹なのでしょうか。
主な理由は次の4つです。
- 軽くて強い(わりに安い)
- 竹は軽いのにしなやかで強く、適切に組めば高い耐荷重を持ちます。
- 運びやすく、設置・解体も早いと言われています。
- ビルの形に合わせやすい
- 竹は長さを自由に切ったり、少し曲げたりできるため、
複雑な形のビルにも柔軟に対応できます。
- 竹は長さを自由に切ったり、少し曲げたりできるため、
- コストが安い
- 鉄パイプより材料費が安く、
熟練職人も多いため、工期を短くしやすいという面があります。
- 鉄パイプより材料費が安く、
- 長年の“職人文化”がある
- 何十年も続いてきた工法であり、
「竹足場師」と呼ばれる熟練職人の世界もあります。
- 何十年も続いてきた工法であり、
実際、香港政府が竹足場を減らそうと動き出すと、
竹足場職人の労組が「文化と仕事が失われる」と反発するなど、
ただの工法以上に「伝統」「文化」の側面も大きいのです。
出火元は本当に「竹の足場」なの?
原因はまだ「調査中」
まず大事な前提として、
「どこから出火したのか」の正式な結論は、
この記事執筆時点ではまだ出ていません。
香港警察は、工事関係者3人を過失致死などの疑いで逮捕しており、
捜査を進めている段階です。
有力視されている「外側からの出火」
ただし、複数の報道を総合すると、
- 火は「建物の外側」から発生した
- 竹の足場や、外壁のネット付近が最初に燃えたとみられている
という点は、かなり共通しています。
香港メディアや専門家のコメントでは、
- 工事作業員の喫煙や
- 溶接・研磨作業の火花
- 電気設備のトラブル
といった可能性が取り沙汰されていますが、
あくまで「可能性の議論」の段階であり、
公式な「これが原因だ」という結論はまだ出ていません。
それでも「竹の足場」が疑われる理由
原因そのものは調査中ですが、
世界中のニュースが一斉に、
「竹の足場が火の広がりを加速させたのでは?」
と報じているのには、いくつか理由があります。
- 映像を見ると、まず竹の足場とネットが巨大な“炎の壁”になっている
- 少し遅れて、ビル内部の部屋にも火が入っているように見える
- いくつもの棟の竹足場がつながり、“炎の橋”のようになっていた
こうした状況から、
「最初の着火は外側(足場付近)で、
そこから団地全体に火が回ったのではないか」
とみられているわけです。
なぜ竹とネットで、ここまで一気に燃え広がったのか
ここからが、この記事のメインテーマです。
① 竹は「燃えない」わけではない
竹は生えているときは青々としていますが、
乾燥すると、れっきとした「可燃物」です。
もちろん、足場に使う竹は、ある程度太く・水分もありますが、
- 乾燥していれば表面から着火しやすい
- 油分や糖分なども含まれているため、
一度燃え始めると勢いがつきやすい
という特徴があります。
特に、
- 長時間の直射日光
- 高温多湿の気候
- 長期間組みっぱなし
といった条件が重なると、
防火性能はさらに低下していきます。
② 竹の足場は「巨大な角材の集合体」
竹の足場は、ビルをぐるっと包むように組まれています。
- 縦・横・斜めに、竹の棒がびっしり
- 結束用の結び目(ひも)が無数にある
- その外側をネットが覆っている
これをイメージで言うと、
「ビルの周りに、木材のやぐらを
何十メートルの高さで組んでいる」
のに近い状態です。
ひとたび火がつけば、
- 縦方向にも横方向にも炎が走りやすい
- 風が吹くと、炎がネット内で煽られる
- 焦げ落ちた竹やネットのかけらが“火の雨”のように下へ落ちる
という、非常に危険な構造になってしまいます。
③ 緑色のネット(メッシュシート)も“燃料”になった可能性
外側に張られている緑色のネットは、
- 作業員の転落防止
- 工事中の落下物を防ぐ
- ほこりやゴミが飛び散るのを防ぐ
といった目的で使われます。
ところが香港メディアの報道では、
- 使用されていたネットの“防炎性能が不十分だった可能性”
- 安価な素材で、火に弱かったのではないか
という指摘が出ています。
つまり、
「竹の骨組み+燃えやすいネット」
がビルを丸ごと包んでいた状態
で火が出たため、
ネットごと炎が走り、あっという間に上と横へ広がったと考えられます。
④ “煙突効果”と“トンネル効果”
高層ビルの外側を足場とネットで囲むと、
- 外壁とネットのあいだに
狭い“すき間の空間”ができます。
ここに火が入ると、
- 下で温められた空気が上へ一気に上昇(煙突効果)
- 上昇気流に乗って炎もどんどん上へ
- 風が吹くと、横方向へも炎が伸びる(トンネル効果)
という現象が起き、火の勢いが極端に強くなります。
今回の火災でも、
- 一部の棟の竹足場が崩れ落ちた
- その破片が、隣の棟の足場にぶつかって火を移した
といった証言や報道が出ています。
なぜ「竹の足場」は問題視されていたのに、まだ使われていたのか?
実は、すでに「減らしていこう」という方針は出ていた
香港政府は、2025年3月の時点で、
- 公共工事の少なくとも50%を、竹足場から鋼製足場へ切り替える
- 竹足場の使用を段階的に縮小していく
という方針を打ち出していました。
理由として挙げられていたのは、
- 竹足場に関する重大事故が相次いでいたこと(2018年以降で23人死亡とされる)
- 強風や台風時に竹足場が倒壊するリスク
- 火災時の安全性への不安
などです。
職人側の「仕事」と「伝統」の問題
一方で、竹足場を組む職人たちは、
- 仕事がなくなる
- 伝統の技術が失われる
- 若い世代に技を継承しにくくなる
といった理由から強く反対していました。
つまり、香港社会ではすでに数年前から、
「安全性を重視して鉄に切り替えるべき」
vs
「コストと伝統を守るべき」
という綱引きが続いていたところに、
今回のような最悪の形の大火災が起きてしまった、
という流れになります。
日本の感覚から見るとどうなのか?
日本の読者からすると、
「え、高層マンションの外側に“竹製のやぐら”を組んで、
しかも何棟もつなげるの?」
と、かなり衝撃的に感じるかもしれません。
日本では、
- 建築基準法や消防法で、
外壁の材料・防火構造に厳しい規定がある - 仮設足場やシートも、防炎性のあるものが普及している
- 高層ビルでの外壁工事は、
かなり細かい安全計画が求められる
といった事情から、
「高層ビルを竹と燃えやすいネットで丸ごと包む」
という発想自体が、あまり一般的ではありません。
もちろん、日本でも工事用シートが燃えたり、
足場からの火災が問題になるケースはゼロではありません。
ただ、今回の香港のように、
- 複数棟の高層ビルがまとめて炎に包まれる
というレベルの事例は、かなり例外的です。
これから香港はどう変わっていくのか
竹足場は一気に“悪者”になるのか?
今回の火災をきっかけに、
世界中のメディアが「竹足場の危険性」に注目しています。
- 「竹足場が炎の通り道になった」
- 「竹+ネットが巨大な燃料になった」
といった指摘は、たしかに一理あります。
一方で、
- 実際の出火原因はまだ調査中
- 足場以外にも、外壁材や配線、工事の管理体制など
いくつもの要因が絡んでいる可能性が高い
という点も忘れてはいけません。
おそらく起きるであろう変化
とはいえ、ここまで大きな犠牲者が出てしまった以上、
香港社会が何も変わらない…ということは考えづらいでしょう。
今後、次のような流れが強まると予想されます。
- 公共工事から竹足場を急速に減らす
- 既存の「50%を鋼製に」の方針が、
さらに厳しくなる可能性があります。
- 既存の「50%を鋼製に」の方針が、
- 民間工事にも規制が広がる
- 公営住宅や大規模マンションなどで、
竹足場の使用制限が強化されるかもしれません。
- 公営住宅や大規模マンションなどで、
- 防炎ネットの義務付け・検査の強化
- 「とりあえず安いネットを張っておけばOK」
という状態から、素材・防炎性能のチェックが厳格化されるでしょう。
- 「とりあえず安いネットを張っておけばOK」
- 足場と建物との距離・区画の見直し
- 一気に燃え広がらないよう、
足場を区切る仕組みや、避難のための開口部などが
新たに設けられる可能性もあります。
- 一気に燃え広がらないよう、
私たちがこのニュースから学べること
「当たり前」は、他の国では当たり前じゃない
香港の人にとっては、
- 「ビルに竹の足場が組まれている」
- 「緑のネットで覆われている」
という光景は、ごく普通のものです。
ところが、世界の多くの国から見ると、
「そんな高層ビルまで竹を組むの!?」
「あれ、火事のとき大丈夫なの?」
と、かなり異様に見えます。
今回の火災は、
「その国の“当たり前”が、
実は大きなリスクになっていることもある」
ということを、強烈に見せつけた事件だとも言えます。
テクノロジーより「古い習慣」がボトルネックになることも
- 高層ビル
- 高度な消防システム
- 最新の救急医療
など、現代の都市は多くのテクノロジーで守られています。
しかし、
- 「昔からこうやってきたから」
- 「コストが安いから」
- 「この街らしさだから」
といった理由で残っている古い習慣が、
一気に安全を壊してしまうこともあります。
竹の足場自体が100%悪い、と決めつけることはできませんが、
今回の火災をきっかけに、
「何を守り、何を変えるべきか」
を、香港社会は厳しく問われることになるはずです。
まとめ:出火元はまだ調査中
最後に、この記事のポイントを整理します。