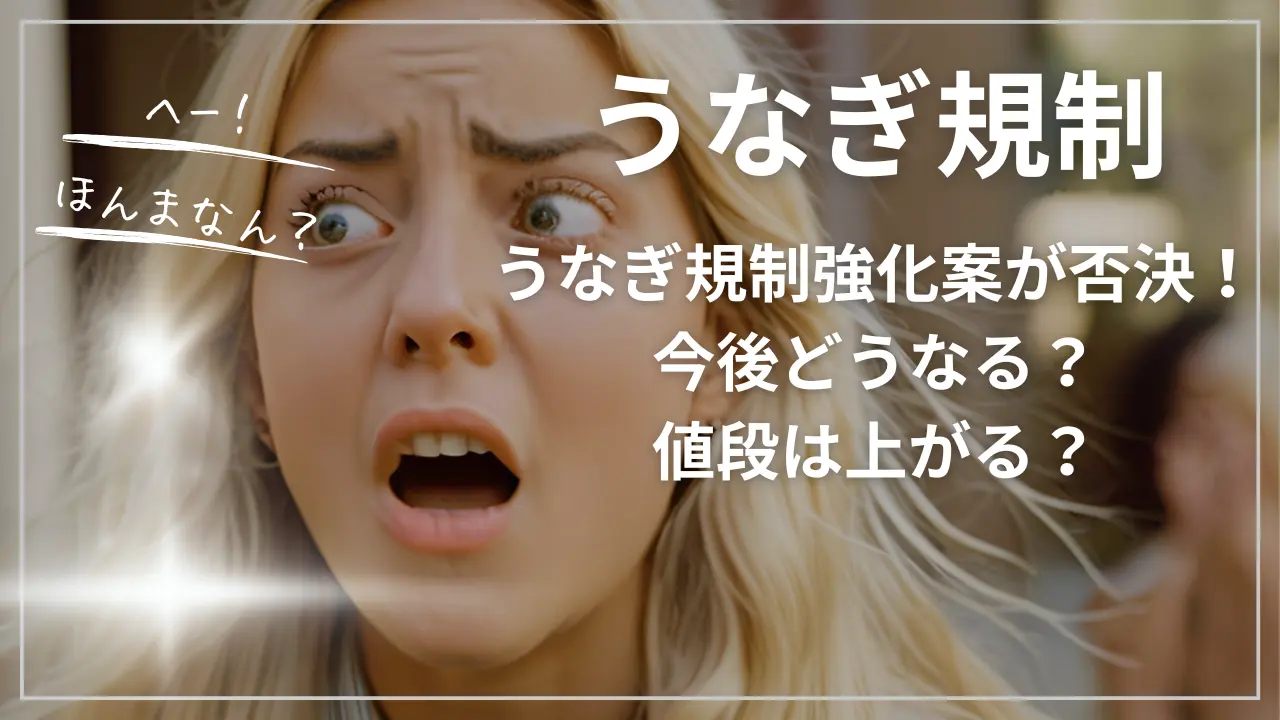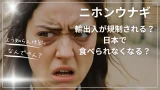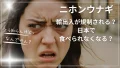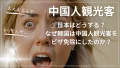「ニホンウナギを含む“ウナギ全種類”を国際取引の規制対象にする案が出ていたけど、否決されたらしい」
そんなニュースを見て、
- じゃあもう安心ってこと?
- 今後もまた規制の話が出てくるの?
- うなぎの値段って、これからどうなるの?
- そもそも“ワシントン条約”って何?
と、モヤモヤしている人も多いと思います。
この記事では、
- 今回“否決”された「うなぎ規制強化案」とは何だったのか
- 規制案が否決された「今後のシナリオ」
- うなぎの値段は本当に上がるのか
- そもそもワシントン条約とは何か
を、順番に整理していきます。
まずはざっくり結論から
結論①:「完全に安心」ではないけれど、とりあえず一息つける状況
2025年11月27日、ウズベキスタンのサマルカンドで開かれている
ワシントン条約(CITES)第20回締約国会議(CoP20)の委員会で、
「ニホンウナギを含むウナギ全種類を
国際取引の規制対象(附属書Ⅱ)にする」
というEUとパナマの提案が、
賛成35、反対100、棄権8の大差で“否決”されました。
日本はこの案に強く反対し、アジアの国々などと一緒に「否決」の流れを主導しました。
結論②:12月5日に“再投票”の可能性あり → まだ完全決着ではない
ただし、これで完全に終わりではありません。
- 12月5日の本会議(全体会合)で、
- 参加国の3分の1以上が求めれば、
再投票(再度の採決)が行われる可能性があるとされています。
多くのメディアは「このまま最終的にも否決になる可能性が高い」と見ていますが、
“絶対にない”とはまだ言い切れない、というのが正直なところです。
結論③:今すぐスーパーからうなぎが消えるわけではないが…
現時点では、
- スーパーのうなぎが明日からいきなり消える
- うな丼・ひつまぶしが即“幻のメニュー”になる
といった極端な状況ではありません。
ただし、
- もし将来、同じような規制案が採択された場合
- あるいは、資源そのものが回復しないまま減り続けた場合
には、値段が大きく上がる、あるいは本当に食べにくくなる未来も、十分あり得ます。
何が否決されたの?今回の「うなぎ規制強化案」をざっくり解説
提案の中身:ウナギ全種類をワシントン条約「附属書Ⅱ」に
今回の提案は、ざっくり言うとこうです。
「すべての“ウナギの仲間”(Anguilla属のウナギ類)を、
ワシントン条約の附属書Ⅱに載せよう」
- 提案国:EU(ヨーロッパ連合)+パナマ
- 対象:ヨーロッパウナギ、ニホンウナギ、アメリカウナギなど、
Anguilla属に属するすべてのウナギ類
附属書Ⅱというのは、
「国際取引の影響で“絶滅の危険”が高まっている、
もしくは将来その危険が高まるおそれがある種類」
が入るリストで、
「完全禁止」ではないけれど、輸出入に厳しいルールがかかるグループです。
もし採択されていたら、何が変わった?
附属書Ⅱに入ると、主にこんな変化が起きます。
- ウナギを国境をまたいで輸出入するときに「輸出許可証」が必要になる
- 「この取引は資源に悪影響を与えない」と、
輸出国の政府が科学的に判断してOKを出さないといけない - 曖昧なルート・違法な取引はかなりやりにくくなる
つまり、ざっくり言うと、
これまで“自由に近かった貿易”に、
きびしい関所と書類チェックがつく
イメージです。
その結果、手続きコストが増えて、ウナギそのものの価格が上がる可能性が高いと指摘されていました。
ワシントン条約(CITES)ってそもそも何?
ここで一度、「ワシントン条約って何なの?」を整理しておきましょう。
ワシントン条約の基本
ワシントン条約(CITES)は、
絶滅のおそれがある野生動植物を守るために、
国際取引(輸出入)をルールでコントロールしよう
という国際条約です。
ポイントは3つ。
- 「取引」に注目している条約
→ 「食べてはいけない」「使ってはいけない」というより、
“国境をまたぐ売り買い”にルールをかける条約です。 - 3つの“附属書”で保護レベルを分けている
- 附属書Ⅰ:原則、国際商業取引はほぼ禁止レベル
- 附属書Ⅱ:ちゃんと管理すれば取引OKだけど、許可証などが必要
- 附属書Ⅲ:特定の国が「うちの国のこの種を守りたい」と申し出たもの
- 2〜3年に一度、「締約国会議(CoP)」で見直す
→ 今回のCoP20がそれにあたります。
「規制される=すぐ食べちゃダメ」ではない
誤解しやすいポイントですが、
ワシントン条約で“規制対象にする”=
すぐに食べられなくなる・国内販売が禁止される
ではありません。
- 国内で養殖した分を国内で消費するのは、
基本的には各国のルールに任されています。 - ただし、国際取引が厳しくなると、
その影響で国内価格や流通の形が変わることは十分あり得ます。
今回のウナギの議論も、まさにここが焦点になっています。
なぜEUは「ウナギ全種の規制」を求めたのか?
EUなどが今回の提案を出した背景には、
「世界中のウナギ資源がかなり危ない状態にある」
という危機感があります。
ウナギは世界どこでも“減り続けている”
- ヨーロッパウナギは、すでにワシントン条約の附属書Ⅱに入っていて、
国際取引はかなり制限されている状態です。 - ニホンウナギやアメリカウナギも、
国際自然保護連合(IUCN)の「レッドリスト」で
絶滅のおそれがある種類とされています。
ウナギの一生は、
- 海の遠く離れた場所で生まれ
- 何千キロも回遊し
- 川や湖で大きくなり
- また海へ戻って一度だけ産卵して死ぬ
という、とても複雑でデリケートなものです。
その途中で、
- ダム・護岸工事・河川改修
- 水質汚染、海水温の変化
- 過去の乱獲・違法取引
などの影響をまとめて受け、世界的に数が減っていると心配されています。
「特定の国だけゆるいルール」は危険
EU側が特に問題視しているのは、
「ある地域では厳しく規制しているのに、
別の地域ではゆるいルールのままだと、
違法な取引や“抜け道”ができてしまう」
という点です。
ヨーロッパウナギはすでに附属書Ⅱですが、
ニホンウナギやアメリカウナギはまだリスト外。
その結果、
- 表向きは別種のウナギとして取引されているけど、
実はヨーロッパウナギが混ざっている - どの種がどれだけ捕られているのか、
正確に追いきれない
といった問題が起きている可能性があり、
「もう、全部まとめて附属書Ⅱに入れて、世界で足並みをそろえよう」
というのが今回の提案の狙いでした。
日本はなぜ強く反対したのか?
一方、日本はこの案に強く反対し、
最終的に委員会での否決を主導しました。
その理由は、大きく3つに整理できます。
理由①:日本はある程度、資源管理をしているという立場
日本政府は、
- シラスウナギ(稚魚)の漁獲量制限
- 養殖のトレーサビリティ(追跡管理)
- 親ウナギの放流事業 などを行っており、
「資源管理はちゃんとやっている。
国際取引が“絶滅の主な原因”だとは言えない」
という立場です。
理由②:経済への影響が大きすぎる
日本で食べられているうなぎの多くは、
中国や台湾などからの輸入品です。
- 附属書Ⅱ入りすると、輸出国側で許可証の発行や管理の手間が増える
- そのコストは、最終的に価格へ上乗せされる
- とくに安価なうな丼やスーパーのうなぎが大きく値上がりするおそれ
これに対して日本は、
「まだ科学的な不確実性も大きいのに、
一律で世界中のウナギを附属書Ⅱに入れるのは、
経済的なダメージが大きすぎる」
と主張してきました。
理由③:食文化の問題
日本にとって、うなぎは
- 土用の丑の日
- うな重・ひつまぶし
- 地方ごとの老舗のうなぎ屋
など、食文化としての重みもあります。
完全に規制されるわけではないとはいえ、
手軽に食べられなくなる → 食文化がしぼむ
という不安も、反対の背景にあります。
委員会で否決されたけれど、今後どうなる?
では、今回「否決された」ことで、
この先の流れはどうなるのでしょうか。
ステップ①:12月5日の本会議で“再投票”の可能性
- ワシントン条約の会議は、
委員会 → 本会議(全体会合)という流れになっています。 - 通常は、委員会の結論が本会議でもそのまま承認されることが多いですが、
参加国の3分の1以上が求めれば“再投票”ができるルールがあります。
FNNなどの報道でも、
「委員会で否決されたが、
12月5日の本会議で再投票が行われ、
可決される可能性もある」
と伝えています。
ただし、今回の票差(賛成35・反対100)はかなり大きいので、
現実的には“このまま提案見送り”の可能性が高いと見られています。
ステップ②:次回以降の会議に向けた“再提案”の動き
仮に今回の提案が最終的に見送られたとしても、
ウナギ資源の問題が消えるわけではありません。
- EUなどの提案国が、内容を少し変えた新しい案を準備する
- アジア各国に「もっと資源管理を強化して」と圧力をかける
- 科学者たちが、より詳しいデータを集めて次回提案の材料にする
といった流れが予想されています。
ステップ③:日本・東アジアの「資源管理」はより厳しく問われる
今回、日本は“反対側”に回りました。
世界からは、
「反対するなら、その分ちゃんと自分で資源を守ってね」
という目で見られることになります。
実際、日本国内でも、
- シラスウナギの漁獲ルールはこれで本当に十分か?
- 養殖で使う稚魚の出どころは、完全に追跡できているか?
- 親ウナギの放流など、資源回復の取り組みは十分か?
といった点が、今後さらに厳しくチェックされていくでしょう。
気になる「うなぎの値段」はどうなる?
多くの人が一番気にしているポイントがここだと思います。
今後、うなぎの値段は上がるの?下がるの?
正直に言うと、「確実な未来」は誰にもわかりません。
ただ、いくつかのシナリオを考えることはできます。
シナリオ①:今回の規制案が完全に流れて、しばらくは現状維持
もし、
- 本会議でも再投票が行われず、そのまま否決確定
- 次回の会議まで大きな新提案も出ない
という流れになれば、短期的には大きな値上げ要因は少ないかもしれません。
もちろん、
- 円安・輸送コスト
- シラスウナギの豊漁・不漁
など、別の要因で上下はしますが、
「ワシントン条約のせいで一気に高騰」という事態は避けられます。
シナリオ②:将来、条件を変えた規制案が採択される
例えば、将来の会議で、
- 一部のウナギ種だけ附属書Ⅱに入れる
- あるいは、猶予期間付き・条件付きで規制を強める
といった妥協案が採択される可能性もあります。
この場合、
- 輸出入に必要な書類・検査のコストアップ
- それによるじわじわとした価格上昇
が考えられます。
シナリオ③:資源悪化で“自然と”高級食材化していく
もう一つ忘れてはいけないのが、
「条約で規制されなくても、
そもそもウナギ資源が減り続ければ、
それだけで高級食材になっていく」
というシナリオです。
- シラスウナギがあまり獲れない
- 養殖に回せる量が減る
- その分、一匹あたりの単価が上がる
という流れは、すでにここ十数年、現実に起きてきました。
つまり、ワシントン条約の議論とは別に、
資源悪化による値上げリスクはずっと続いているということです。
「守りながら食べる」ために必要なこと
「値段が上がるのは嫌だけど、
資源が減って本当に食べられなくなるのはもっと嫌」というのが、
多くの人の本音ではないでしょうか。
「守りながら食べる」を実現するには、
どんな条件が必要なのでしょうか。
① シラスウナギの漁獲ルールを科学的に
- いつ・どこで・どれだけ取っているか、
データをさらに細かく集める - それをもとに「ここまでなら取っても大丈夫」という
科学的な上限(クォータ)を守る
② 養殖の“見える化”を徹底
- どこの国・どの川で捕った稚魚なのか
- どのルートで養殖場に運ばれたのか
を、書類とデータで追えるようにすることは、日本だけでなく世界共通の課題です。
③ 完全養殖の実用化
日本ではすでに、ニホンウナギの「完全養殖」(卵から卵まで)の技術は研究段階で成功していますが、
まだコストが高く、商業レベルには遠いと言われています。
しかし、もしこれが本格的に実用化できれば、
「自然の資源を過度に減らさずに、
うなぎを安定して供給する」
という未来にぐっと近づきます。
私たち消費者にできる小さなアクション
最後に、「国の政策」とか「国際会議」とか、
自分から遠く感じられる話の中で、
私たち一人ひとりにできることも少しだけ考えてみます。
① 安さだけで飛びつかない
- あまりにも安い“謎うなぎ”を見たときは、
一度立ち止まって「この値段で大丈夫なのかな?」と考えてみる - 多少高くても、信頼できる店・ブランドを選ぶことが、
結果的に資源を守ることにもつながります。
② 「たまのごちそう」として大切に食べる
- 昔の日本では、うなぎは“年に数回のごちそう”でした。
- 毎週食べる日常食ではなく、
「ここぞ」という日にじっくり味わうスタイルに戻す、という選択肢もあります。
③ 情報に関心を持ち続ける
- 「規制反対!」か「規制賛成!」かの二択だけで終わらず、
その裏にある資源の状況や世界の議論にも少し目を向ける - そうした関心の積み重ねが、
長い目で見れば、政策や企業の行動を変えていきます。
まとめ
この記事のポイントを最後にもう一度整理します。
つまり、
「うなぎ規制強化案が否決された=やったー、これでもう安心!」
ではなく、
「いったん時間は稼げたけれど、
これからどう資源を守って、
食文化を残していくかが本番」
だと考えるのが、いちばん現実的です。
土用の丑の日にうな丼を前にしたとき、
「高くなったなあ」とため息をつくだけでなく、
「この一杯を、10年後・20年後の子どもたちにも残すには、
どんな選択をしていけばいいんだろう?」
と、ほんの少しだけでも考えてみる。
その小さな意識の変化こそが、
「うなぎを守りながら、おいしく食べ続ける未来」への
第一歩なのかもしれません。