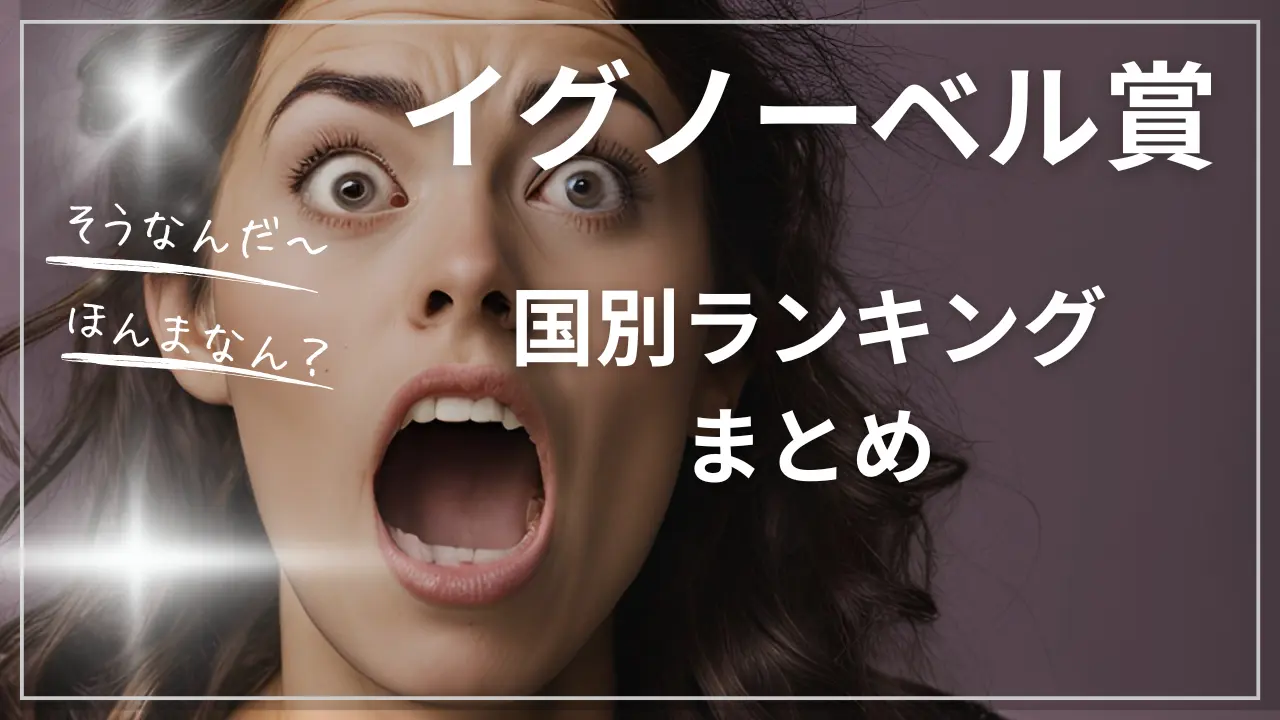最新の公的データと一次情報をもとに、国別の「イグノーベル賞」ランキングと、その読み解き方を“わかりやすく、丁寧に”まとめました。
数え方(「誰の国籍でカウントするか」「共同受賞の扱い」など)で順位が入れ替わる可能性があるため、本文ではデータの出所と集計ルールをきちんと明記し、長期傾向と直近トレンドの両面から整理しています。
はじめに:そもそも“何を数える”のか——集計ルールで結果は変わる
イグノーベル賞は1991年に創設され、毎年10件前後の受賞が発表されます。
受賞は単独研究者のときもあれば、複数国の研究チームのときもあり、さらに組織(政府・自治体・企業)が対象になる年もあります。
そのため「国別ランキング」を作る際には、最低でも次のどれで数えるかを決める必要があります。
- 受賞者一覧の先頭に記された人物(first named recipient)の所属国で数える
- 受賞に名を連ねたすべての国を均等にカウントする(分配計上 or 重複計上)
- 受賞者の国籍で数えるのか、所属機関(受賞当時)の所在国で数えるのか
本稿の「長期ランキング」では、米ジョージア工科大学のテクノロジー・ポリシー評価センター(TPAC)が行った網羅的なビブリオメトリック分析をベースにします。
彼らは1992〜2015年の253件・595名の受賞データから、先頭に記された受賞者の所属国を軸に各国のシェアを算出しています(のちに2016年まで更新予定と明記)。
この方法は「どの国の研究主導だったか」を見やすいのが長所です。集計の骨子と国別シェア(米英日が上位)は同センターの公開ページで確認できます。
一方、直近年の“勢い”は、主催者(Annals of Improbable Research)の公式「Past Ig Winners」ページで、各年の受賞リストと受賞国表記をもとに俯瞰します。
最新(2025年)も含め各賞に国名タグが付いており、多国間受賞の広がりや日本の連続受賞といった近年の特徴を把握できます。
さらに、日本の連続受賞年数については、日本語の一次レポート(nippon.com ほか)や国内主要メディアの解説を用いて年次の正確性を補強します。
長期累計ランキング(1992–2015、first-named方式・TPAC分析に基づく)
結論から:上位3カ国はアメリカ、イギリス、日本。TPACの集計では、先頭受賞者の所属国ベースで以下のシェアが示されています。
- アメリカ … 約32〜34%(受賞者全体ベースでは34%、first-namedでも最大)
- イギリス … 約12〜14%
- 日本 … 約11〜12%
TPACは「受賞者全体の国別内訳(US 34%、UK 14%、日本 12%)」および「first-named受賞者の国別シェア(US 32%、UK 12%、日本 11%)」を報告。期間は1992〜2015年(2016年にかけ更新方針)。
なぜこの3強?
- アメリカは研究人口・研究費・分野の広がりが圧倒的。イグノーベル賞は「笑って、考えさせる」研究を称える賞で、学術誌に載る“本気の研究”が母数として重要です。米国の論文生産力が直結します。
- イギリスは科学コミュニケーションや“科学ユーモア”の文化が強く、社会・人文含む幅広い題材で存在感。
- 日本は日常の不思議を科学で解くタイプの研究が豊富で、継続的な応募・選考の可視性が高い。のちの章で触れる“連続受賞”が長期的な厚みを生みました。
参考:イグノーベルのフィールド分布
1991〜2015で自然科学38%、医療・健康20%、社会科学16%、人文11%、平和20%、工学18%(重複あり、TPAC区分)。医療系の比率が近年上昇という指摘も。
上位3位以降は“拮抗のグループ戦”
TPACのページは上位3か国を明示する一方で、全順位リストは公開されていません。
ただし本文から「55カ国が受賞に関与」し、欧州とアメリカ大陸で大半を占めること、そしてオランダ、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、オーストラリアなどが継続的に名を連ねていることが読み取れます。
国の科学規模や英語圏の論文文化が与える影響は小さくありません。
注意点:国別ランキングはカウント法で順位が動く
例:すべての共著国に1ポイントを与える方法だと、多国籍チームの多い欧州が上方修正されやすい。一方、first-named方式は主導国の寄与を強調します。どちらも合理性があり、目的に応じた使い分けが必要です。
2020年代の「直近トレンド」:多国籍化の加速と“日本の粘り”
最新(2025年)の受賞国ミックス
公式「Past Ig Winners」では各賞に受賞国のタグが並びます。2025年も複数国の連名が多数。
たとえば心理学賞はポーランド・オーストラリア・カナダ、栄養学賞はナイジェリア・トーゴ・イタリア・フランスの連名。
生物学賞は日本の研究チーム(牛にシマウマ風の縞を描くと吸血性のハエが減るという実験)が受賞し、日本の連続受賞は19年へ。
この多国籍化は、
- 国際共同研究の一般化
- 研究資源(データ・動物・野外フィールド)や分析ツールの国境横断的利用
- イグノーベルの題材の広がり(自然科学×社会、工学×日常生活 などの越境)
を背景にしています。実際、主催者公式ページの各年一覧を眺めると、国タグが2〜4カ国にまたがる受賞が珍しくなく、アフリカやアジアの国名も年々増えています。
日本の“強さ”はなぜ続くのか
- テーマ選定の巧さ:身近な謎(ワサビ目覚まし、猫×牛×紙袋、コイン表裏の偏り、肛門呼吸など)をまじめに検証する伝統がある。
- 論文化・国際発信:イグノーベルは実在の学術成果を評価する賞。日本勢は英語論文での発信が安定しており、審査側の可視性が高い。
- 文化的土壌:ユーモアと実験精神が同居する“理科ノリ”。主催者への取材でも「なぜ日本は多いのか」がしばしば話題になり、長年の“常連”を裏づけています。
- 事実としての連続受賞:2007年から18年連続(2024年)、2025年で19年連続に到達。国内メディアも年次で確認・報道しています。
「最新ランキング」をどう見るか:2枚看板で使い分け
- 長期の“地力”を見るなら
→ TPACのfirst-named方式(1992–2015)を基準に、米・英・日=3強を押さえる。これは研究主導国のパターンを読むのに向きます。 - 足元の“勢い”を見るなら
→ 主催者公式の年次リストで、各年の受賞国タグを合算。多国籍チームが増えているので、
参考:上位3カ国の“らしさ”を示す代表的トピック
- アメリカ
- 分野の裾野が圧倒的。医学・公衆衛生や心理系から工学まで“何でも来い”の総合力。論文主導の賞で強いのは必然。
- イギリス
- 科学ユーモアの伝統と、日常×科学の見せ方の巧さ。社会・人文も含めた幅広い題材で存在感。
- 日本
- 身近×ガチ検証の好例が多い。2024年には「哺乳類の肛門呼吸」の研究チームが生理学賞、2025年には「牛にシマウマ縞→虫刺され半減」で生物学賞と“らしさ”が続く。
Q&A:よくある疑問
Q1. 公式に“国別通算ランキング”はある?
A. 主催者公式サイトは年次の受賞一覧(国タグ付き)を公開していますが、国別通算表は常設していません。長期の俯瞰にはTPACのような学術的整理が役立ちます。
Q2. 「日本はノーベル賞よりイグノーベル賞が多い」って本当?
A. SNS等で話題になりますが、比較の前提(分野・年次・国籍/所属・計数法)がバラバラだと誤解を生みます。イグノーベルは“複数国・複数学際”が普通なので、単純比較は要注意。評価するなら同じルールで並べるのが鉄則です。根拠のない“断言”は避けましょう。
Q3. 直近だけの“最新ランキング”は?
A. 今年(2025年)は、心理学(ポーランド/豪/加)、栄養学(ナイジェリア/トーゴ/伊/仏)など多国籍受賞が目立ち、日本は生物学賞で継続受賞。「重複計上」の直近5年集計を作ると、欧州+アフリカ+アジアの広い分布が見えてきます。
まとめ
- 長期の累積で見れば、米・英・日が3強(TPACのfirst-named方式)。これは研究主導国の姿を映すミラーです。
- 直近の勢いで見れば、多国籍化の波がはっきり。アフリカや東欧の国名も前年より増え、世界の裾野が確実に広がっています。
- 日本の強さは継続中。2024年で18年連続、2025年で19年連続。「身近×ガチ検証」の組み合わせが世界に伝わり続けています。
最後に——イグノーベル賞は笑いのためのネタではなく、「笑って、そして考えさせる」実在の研究を称える賞です。
“国別ランキング”は競馬の順位表ではなく、科学文化の地理的分布を眺める地図。正しいルールで楽しく“読み解く”──それがこの賞のいちばん良い楽しみ方だと、私は思います。
出典・参考(主要)
- TPAC(ジョージア工科大学)「Bibliometric Analysis of the Ig Nobel Prizes」:集計方法/国別シェア(US 34%、UK 14%、日本 12%;first-namedでもUS 32%、UK 12%、日本 11%)、対象は1992–2015。tpac.spp.gatech.edu
- Annals of Improbable Research「Past Ig Winners」:各年の受賞一覧と受賞国タグ(最新2025年を含む)。Improbable Research
- nippon.com「イグ・ノーベル 18年連続で日本人受賞」(2024年9月):連続受賞の年次確認に。Nippon.com
- FNNプライムオンライン(2025年9月):2025年の日本(生物学賞)受賞と19年連続の報道。FNNプライムオンライン
- Wikipedia「List of Ig Nobel Prize winners」:年次の受賞詳細の確認に(最新更新)。ウィキペディア
この記事は2025年9月26日時点の公的ページと主要メディアの情報に基づき作成しました。以後の更新で内容が変わる可能性があります。