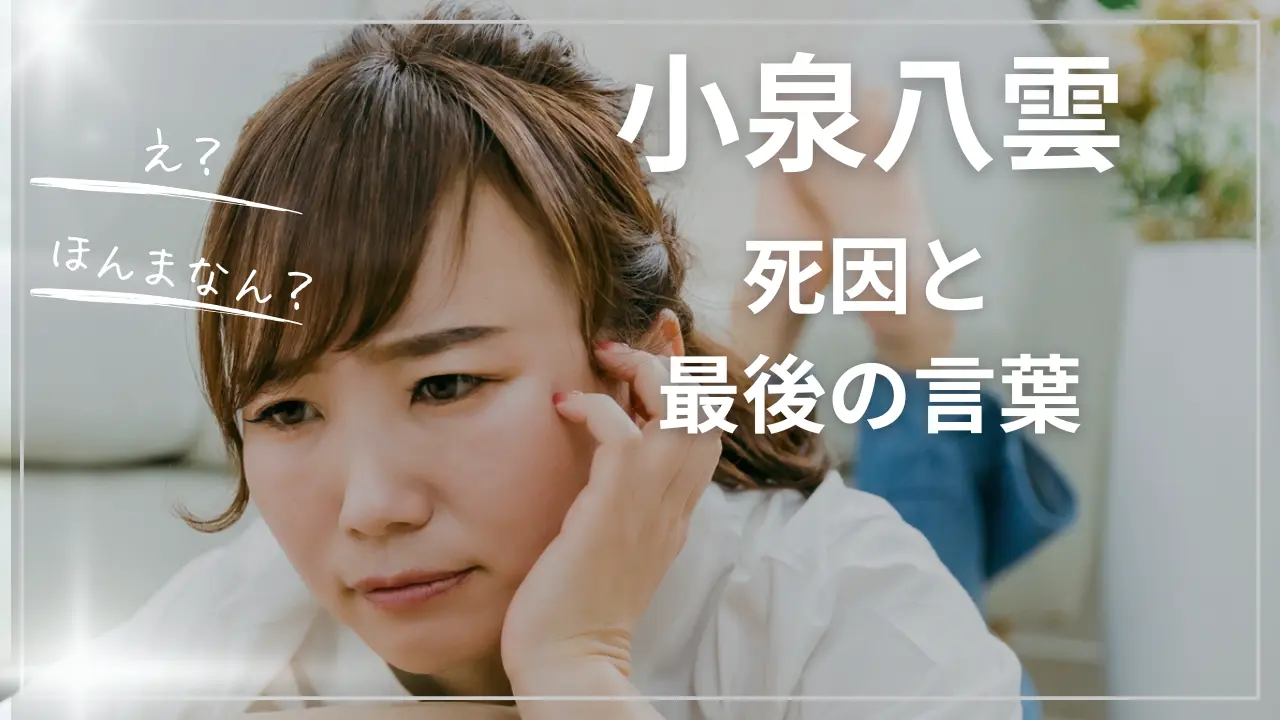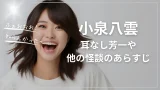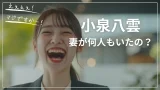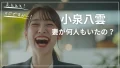—なぜ名作『怪談』の語り部は54歳で急逝したのか
この記事のポイント
はじめに——“幽玄”を愛した異邦人の、静かな幕切れ
『耳なし芳一』『雪女』など、日本の怪談を世界に広く伝えた小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。彼は壮年のうちに突然この世を去りました。
晩年は多忙を極め、講義・執筆・家族との生活が重なる日々。そんな中で彼を襲ったのは心臓の激しい痛み——当時「狭心症」と呼ばれた症状です。1904年9月26日、東京の自宅で発作が起き、54歳で静かに息を引き取ります。
本記事では、確かな史料に基づいて「死因」「亡くなる前の様子」「最後の言葉」について丁寧に解説します。あわせて、遺言めいた言葉が語られた背景や、死生観ににじむ八雲の人柄にも触れます。
死因は「狭心症」
何が起きたのか
公的な年譜や事典類は、死因を「狭心症」(心臓発作)と明記します。亡くなったのは1904年(明治37年)9月26日、場所は東京。年齢は満54歳でした。
海外資料にみる表現—“paralysis of the heart”
当時の英語圏の記述には“paralysis of the heart(心臓まひ)”という表現も見られます。現代医学の分類では、狭心症発作や急性心不全に相当する語が、時代の言葉づかいとして“paralysis”と記されたと理解できます。いずれも急性の心疾患で亡くなった点では一致しています。
まとめ:国内史料=「狭心症」/英語圏の同時代記述=「心臓まひ」。用語は揺れても、“急性の心臓の異常で急逝”という事実は共通。
最後の一週間に何があったか——妻・セツの回想
発作の“予告”のような会話
亡くなる1週間ほど前(9月19日頃)、八雲は妻・セツに、骨壺や埋葬方法、家族への気遣いまでを語っています。いわば「遺言めいた言葉」です。
そこには、「泣いてはいけない」「小さい瓶を買って骨を入れ、田舎の淋しい小寺に埋めてほしい」「知らせは要らない」など、家族思いで慎ましい願いが並びます。これはセツや近親者の口述・回想を基にした伝記に収められ、今日に伝わっています。
この文体は、夫婦が日常で使った“ヘルンさん言葉”(助詞や活用を気にせず通じるよう工夫した日本語)に近く、不器用だが真心のこもった日本語として知られます。
9月26日夜“最後の言葉”
そして亡くなる当日の夜。セツの回想によれば、八雲は書斎の廊下を散歩した後、穏やかに戻ってきて小声でこう告げます。
「ママさん、先日の病気また参りました」
その後、胸に手を当てて部屋の中を歩き、寝床に横たわると間もなく帰らぬ人になった——と記されています。これが、伝わるかぎりもっとも確かな“最後の言葉”です。
注意:ネットでは「ああ、病気のため!」など別の“名台詞”が紹介されることもありますが、一次資料(妻の回想)と照らすと信憑性に乏しいと考えられます。最も根拠のある言葉は、上の「ママさん…」の一節です。
なぜ急逝したのか——「忙しすぎた晩年」を読み解く
退職、再就職、そして執筆ラッシュ
八雲は1903年に東京帝国大学を退職し、翌1904年4月から早稲田の前身・東京専門学校で講義を始めます。
講義準備に加え、英文学・随筆・怪談の原稿依頼が重なり、創作と教育の“二足のわらじ”に。過密日程が心臓に負担をかけた可能性は、研究者や伝記の記述からも度々指摘されています。
家族の時間と、焼津の夏
ハーンは家族との時間を愛し、夏には静岡・焼津で過ごすことが多く、離れている間はセツと“ヘルンさん言葉”の手紙を交わしました。
これら書簡や回想は、温厚で家庭人の一面を伝えます。それだけに、幼い子ども4人を残した急逝は家族にとって痛恨でした。
「死」と向き合う姿勢——遺言めいた言葉が語るもの
簡素さ、匿名性、そして“悲しまないで”
遺骨を「小さい瓶」に入れ、田舎の小寺にひっそりと——この願いは、華美を避け、名を残すことにも執着しない八雲の価値観を映します。
妻と子どもに「泣く、決していけません」「子供とカルタして遊んでください」と諭す言葉には、家族の暮らしが、悲嘆よりも大切だという思いが読み取れます。
仏教への親近と“無常”の感覚
晩年の八雲には、仏教的な死生観への親近が指摘されています。直接の著述ではなくとも、最晩年の様子を伝える研究は、彼が静かに無常を受け入れた人物像を示します。
遺言めいた言葉の“簡素さ”も、その延長線上にあると考えられます。
その後——葬送と墓所、そして現在
葬られた場所
八雲は東京・雑司ヶ谷霊園に葬られました。のちに妻・セツの墓も近くに建てられ、今日も静かな木立の中で並んで眠る姿を見ることができます。
ゆかりの地としては、松江・熊本・神戸・東京に旧居や記念館が残り、彼の足跡を辿ることができます。
残された家族と作品
4人の子は、父の死後も母と共に暮らし、講義ノートの整理や回想が進み、『怪談』をはじめとする作品群は国内外で読み継がれていきます。
「日本のこころ」を世界に伝えた語り部の歩みは、今も記念館や研究会、出版物によって更新され続けています。
「最後の言葉」をどう受け取るか——読者へのヒント
歴史上の人物の“最期のひと言”は、しばしば脚色や伝聞で姿を変えます。小泉八雲の場合、最も信頼できる一次情報は妻・セツの回想(口述)に依拠する伝記部分です。
そこに残る「ママさん、先日の病気また参りました」は、華やかさはないけれど、日常の延長にある静かな現実感をたたえています。
私たちはつい“名台詞”を求めがちですが、八雲の誠実な生活者としての横顔は、むしろこの素朴なひと言にこそ表れているのではないでしょうか。
よくある疑問Q&A
Q1. 本当に「狭心症」だったの?
A. 国内の主要な年譜や事典は「狭心症(心臓発作)」とします。一方、英語圏の同時代文献は“paralysis of the heart”と記しました。いずれも急性の心臓疾患を指し、結論は一致しています。
Q2. 「ああ、病気のため!」が最後の言葉という説は?
A. 出典が弱い二次・三次情報が多く、一次資料(妻の回想)に一致しません。信頼性は低いと見なされます。もっとも確かな記録は「ママさん、先日の病気また参りました」です。
Q3. お墓はどこ?
A. 雑司ヶ谷霊園(東京)です。文学散歩の定番スポットとしても知られています。
まとめ——別れの言葉は、暮らしの言葉
八雲の“最後のひと言”は、劇的な名台詞ではありません。しかし、日々の延長線上にある、小さな呼びかけでした。だからこそ心に残ります。
私たちが彼の作品を読み、暮らしの中でふと立ち止まるとき——その静かな声は、今も確かに届いてくるのです。
参考にした主な史料(読みやすい順)
- 年譜・事典等:死因・没年月日・墓所の確認に使用。ウィキペディア
- 同時代英語資料:死因表現“paralysis of the heart”の確認。The Atlantic
- 関連解説:夫婦の“ヘルンさん言葉”や晩年像。Nippon
※「最後の言葉」については、一次情報(妻の回想の口述を収めた伝記部分)に基づく記録を優先し、出典不明の名台詞は取り上げませんでした。必要に応じ、原文に近い記録(活字資料・美術館資料)へあたると確実です。hearn-museum-matsue.jp
付記:ゆかりの地へ
松江の小泉八雲記念館・旧居、熊本・神戸・東京の各所にも足跡が残ります。文学散歩や資料館の展示は、晩年の心情や家族との時間をより立体的に感じさせてくれます。旅の計画の際は、各施設の最新情報をご確認ください。hotel-nagata.co.jp