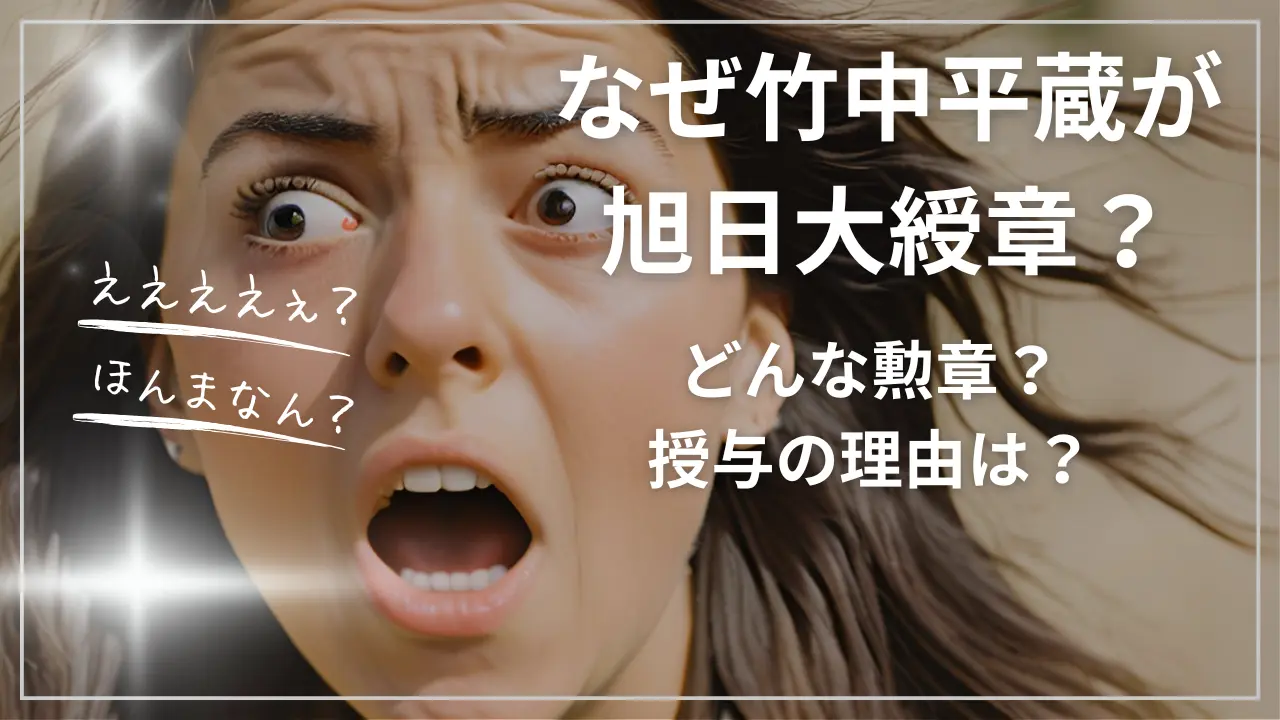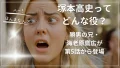2025年11月3日、「秋の叙勲(あきのじょくん)」として政府から発表された受章者の中に、元総務相で経済学者の竹中平蔵(たけなか・へいぞう)さんの名前がありました。
授与されたのは、日本の勲章の中でも上位にあたる「旭日大綬章(きょくじつだいじゅしょう)」です。
ニュースを見た多くの人は、こんなふうに思ったはずです。
この記事では、
- 旭日大綬章とはどんな勲章か
- 叙勲(勲章をあげること)は、どういう仕組みで決まるのか
- 竹中平蔵さんとはどんな人物で、何をしてきたのか
- 今回の受章理由として、公式に説明されているポイント
- 世間で賛否が分かれている背景
を順番に整理していきます。
今回のニュースをざっくり整理
まずは、今回の動きをかんたんにまとめます。
一方で、X(旧Twitter)などのSNSでは、
- 「構造改革で生活が苦しくなったのに、なぜ勲章?」
- 「評価すべき功績もあるが、格差を広げた面も見逃せない」
といった賛否両方の意見が一気に噴き出し、関連ワードがトレンド入りしました。
ここから先は、
- 「勲章そのものの意味」
- 「竹中さんが何をしてきた人なのか」
を見ていくことで、「なぜこの人に旭日大綬章なのか?」を、感情論の前に一度整理してみようというスタンスで話を進めます。
旭日大綬章ってどんな勲章?
「旭日章」というグループの一番上
日本の勲章にはいくつかの種類がありますが、そのひとつが「旭日章(きょくじつしょう)」です。
内閣府の説明によると、旭日章は明治8年(1875年)に、日本で最初に作られた勲章で、
「社会のさまざまな分野で顕著な功績(目立つほど大きな功績)を挙げた人」に対して、男女共通で授与されるものだとされています。
旭日章にはランク(等級)があり、
- 旭日大綬章(だいじゅしょう)
- 旭日重光章
- 旭日中綬章
- 旭日小綬章 …など
と分かれています。その中で一番上に位置するのが「旭日大綬章」です。
どんな人が対象になるの?
旭日大綬章の授与基準は、閣議決定された「勲章の授与基準」によると、
- 主に、内閣総理大臣・衆参両院議長・最高裁長官クラスの人で顕著な功績を挙げた人
- あるいは、それに準じるクラスの人で、政治・行政・経済などで特に大きな功績を残した人
が対象とされています。
ただし実際には、
- 元都道府県知事
- 大企業の経営者
- 労働組合の幹部
- 各分野で長年活躍した著名人
などにも授与されており、「国や社会にとても大きく貢献した人に贈られる上位の勲章」というイメージでとらえるとわかりやすいです。
授与式はどこで行われる?
旭日大綬章クラスになると、皇居の「松の間(まつのま)」で行われる親授式(しんじゅしき)で、天皇陛下から直接勲章を受ける形になります。
ここまでをまとめると、
旭日大綬章=「国や公共に対して特に大きな功績を残した人」に与えられる
旭日章の中で最上位クラスの勲章
というイメージです。
「秋の叙勲」ってどうやって決まるの?
年2回の「春の叙勲」「秋の叙勲」
日本では、毎年 春と秋の2回、政府が叙勲の受章者を発表します。
- 春:主に「春の叙勲」
- 秋:主に「秋の叙勲」
今回の竹中さんの受章は、2025年秋の叙勲にあたります。
どのくらいの人数が受章するの?
2025年秋の叙勲では、
- 合計3963人が受章
- 桐花大綬章(きりのはなおおじゅしょう):2人
- 旭日章:935人
- 瑞宝章:3026人
と報じられています。
竹中さんを含む旭日大綬章の受章者は、政治・行政などの分野で功績のあった一部の人たちで、その中には、
- 前熊本県知事の蒲島郁夫さん
- 高市早苗首相の夫で元衆院議員の山本拓さん
なども含まれています。
誰が決めているの?
叙勲は、
- 各省庁や関係機関が「この人を推薦したい」と候補者を出す
- 内閣府の賞勲局などが中心となって審査
- 閣議(内閣の会議)で決定
- 勲章は天皇陛下から親授(しんじゅ)される
という流れで決まります。
このプロセス自体は毎年行われる公的な制度であり、
「誰か一人の好みで突然決まる」というようなものではありません。
竹中平蔵ってどんな人?
次に、「そもそも竹中平蔵ってどういう人物なの?」という点を整理します。
経済学者から政治の世界へ
Wikipediaなどによると、竹中平蔵さんは、
- 1951年生まれ、和歌山県和歌山市出身
- 一橋大学経済学部を卒業後、日本開発銀行・大蔵省研究所などを経て、
大阪大学・慶應義塾大学などで経済学の研究者・教授として活動 - その後、慶應義塾大学総合政策学部教授などを務める
という「元々は学者畑の人」です。
小泉政権の“構造改革の顔”
政治の世界では、小泉純一郎政権(2001〜2006年)の中枢で活躍しました。
主なポストは、
- 経済財政政策担当大臣
- 金融担当大臣
- 郵政民営化担当大臣
- 総務大臣
など。
特に、
- 不良債権処理(銀行が抱えていた「返ってこなさそうなお金」の整理)
- 郵政民営化
- 規制緩和・構造改革
といった「痛みを伴う改革」の旗振り役として知られました。
このため、
- 「日本経済を立て直そうとした改革派の象徴」
と評価する人もいれば、
- 「格差や非正規雇用を広げた張本人」
と強く批判する人もいて、もともと賛否の激しい人物でもあります。
なぜ竹中平蔵が旭日大綬章?
公式に説明されている授与理由
では、本題の「なぜ旭日大綬章なのか」です。
経済系メディアなどの報道によると、政府側の公式な説明としては、主に以下のポイントが挙げられています。
- 小泉政権下で、経済財政政策担当相・総務相などとして「構造改革」を推進したこと
- 不良債権処理や、公共事業削減など、日本経済の立て直しに関連する政策を担ったこと
- 経済学者として、国際的にも日本の経済政策や経済学研究に貢献してきたこと
ある報道では、政府は叙勲理由として
「長年にわたる経済構造改革の推進、および国際経済学への貢献」
といった内容を挙げているとされています。
つまり、評価されているのは「構造改革の功績」や「経済政策・研究への貢献」です。
もちろん、この「功績」をどう見るかは人によって大きく違いますが、
「政府がどういう点を評価しているのか」という意味では、
- 政治家・大臣としての役割
- 経済学者としての長年の活動
がセットで見られている、というイメージを持っておくと良いでしょう。
世間の声は? 賛成と反対が割れる背景
今回の受章で特徴的なのは、世論の反応がものすごく割れていることです。
「評価する」側の声
評価・賛成の立場からは、たとえばこんな見方があります。
- 1990年代以降、日本経済が低成長に苦しむ中で、
「不良債権処理」「老朽化した制度の見直し」など嫌われ役の仕事を引き受けた - 国際的な経済学の場でも発言してきて、日本の立場を発信してきた
- 結果がどうであれ、「何もせず現状維持」ではなく、改革にチャレンジしたこと自体は評価すべき
このように、
「痛みを伴う改革だったが、長期的には必要だった」
という文脈で、功績を重く評価する声があります。
「反対・批判」側の声
一方で、批判・反対の立場からは、こうした意見が根強くあります。
- 労働者派遣法の改正などの影響で非正規雇用が増え、格差が拡大したとする見方
- 公共事業削減や三位一体改革などが、地方経済や生活を苦しめたという批判
- 「構造改革」の名のもとに、弱い立場の人にしわ寄せが行ったのではないか、という感覚
SNS上では、「竹中平蔵」「旭日大綬章」などのワードがトレンド入りし、
- 「格差の象徴に勲章を与えるのか」
- 「自分の生活が苦しくなった原因の一つだと思っている」
といった声も数多く見られました。
なぜここまで賛否が分かれるのか
ここまで賛否が分かれてしまう背景には、少なくとも次の3つのポイントがあると考えられます。
- 改革の「メリット」と「デメリット」が、違う人に違う形で現れた
- 恩恵を受けた企業・人もいれば、ダメージを強く感じた人もいる
- 影響が短期ではなく「20年単位」で続いている
- 雇用のあり方や賃金の水準など、今もなお影響が残っていると感じる人が多い
- 経済政策の評価は、数字だけでは決めきれない
- 成長率・失業率だけでなく、「安心感」「将来への不安」など感情面も評価に入りやすい
そのため、「功績だ」と思うか「失敗だ」と思うかは、
自分がどの立場・どの経験から日本の2000年代以降を見てきたかで大きく変わります。
「なぜ勲章?」を考えるための視点
ここまでの話を踏まえて、「なぜ竹中平蔵に旭日大綬章?」という疑問に向き合うとき、
次のような3つの視点を持っておくと、感情だけに流されずに考えやすくなります。
叙勲制度は「評価の物差し」が限られている
叙勲制度は、
- 「長年の功績」
- 「社会への貢献度」
を中心に評価する仕組みです。
そのため、
- 「誰かの人生を苦しめた政策だったか」といった、細かい影響の分布まで
ていねいに評価してくれる制度ではありません。
逆に言うと、
「叙勲された=その人のすべてが肯定された」
というわけではなく、
「特定の観点から見た功績が高く評価された」というサインに過ぎない、とも言えます。
同じ出来事でも「評価軸」が違うと結論も変わる
たとえば、竹中さんの構造改革を、
- 「財政の立て直し」や
- 「企業の競争力アップ」
という軸で見ると、プラス面が大きく見えるかもしれません。
しかし、
- 「雇用の安定」
- 「地方や弱い立場の人の暮らし」
という軸で見ると、マイナス面が大きく見えることもあります。
つまり、
同じ政策でも、「何を大事にするか」で評価が変わる
ということです。
勲章をきっかけに「過去の政策を学び直す」チャンス
今回の受章は、多くの人にとって
- 「なんとなくニュースで聞いていた“構造改革”って、実際どういうことだったの?」
- 「非正規雇用って、なぜこんなに増えたの?」
といった疑問をあらためて考え直すきっかけにもなっています。
勲章そのものに賛成か反対かは別として、
- 「あの時期の政策が、今の生活や働き方にどう影響しているのか」
- 「自分はどんな社会を望むのか」
を考える材料として、このニュースを使うこともできるはずです。
まとめ
最後に、この記事のポイントを整理します。