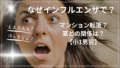市川新之助さんについて語るとき、まず大前提としておさえておきたいのが
「まだ小学生〜中学生世代の“成長途中の役者さん”である」
という点です。この記事では、ゴシップや噂話ではなく、公に報じられている舞台・インタビューなどをもとに「評判」と「実力」を整理していきます。
- どんな初役からスタートしたのか
- どんな作品で経験を積んできたのか
- 観客や専門家からはどんな評価を受けているのか
を、できるだけ時系列でたどっていきますね。
① 市川新之助ってどんな人?
まずプロフィールをざっくり。
- 屋号:成田屋
- 襲名名:八代目 市川新之助
- 本名:堀越 勸玄(ほりこし かんげん)
- 生年:2013年3月22日生まれ(まだ10代前半)
- 父:十三代目 市川團十郎白猿
- 母:フリーアナウンサーとして活躍した小林麻央さん
「新之助」という名前自体が、成田屋にとってとても重い“名跡(みょうせき)”。
団十郎の直系が受け継いできた、看板中の看板です。
② 幼少期〜堀越勸玄としての初舞台
新之助を語るとき、じつは「堀越勸玄(ほりこし かんげん)」としての活動時代も外せません。
◆ きっかけは父・海老蔵(現・團十郎)の公演
長男として生まれた勸玄くんは、幼いころから舞台のそばで育ち、
父・海老蔵(当時)の舞台で少しずつ出演機会を増やしていきました。
- 歌舞伎座や各地の公演で、童子役や子ども役として登場
- 花道を一緒に歩いたり、セリフをもらったりしながら経験を積む
この頃からすでに、
「度胸がある」「物おじしない」
といった声が、観客やメディアから上がっていました。
③ 2022年:八代目 市川新之助として初舞台
◆ 襲名と初舞台は「十三代目市川團十郎白猿 襲名披露」とセット
2022年11〜12月、歌舞伎座で行われたのが
「十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目市川新之助初舞台」
という超ビッグイベント。
- 父が十三代目 市川團十郎白猿を襲名
- 長男の勸玄くんが「八代目 市川新之助」として初舞台
歌舞伎座での襲名披露は2か月にわたる長丁場。
テレビCMも作られ、日本の伝統芸能の「大きな節目」として話題になりました。
◆ 評判:プレッシャーの中でも堂々
この初舞台では、
- 小さい体でありながら、しっかり通る声
- 表情が豊かで、かわいらしさと凛々しさが混ざった存在感
- 所作がきちんとしており、「仕込まれている」と感じさせる動き
などが、新聞・ネットニュースでポジティブに取り上げられました。
もちろん、「名跡の重さ」に対する世間の期待や、
父への注目も相まって、かなり大きなプレッシャーがあったはずです。
それでも舞台では、緊張よりも「楽しんでいる感じ」が伝わってきた、という声が多く見られました。
④ 2022年末:「毛抜」での大役に挑戦
初舞台から間をおかず、同じく2022年12月の「十二月大歌舞伎」では、
『毛抜(けぬき)』の粂寺弾正(くめでら・だんじょう)を史上最年少で勤めています。
この役は、ユーモアも色気も必要な人気の立役。
腰元たちを口説く色っぽい場面もあり、子どもにはかなり難しいポジションです。
◆ 評価ポイント
- 「愛嬌たっぷり」「色っぽいシーンも嫌味がない」
- 花道での挨拶も、ハキハキとして堂々
- 観客から大きな拍手が送られた
と、メディアの記事でも好意的に報じられました。
ここで早くも、
「セリフ回しのテンポが良い」
「観客との“間”をつかむのが上手い」
といった、将来の“座長候補”らしい評価もチラホラ出てきます。
⑤ 2023年:全国巡業や新作・イベントで経験値アップ
◆ 襲名披露興行は“2年がかり”
2022年の歌舞伎座を皮切りに、
「十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目市川新之助初舞台」は、
各地の劇場を回るかたちで約2年間続きました。
- 東京・歌舞伎座
- 大阪松竹座
- 博多座、南座、地方都市の巡業公演 など
この間、新之助は親子共演を重ねながら、
役の大きさや難易度も少しずつステップアップさせていきます。
◆ トークや会見でも“しっかり者”ぶり
記者会見や公演発表の場でも、
- 丁寧な言葉遣い
- 大人顔負けのコメント力
- でも子どもらしい笑顔や茶目っ気
が印象的で、「受け答えがしっかりしている」とたびたびニュースになりました。
役者としてだけでなく、「公の場に立つ人」としての訓練も、
かなり意識されているのが分かります。
⑥ 2024年:『連獅子』で初役に挑戦(大きな転機)
2024年秋、大阪松竹座「十月大歌舞伎」では、
親子で『連獅子』に挑戦しました。
- 父・團十郎:親獅子の精
- 新之助:初役で仔獅子の精
『連獅子』は、歌舞伎の中でもとくに人気の高い演目で、
- 体力勝負の毛振り(長い毛を振り回す動き)
- 親子の情や成長を描くドラマ
- 舞踊としての格の高さ
などが求められる、まさに“看板級”の演目です。
◆ 評判:観客を魅了した毛振りと存在感
公演レポートでは、
- 親子で息の合った毛振りを見せた
- 初役ながら、堂々たる仔獅子ぶり
- 客席からは「万雷の拍手」「総立ち」といった表現が出るほどの熱気
と、非常に高い評価がされています。
新之助本人も取材で、
「初役ですが、楽しくてあっという間でした」
と語っており、「キツさ」よりも「楽しさ」を口にしているのが印象的です。
このあたりから、
「舞台が好き」「踊りが好き」
という気持ちそのものが、演技の芯になりつつあるように感じられます。
⑦ 歌舞伎以外の仕事:声優やイベント出演
◆ アニメ映画の吹き替えに挑戦
フランスのアニメーション映画『古の王子と3つの花』では、
吹き替え声優に初挑戦しています。
インタビューでは、
- 「一生懸命に勤めます」
- 「新しい経験を楽しみたい」
とコメントしていて、
歌舞伎以外の表現にも前向きに取り組んでいる様子がうかがえます。
◆ 社会活動・イベントにも参加
環境保全プロジェクト「ABMORI」のキックオフイベントに、
團十郎さん・ぼたんさんとともに参加した様子も報じられています。
ここでも、新之助は
- 落ち着いた表情で挨拶
- 周囲に気を配りながら作業に参加
している様子が取り上げられ、
「まだ小さいのに、きちんとしている」
といった印象を残しています。
⑧ 市川新之助の「実力」はどう評価されている?
ここからは、これまでの公演や報道をもとに、
新之助の「実力」を、いくつかのポイントに分けて整理してみます。
1)セリフ回しと声
- 声がよく通る
- 早口になりすぎず、テンポが良い
- 花道での挨拶や口上もハッキリ聞こえる
という評価が多く、
歌舞伎役者として重要な「声の力」は、すでにかなり高いレベルにあるといえます。
2)所作・立ち居振る舞い
成田屋の子として幼い頃から仕込まれていることもあり、
- 礼の仕方
- 歩き方
- 視線の置き方
などの基本動作がとても美しい、とよく言われます。
『連獅子』のような舞踊でも、足腰の強さやバランスの良さが目立ちました。
3)存在感と愛嬌
- 舞台に立ったときの「華」
- 観客の視線を自然に集める力
- 子どもらしい愛嬌と、成田屋の跡取りらしい凛々しさの両立
このあたりは、血筋や環境だけでなく、
本人の性格や感性による部分も大きいでしょう。
『毛抜』での愛嬌たっぷりの演技や、
『連獅子』での仔獅子ぶりを見ると、
「“役者の顔”をしている」
と言われるのも頷けます。
4)プロ意識とコメント力
会見やインタビューでの発言からも、
- 「襲名の重みを理解しようとしている」
- 「見てくださるお客様への感謝をきちんと言葉にできる」
といった、プロ意識の高さが感じられます。
この「言葉の力」は、将来座頭として座組を引っ張るときに、
とても大事な資質になります。
⑨ 「評判」は?世間の目と専門家の目
◆ 観客・メディアからの評判(ポジティブ面)
これまでの報道やSNSの反応をざっくりまとめると、
- 「かわいいだけじゃなくて、本当に上手」
- 「目が印象的で、舞台で映える」
- 「父に似ているところもありつつ、自分の色が出てきている」
- 「将来の団十郎として楽しみ」
といった、期待を込めたポジティブな声が多い印象です。
◆ 一方で意識したいこと(中立的な視点)
- まだ10代前半で、身体も心も成長途中
- 家の名跡や世間の注目が非常に大きい
- 本人のペースを尊重することが大事
という点も、忘れてはいけません。
「評判」を語るとき、どうしても
「将来の団十郎としてどうか?」
という視点が中心になりがちですが、
いまはまだ「一人の子ども役者としてどんな経験を積んでいるか」を
あたたかく見守る段階とも言えます。
⑩ これからの課題と楽しみなポイント
最後に、今後の成長が楽しみなポイントを整理してみます。
◆ 1)レパートリーの広がり
- 立役(男の役)だけでなく、子どもらしい役・女方寄りの役など
- 古典だけでなく、新作歌舞伎や外部作品
など、これからどんな役に挑戦していくかが楽しみです。
◆ 2)身体づくりと体力
『連獅子』のような体力勝負の演目に挑戦したことで、
筋力や持久力はこれからさらに必要になってきます。
- 成長期の身体をどう鍛え、どう守るか
- 忙しいスケジュールの中で、休息とのバランスをどうとるか
といった点も、大きなテーマになるでしょう。
◆ 3)「新之助らしさ」の確立
成田屋の伝統を受け継ぎながらも、
- 表現の細やかさ
- 殺陣や舞踊のクセ
- セリフの抑揚
などに「新之助らしさ」が出てくるのは、これからの数年〜10年の話です。
「父に似ている」と言われる時期を経て、
どこかのタイミングで
「あ、これは“新之助の芝居”だ」
と感じさせる瞬間がきっと来るはずです。
まとめ
ここまで時系列でざっと追ってきた内容を、一言でまとめると
「名跡にふさわしい素質を十分に感じさせる、“伸び盛り”の若手歌舞伎役者」
という表現がいちばんしっくりきます。
- 声・所作・存在感ともに、年齢以上のレベル
- 大きなプレッシャーの中でも、楽しさを忘れない姿勢
- 観客やメディアからの評判も、おおむね好意的
- まだまだ成長途上で、今後10年でガラッと変わっていく可能性大
という意味で、「今」の姿に期待しすぎて結論を急ぐよりも、
「毎年、どんな役に挑戦するのか」
「舞台での表情がどう変わっていくのか」
を長い目で追いかけるのがおすすめです。